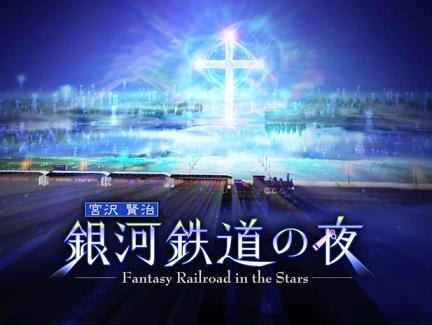2007/07/14 記
BCG(ボストンコンサルティンググループ)社長、年収2億円の高給取り。
その地位・給与を全て未練なく捨てて、新たな日本の明日のソニー・ホンダを100社育てようと立ち上がった男がいた。
1945年兵庫生まれ。 東京大学法学部卒、読売新聞、三菱商事を経て、80年ハーバード大学院MBA取得。 2000年DI(ドリームインキュベータ社)設立。・・・その男の名 堀 紘一
本屋で何気なく手にした本、チョット高いなぁ~と思いつつ、表題に惹かれ購入。(俺も単純だなぁ~と思いつつ。) 時代と社会の閉塞状況を、経済の時点・ビジネスの観点から打ち破ろうとの心意気に惹かれる。
『チャレンジ・イズ・ライフ=人生とは挑戦なんだ。』
『よ~し、やるぞ!』 との思いが湧いてくる。
以下、冊子の中から気迫ある言動の幾つかをポイントのみ列挙してみよう。
元気をなくした方には、励みともなり、 これから何かやろうとしている方々にとっては、何等かのヒントが得られるかも知れない。
*************************************
・21世紀の日本が良くなるためには、とにかく皆が未だ誰もやったことがない新しいことにチャレンジしていく以外に道はない。 出来るできないではない、大事なのはチャレンジするかしないかだ。 夢がもてるかどうかだ。
・明治大学ラグビーは、重量級フォーワードがスクラムを組み、どこまでも押していく。 早稲田大学ラクビーは、バックスの展開の早さスピードで勝負した。 企業で言えば、フォーワード=大企業で、官民一体の護送船団方式での戦略システムでやってきた。
・21世紀日本に必要なのは、ビジネスマンでなくビジネスパーソンであり、ラクビーの戦略で言えば、新生全日本チームのコンタクト方式の戦い方である。 経営者から現場の労働者に至るまで、男も女も、日本人も外国人も、年齢も学歴も関係ない。 それぞれが、それぞれの納得済で配置されたポジションに応じた力をフルに発揮、連動させ合って初めて成功への道を歩き始めることができる。
・経営者は何も新しいことに挑戦しようとせず、事なかれ主義が多く、なんとか三期六年間の任期を無難に勤めあげようと計算している。
・コンタクト方式とは、自分の方からぶつかっていく方式である。 明治大学方式はぶつかりあいでなく押し合い、早稲田大学方式は、相手の間を縫って走り抜ける典型的“避”コンタクト戦法である。
同じぶつかり合いでもこちらから当たりに行く方が、当たられるよりよほど痛みも少なく、怪我もしないものである。
・減点主義の人事評価を止めて、足し算も加味する野球方式へ変えることだ。
敗者が復活できる社会システムをつくる事だ。
・大企業でもベンチャーでも、経営者がやるべきことは、どうやって社員が攻めの姿勢になり、自分から当たりにいく様になるか仕掛けることである。
社長というのは、「変化の仕掛人」でなければならない。
ともかく高い志を持ち続け、失敗など恐れずに。 転ぶ前から転ぶことを考えていたのでは何も出来ない。 大切な事は、事業アイデアの内容、可能性の大きさ、経営者のエネルギー、視座の高さである。
いつの時代でも、夢をもった前向きの人間が集まっている組織は強い。
志の高いビジネスパーソンたちが、心を一つにして共通の目的を目指す企業は、いつだって成功する確率はグッと高くなる。
この様な一体化した組織づくりができるトップの条件を一つだけ挙げよと言われたら私は「私欲を捨てられることだ」と答えたい。 本気で世のため人のために頑張れるかどうかである。 凡そ戦力になりそうな人間は、器の小さなトップには忠誠心などもちはしない。
今の日本は、あらゆる面に私利私欲が強すぎる。
自己主張すると生意気だと疎んじられ、上司に迎合すると「憂いやつ」だと引き立てられる。
しかも上から下まで失敗を恐れ、何も新しいことにチャレンジしようとしない。
それで経営が苦しくなると、経営責任を棚上げしてリストラを大義名分に社員の首を切る。
会社の私物化、私利私欲、公私混同と言われてもいたしかたない。
日本が変わるには、会社が変わらなければならない。 会社が変わらなければ個人が変わる必要がある。 21世紀にはサラリーマンは死滅する。 これからは、ビジネスパーソンの時代になる。
アイデアを出し、ヒト・モノ・カネを集めてビジネスをプロデュースしていく人間でなければ通用しなくなる。
ビジネスパーソンであれば、組織を硬直化させることはない。 組織をより進化させることが出来る。 それを拒否するような組織なら自らでていけばいい。
夢を持て! 大志を抱け! 若いうちは貯金なんかするな! 使える金は全て自分に投資せよ!
失敗を恐れるな! 命まではとられない。 チャレンジしろ! 失敗したら必ずそこから何かを学べ!
考え抜くことができるかできないかで、雲泥の差がつく。考えることにかねはかからない。
最後の1センチを考え抜けるかどうかだ!
変化する時間が速ければ速いほど、スピードが勝敗の決め手となる。
規模が商社の条件とはならなくなった。
「チャレンジ・イズ・ライフ=人生とは、挑戦である。」
「ドリーム・イズ・ライフ=夢があるから人生である。」
私たちがやらなければならないのは、まだ誰も予測することが出来ない未来への壮大なる挑戦なのだ。 肝心なのは、失敗など恐れず、夢の実現に向って体当たりでぶつかっていくチャレンジ精神なのだ。 ・・・・・・・以上、ポイント要約。
なるままに記
かっこ良く言えば、正しく、自分が考え、言わんとしてきたことが網羅されていたと言える。
(否むしろ、こう有りたいとの願望とも言うべきものを、ここに見出したと言うべきか?)
起業であれ、NPOであれ、はたまたボランティアであれ、一つの生きる姿勢として、皆様の何らかの励みのきっかけにでもなれれば、幸いである。
ついでに言えば、上記のことは、様々な問題を起こしている各種組合や旧態依然とした態度で仕事を単にこなしている姿勢の方々にとっても同様の事が言えるのでは?
社会保険庁の組織(経営役員と自治労)における労働時間や取組む姿勢への協約問題もその一例であろう。 組合の必要性も当然であると思うが、併せて住民サービスの徹底化を図るべきであると思う。
平気で組合員の会費を遊行費や自宅増築に使ったりする幹部や、勝手に使用目的を逸脱して投資に使ったり、挙句の果てバレルと、言い訳ばかりで、きちんと明細を見せ様ともしない。 組合の新規情報も取り巻き連中ばかりに先に流し、組織防衛の名のもとに、迅速なる情報公開もしようともしない。 新規情報は、組合からより新聞報道や会社情報のほうが正確で速いという、後追い連絡で済ませているとしたら・・・最早、呆れるばかりの退廃ぶりである。
一昔前なら責任をとって切腹ものである。(チョット過激で古すぎたかな~。) 何れにせよ、かかる御仁方には、恥という言葉が無いらしい。 恐るべき時代・社会状況である。
議員における「政務調査費」なるものも国会議員のみならず各市町村でも市民オンブズマン? なるものが調査及び問題提起しているが・・・ここ糸島は大丈夫であろうか? 純粋な方々が多いこの地域では、まさかその様な大それた、いい加減な、使用は為されていないことと信じたい。