奈良3景
(博物館建物に掲げられた看板) 4月4日に出発した旅行、京都には1泊しただけで奈良に向かいました。奈良の「国立奈良博物館」では、4月3日から「大遣唐使展」が開催されていて、ここを訪れるのが今回の旅行の目的の1つです。嬉しい事に「国立東京博物館」の年間パスポートが使えるのです。「東京国立博物館」の時と同じように開館30分前の9時には列に並びました。
4月4日に出発した旅行、京都には1泊しただけで奈良に向かいました。奈良の「国立奈良博物館」では、4月3日から「大遣唐使展」が開催されていて、ここを訪れるのが今回の旅行の目的の1つです。嬉しい事に「国立東京博物館」の年間パスポートが使えるのです。「東京国立博物館」の時と同じように開館30分前の9時には列に並びました。
 遣唐使として、命がけで中国に出掛けて行った多くの人々の情熱や意気込みを感じました。新しい国作りに必要な知識・技術を学び取ろうとする、空海や阿部仲麻呂等の気魄が伝わってきます。5回の海難を乗り越え、盲となってまで日本にやって来られた鑑真和尚の絵巻も展示されていました。吉備真備の唐での活躍を描いた、”里帰り”「吉備大臣入唐絵巻」がビデオ放映されていていて、楽しく見られます。
遣唐使として、命がけで中国に出掛けて行った多くの人々の情熱や意気込みを感じました。新しい国作りに必要な知識・技術を学び取ろうとする、空海や阿部仲麻呂等の気魄が伝わってきます。5回の海難を乗り越え、盲となってまで日本にやって来られた鑑真和尚の絵巻も展示されていました。吉備真備の唐での活躍を描いた、”里帰り”「吉備大臣入唐絵巻」がビデオ放映されていていて、楽しく見られます。
平城京遷都1300年を記念して数々のイベントが企画されている事でしょうが、この「大遣唐使展」まさにタイムリーな催しと思います。
会場を巡る半ば、美しく、背丈大きい十一面観音立像に出会いました。国宝とか重要文化財との銘がありません。不思議に感じたのか妻がボランティアの解説委員の方に聞くと「最近になって、京都・安祥寺で見つかった『十一面観音立像』の初公開です」との事。帰ってきて調べると、像は9世紀に作られたもので、首の部分だけ後世にすげ替えられたものとありました。
(左保川の桜) 宿泊先そばを流れる「左保川」の両岸には桜並木が数キロに亘って連なり、見事な風景でした。
宿泊先そばを流れる「左保川」の両岸には桜並木が数キロに亘って連なり、見事な風景でした。
(法華寺本堂) 法華寺も宿泊先から徒歩15分の距離にあり、4月7日早朝に訪れ、この日までの、国宝「十一面観音立像」の特別拝観が叶いました。
法華寺も宿泊先から徒歩15分の距離にあり、4月7日早朝に訪れ、この日までの、国宝「十一面観音立像」の特別拝観が叶いました。
(法華寺境内)
唐招提寺や浄瑠璃寺にお参りする事もかない、雨にも降られず、花の大和路を巡って来られました。










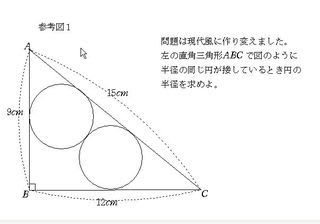



 琵琶湖疏水完成の最大の功労者田辺朔郎の立像、今回は見忘れませんでした。
琵琶湖疏水完成の最大の功労者田辺朔郎の立像、今回は見忘れませんでした。








