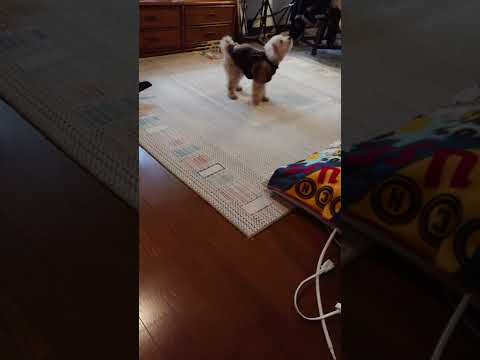*****「精神疾患シリーズ」最終回*****
私は人に「辛い!」「苦しい!」と伝えたり、悩みを相談したりした時、みなさん、私のためになると思うことを一生懸命考えて言ってくださいます。でも、ありがたいと思っているのに、なぜか、あとからモヤモヤすることがあるのはどうしてかとずっと気になっていました。
私が辛いといった時、「そうなんや…。」とか「そんなふうに思うんやね。」と相槌を打ちながら、ひたすら聞いてくださる方がいます。話を聞いてもらうことで気持ちが落ち着いてきます。人に話すことで気持ちが整理されていきます。人に聞いてもらって辛さを吐き出すというのは気持ちを軽くするのにとても効果があると思います。
悩みを相談した時、「それは心配だね。」と全部聴いてくださった後に「私に何かできることある?」と聞いていただいた時はとても嬉しく思いました。
周りの人に「辛い!」「苦しい!」と伝えたあとすぐに
「気にしすぎたらいけないよ。」
「考えすぎたらいけないよ。」
「嫌なことは忘れて、いいことだけを考えなさい。」
「誰でも辛い時はあるよ。」
「私は人に辛いとは言わないよ。」
「いつまで引きづっているの!切り替えないと!!」
「大丈夫、元気!」
「考え方、捉え方を直しなさい。」
とアドバイスしてくださいます。
どなたも、とても思いやりのあるいい方です。人生経験や知識の豊富な方々です。親身になって何とか私を楽にしてあげようと一生懸命に考えてアドバイスしてくださいます。
人から相談されたり、辛さを吐露されると自分の知識や体験から一番いいと思うことをアドバイスしようとします。アドバイスしなければいけないと思います。私自身もそうです。
それは分かるのに「どうして、こんなにモヤモヤするのだろう?」「もう話をしない方がいいの?」と思う自分がいて、「私って、ひがみっぽいのかな?」「心が狭いの?」とずっと思ってきました。
もしかしたら、双極性障害Ⅱ型の『対人過敏症』の影響もあるかもしれません。
ネットをいろいろ調べてみたら ”アドバイスはしてはいけない” と書いてあるではありませんか!それも、異口同音に!!
これには驚きました。そして、納得しました。
私はうつが酷くなると心があると思われるところが膨らんできたり、不快なものが貼り付いたりしてとても苦しく辛くなるので、吐き出さずにはいられなくなります。(ため息がたくさん出ます。)
「辛い、苦しい!」と声をかけて、どのように辛いのか、苦しいのかを聴いていただく前にすぐにアドバイスしていただくとそれ以上話せなくなってしまいます。
めるもコミュニケーション総合研究所代表理事 松橋良紀さん
やってはいけない「励まし方」、効果的な「励まし方」
ここに書かれている『心にたまった泥水を捨ててもらうこと。泥水を吐き出さなければ、きれいな水は入らない。』は目からウロコでした。
『相手が悩み事や愚痴を他人に打ち明けるときというのは、心のバケツに泥水がたまって溢れている状態です。
心のバケツがいっぱいの状態では、きれいな水を受け入れる余裕がないということです。どんなアドバイスも励ましも、受け取れる状態ではないのです。
まずは心の中の泥水を、すべて吐き出させてあげることが大切なのです。』
『「なにがあったの?」「どうしたの?」「どうしてそう思うの?」と、話を促しながら、とにかく聴くことです。
あなたのアドバイスや励ましは、その時点では不要です。
誰かに聴いてもらうことでしか、心のバケツにたまった泥水を吐き出す方法はないのです。』
まさに私が辛いのは心に泥水が溜まって溢れそうになっている状態なのだと思います。
心理カウンセラー・ラッキーさん
【聞き上手は好かれる!】悩み・愚痴の正しい聞き方
これはとても分かりやすいし楽しく読めます。男性必見かも…😆
ブロガー、カウンセラー、そしてコンサルタントとしての仕事もしている立花岳志さんによれば・・・
もし、相談を受けた時、やってはいけないことが「アドバイス」以外にもある。それは、「正論を説く」「指導する」「説教する」
『どんなにあなたが言っていることが正しかったとしても、相手の言葉を遮っていきなり正論をアドバイスしても本人には届かないし、話を遮られたら「この人は話を聴いてくれない」「私のことを受け入れてくれていない」と判断し、ガッカリし、心を閉ざしてしまう。』
『あなたにアドバイスを求めに来る人は、アドバイスや指導の前に、まずはあなたに理解してもらいたがっている。寄り添ってもらいたがっている。』
『安心感を与えてあげることが出来れば、相談しにきた人は安心するし、あなたに対して心を開くだろう。』
『心を開いてお互いが信頼関係を構築したあとで、相談者に提案した形でアドバイスや指導をして、その人が抱えている問題が解決したら最高だ。』
『「共感なき解決」では人は救われない。』
私は早期退職をしましたが小学校の教師をしていたことがあります。
教師は「正論」「指導」「説教」をするのが仕事のようなものです。少なくても、私はそう思って来ました。
忙しい中、いろいろなトラブルや解決しなければいけないことがあり、瞬時に「正論」を子どもたちに説き、「指導する」必要がありました。よく「説教」もしました。
子どもたちのトラブルを解決するとき、時間がないので、一通り話を聞いた後、喧嘩両成敗のようなことをしていたのではないかと反省します。
しっかり、話が聞けない中、「ごめんね。」「ごめんね。」とお互いに謝らせて解決することもありました。休み時間は10分、長くても25分しかありません。その終わりの方でトラブルがあることもあります。次の授業が気になり、しっかり子ども達の話を聞けなかったのです。
もしかしたら、今でもそういう癖が染み付いているかも知れません。(私のブログも正論、指導、説教じみたところがありますね😅 )
日本の1学級あたりの児童数は世界と比べても多い方です。やっと35人学級が進みつつありますが、教職員の増員と20人、25人学級を早く実現してほしいと願っています。
では、どうしたら・・・?
「そうなんだね」
「大変なんだね」
「疲れてるんだね」
「もう無理って感じるんだね」
とやはり寄り添うだけでいいのだということです。
今まで書いてきたことは精神疾患ではない一般的な悩みの相談に対しての対処法です。
精神疾患のある人に対してもほぼ同じことだそうです。違うところはその人の様子をよく見る。場合によっては医療機関に相談する(無理強いはしない)。自殺をしないかを見極める。
自分の周りの人が、うつかもしれない。
医師に聞く、「そんなときはどう接したらいいの?」
話は少しそれますが、双極性障害の自殺企図の割合は、一般集団と比較し、成人で20倍以上、青年で50倍以上だということです。
自殺は自らの意思で死を選ぶものではなく、双極性障害で自殺したくなるのは、病気の症状です。
幸い、私は自殺しようと思ったことはありませんが症状の出ている時の辛さは相当なものです。
私は相談を受けた時、悩みを吐露された時、アドバイスしないでじっくり話を聴こうと思いましたが、悩んでいる人に対して、アドバイスしないということは本当に難しいことです。どうしても励ましたくなったり、自分だったらこうするといいたくなったりしてしまいます。
でも、知らなかった時と比べると努力しようとしている分、少しは寄り添って聴けるようになっているかも知れません。入院中、患者さんの話を聴く時、相手の顔をしっかり見て、全身で聴くことを心がけました。何を言おうかと思いめぐらさなくていいのですから聴くことに集中できます。
これは関係性によっては難しいと思いますが、手、肩、背中など体のどこかに触れながら聴くというのもいいかも知れません。
昔、坂道を上る時、死んだ弟に背中を押してもらったことがあります。その時、助けてもらって有り難かったのと同時にとても心が温かくなって嬉しかったことを覚えています。
入院していた時、ある患者さんのパーカーのフードがひっくり返っていました。私が「このままでは幸せは逃げてしまいますよ。」フードをひっくり返して「はい、これで幸せがたっぷり入ります。」と背中をポンポンとしました。
あとで、その方は「背中を叩いていただいたことがこんなに嬉しいとは思わなかった。」と言っておられました。
今はコロナで難しいですが、出来る時はボディタッチもコミュニケーションの一つにしようと思います。
「精神疾患」シリーズを書いている途中で、うつ状態がひどくなり、入院まですることになるとは思いもしませんでした。
光トポグラフィーの検査は病院側からの指示だったのですが、検査をするといわれてから入院してせっかく良くなって来ていたのに、私は状態が悪くなってしまいました。
なぜなら、私はブログで私の双極性障害のことを書いて来たのに、検査の結果、とてもきれいな健常者のパターンだったら、今まで書いて来たことが崩れ落ちるような気がしたからです。
悩んでいたことを伝えていた看護師さんに結果を報告すると「おめでとう!」と言われました。私の悩みが解消したことに対してです。
私は自分の光トポグラフィーの波形を見て、この辛さはやはり「脳」から来ていたのだと改めて思いました。
事情があって、早く退院しました。症状が良くなって退院したわけではないのでまだ辛い症状が出ます。
友人、知人、近所の方に助けていただいてなんとか過ごしています。真心の温もりに触れると症状が軽くなります。本当に不思議です。
とりあえず、これで「精神疾患」シリーズは終えようと思います。
文章が長い上に難しい内容で読みにくかったことでしょう。
独りよがりの部分もあったかも知れません。
「精神疾患5人に1人」の時代です。
これらの記事が外から見えにくい「精神疾患」を知るきっかけになり、身近な人が「精神疾患」になられた時に何かのお役に立てば嬉しいです。
また、同じ病気の方がここは同じ、ここは違うと教えていただけるとありがたいです。
フォロワーさんはじめ、私のまわりの皆さま、この精神疾患のブログを長きにわたって読んでくださった皆さまに心から感謝いたします。
2022.2.26