小山 鉄郎著 共同通信社
昔、いつごろだったか定かではないけれど、NHKで象形文字から
漢字になっていく過程と、その意味をやっている5分ほどの番組があった。
そのときも楽しく見ていた。
で、気になったので図書館で本を借りました。
「ほぉ~」とか、「へぇ~」とか思うことが多かったのですが、
その中で私が反応したのは「婦人」の「婦」と言う漢字。
昔、誰だか、そういったことに敏感な方々が、
「婦人の婦には、帚と言う字が使われているので、差別だ!!」
などと言う話になり、結構街の中から、婦人と言う言葉が消えていった。
ゼロにはなっていないが、「女性」と言う言葉に変わって行った。
もちろん、これだけが理由ではなかっただろうけれど、行政関係の言葉からは
極端減っていったような気がする。
で、この「婦」と言う字は、白川先生いわく、
紀元100年ごろ許慎の書いた「説文解字」に
『服従する人、掃除する人』と言う説明があり、この解説がこの字を
使うことを良しとしない人たちの根拠のひとつになったらしい。
けれど、白川先生は、「帚」は、ごみ掃除の「帚」ではなく、
香をつけ、酒を降りかけ、家の祖先を祭る廟を祓い清める行為に
使うもので、その仕事はその家を代表する女性があたっていたものだという。
その仕事が主婦がするもので、女の人が帚をもっているものが、文字になったと言うことらしい。
こんな結論に至る過程はもうひとつ、どんな研究でそうなったのか私には、
もう一つだけど、「婦」って字もなかなかなんだな~と、思ったしだい。
昔、いつごろだったか定かではないけれど、NHKで象形文字から
漢字になっていく過程と、その意味をやっている5分ほどの番組があった。
そのときも楽しく見ていた。
で、気になったので図書館で本を借りました。
「ほぉ~」とか、「へぇ~」とか思うことが多かったのですが、
その中で私が反応したのは「婦人」の「婦」と言う漢字。
昔、誰だか、そういったことに敏感な方々が、
「婦人の婦には、帚と言う字が使われているので、差別だ!!」
などと言う話になり、結構街の中から、婦人と言う言葉が消えていった。
ゼロにはなっていないが、「女性」と言う言葉に変わって行った。
もちろん、これだけが理由ではなかっただろうけれど、行政関係の言葉からは
極端減っていったような気がする。
で、この「婦」と言う字は、白川先生いわく、
紀元100年ごろ許慎の書いた「説文解字」に
『服従する人、掃除する人』と言う説明があり、この解説がこの字を
使うことを良しとしない人たちの根拠のひとつになったらしい。
けれど、白川先生は、「帚」は、ごみ掃除の「帚」ではなく、
香をつけ、酒を降りかけ、家の祖先を祭る廟を祓い清める行為に
使うもので、その仕事はその家を代表する女性があたっていたものだという。
その仕事が主婦がするもので、女の人が帚をもっているものが、文字になったと言うことらしい。
こんな結論に至る過程はもうひとつ、どんな研究でそうなったのか私には、
もう一つだけど、「婦」って字もなかなかなんだな~と、思ったしだい。



















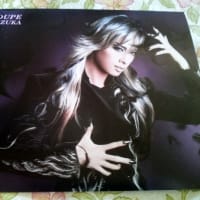
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます