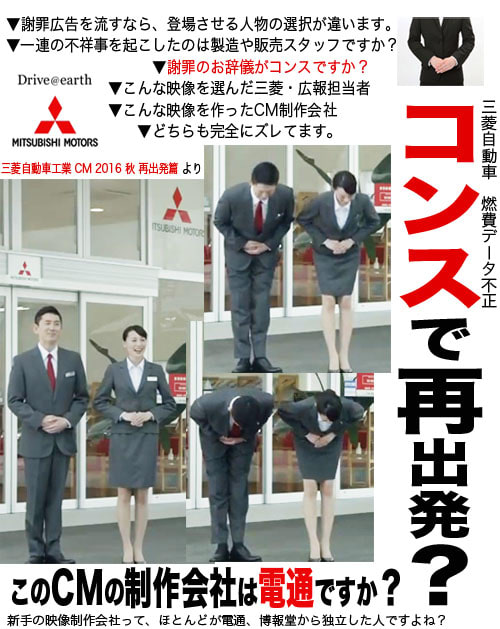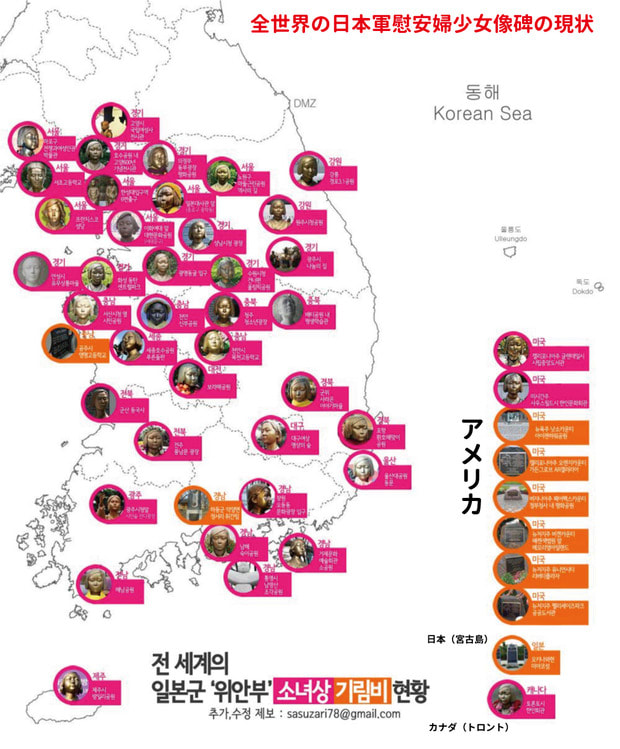何かの予兆? 首都圏の新築マンションが、パッタリ売れなくなった
7/17(水) 6:30配信
現代ビジネス
何かの予兆? 首都圏の新築マンションが、パッタリ売れなくなった
写真:現代ビジネス
土地価格は少なくとも東京五輪まで上がる――。そう信じて都心にマンションを買った人たちが、いま痛い目を見ている。開発されつくした首都圏に建つ、大量の売れ残りマンションはどうなるのか。
いまマンションを「買っていい街」「ダメな街」を実名公開
何かの予兆? 首都圏の新築マンションが、パッタリ売れなくなった
Photo by gettyimages
どう考えても作りすぎ
「うちも含めて、大手デベロッパーはみんな焦ってますよ。都心の新築マンションがまったく売れないんです。マンションは第1期の売り出しで、最低でも半分が即日で成約しなければ全室売り切れないと言われています。
アベノミクスがはじまったころは即日完売が当たり前だったのに、今は1期あたりの売り出し戸数を5分の1にして、『第1期即日完売』と無理やりアピールしています。売れている雰囲気を作るのに必死ですよ」(大手デベロッパー社員)
不動産価格は伸び続ける。居住用でも投資用でも、今買っておいて損はない。こんな商売文句で客を口説いていたデベロッパーが、揃って頭を抱えている。
6月17日に不動産経済研究所が発表した「首都圏のマンション市場動向」は、高止まりの続く不動産市場が完全な「曲がり角」にさしかかったことを示した。
東京23区における今年5月の新築マンション発売戸数は781戸で、前年同月と比べて36.3%も減少したのだ(契約率は65.8%で同3.9%減)。
ちなみに、首都圏で4月に発売された新築マンションは1421戸で、4月に1500戸を割り込んだのは27年ぶり。バブル崩壊直後の'92年並みの水準に逆戻りした。
アベノミクスが始まった'13年から、マンションは建てれば即日完売という状況が続いた。ところが今年5月、首都圏で即日完売となった新築マンションはわずか5棟22戸にとどまっている。
マンションが売れなくなった。原因は明確だ。近年の好景気ムードに押されて、あまりにもマンションを建てすぎてしまったのだ。
「特に顕著なのがタワーマンションです。超高層なら猫も杓子も売れていた時期がありましたが、今は竣工から5年が経過しても売れ残るケースが増えています。
たとえばゴールドクレストが建てた『勝どきビュータワー』は、2010年竣工にもかかわらず未入居物件の広告がいまだに出ています」(不動産ジャーナリストの山下和之氏)
'19年5月時点での首都圏マンション完成在庫は3539戸にのぼる。アベノミクスが始まった'13年は1000戸台だったことを考えると、「作りすぎ感」が否めない。
供給過剰になれば、新築・中古問わずマンション在庫がダブつくのは当然だ。価格の頭打ちを迎え、割高でマンションを手にしてしまった住民たちは強く後悔している。
中古も買い手がつかない
4年前に湾岸エリアで新築2LDKのタワーマンションを購入した30代男性はこう言う。
「2年間住んだあと、購入価格に300万円上乗せして売り出したのですが、半年経っても売れる気配がない。
そこから400万円下げ、原価割れで売り出したのですが、若干問い合わせが増える程度。さらに200万円値下げした今になってようやく買い手がつくかな、という状況です」
市場が飽和するほどマンションを建て続けた理由は、少なくとも東京五輪が行われる2020年まで、首都圏の土地価格がずっと上がり続けると信じられてきたからだ。だが実際のところ不動産市場では、ジワジワと悲観的な予測が増えはじめている。
このことを裏付けるのが、6月10日に全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が発表した「不動産市況DI(指数)」だ。
この指数は、3ヵ月前と現在の不動産価格の推移や取引実績を比較調査し、「現在」そしてさらに「3ヵ月後」の土地価格が上昇傾向、または下降傾向にあるのかを数値化したものである。
今年4月に行われた調査では、全国で5.4ポイントと前回('19年1月)比0.8ポイントの上昇がみられたが、関東に限ればマイナス3.1ポイントと、前回比2.6ポイントの下落を示したのだ。ちなみに関東は2調査連続のマイナスである。
それだけではない。「3ヵ月後」の見通しは全国ベースでマイナス6.2ポイント、関東ではマイナス12.8ポイントと、大幅なマイナス予測が出ているのだ。
投資家は「終わり」を見越している
この数字をどう読み解けばいいのか。前出・山下氏は言う。
「全宅連の調査対象は50坪程度の個人間売買物件で、商業地や大規模な宅地は含みません。ただ、この指数がマイナスであるということは、すでに地価が頭打ちとなり、下落に向かうと感じている人が増えてきていると言えます」
買った物件に住んで自分で使う、いわゆる「実需」ベースの購買層だけでなく、マンションバブルを牽引してきた投資家層も、不動産バブルの終わりを予期して動き出している。
住宅ジャーナリストの榊淳司氏が言う。
「一時期人気を集めた晴海などの湾岸エリアや武蔵小杉で異変が起きています。地価上昇を下支えしていた中国人購買層がマンションを売りに回しはじめたのです。
市況に敏感な彼らが引き揚げたということは、想定以上に値崩れのスピードが早い物件が出てくるかもしれません」
オフィスビル仲介大手の三鬼商事の調査によると、今年5月の都心5区のオフィス空室率は1.64%と、'02年1月以来最低を更新し続けている。
またインバウンド需要を見込み、都内では年間1万室近いホテルが新しく建てられ、山手線の狭いエリアで陣取り合戦が繰り広げられている。いわゆる商業用地の土地価格が伸びるウラで、住宅地の値段は下がり始めているのだ。
日本最後のバブルが終わる
飽和から崩壊へと向かい始める不動産市場だが、「とはいえ五輪までは大丈夫」と楽観視する向きもある。だが、「それまで持たない」と構えていたほうがいい。
「五輪前により一段、価格が下がる契機があるとすれば、やはり10月の消費増税でしょう。本当は新築が欲しいけれど、さすがに予算オーバーだと考えている購入層は、同価格帯の新築・中古物件を回遊魚のように巡って検討を重ねています。
それが10月、個人所有の中古物件には消費税がかからない事実を目の当たりにして、新築の夢を捨て、みんながお得な中古を選ぶという市況が十分に想定できます。新築物件の売れ行きがさらに悪くなれば、不動産市場全体の値下がり傾向も強まるでしょう」(マンショントレンド評論家の日下部理絵氏)
かねてから囁かれていた不動産バブルの崩壊が訪れたとき、どのようなエリアが大きく値を崩すことになるのか。「マンションレビュー」を運営する川島直也氏はこう語る。
「新築物件でいえば、これまで人気だった世田谷区や大田区がすでに苦戦を強いられています。
両区は『竣工残』、つまり完成後も売れ残っている物件の在庫が溜まってきています。また、ほかの人気エリアでも、駅遠物件が避けられる傾向は引き続き変わらないでしょう」
前出・日下部氏は、都心へのアクセスがよい人気エリアにも思わぬリスクがあると考える。
「近年『穴場』と言われ、急激な地価上昇が続いているエリアが、逆に大きな痛手を負う可能性が高いです。
都心へのアクセスが良好で割安な北千住、浦和、松戸などでは今後も大規模マンションの建築が予定されていますが、本来の土地評価以上に値上がりしている感が否めず、危険な買い物になるかもしれません」
これまで「お買い得」とされていたエリアのマンションも、首都圏の土地価格が下がれば一気に「不良債権」へと変化するのだから恐ろしい。
そのような状況下でも、価格が「下がらない」地域はあるのだろうか。
前出・榊氏はこう語る。
「マイナス材料が多いなか、期待値が高いのが、五反田~泉岳寺周辺です。高輪ゲートウェイ駅新設に伴う再開発が進み、周囲には白金や御殿山など高級住宅街もある地域。『湾岸付近最後のフロンティア』と言えるでしょう」
首都圏はもはや開発の余地がない。数年にわたって続いた地価上昇は日本史上最後のバブルになるかもしれない。そして最後のバブルが今、崩壊しはじめたのだ。
「週刊現代」2019年7月6日号より

go_***** | 15分前
オリンピック終了後半年以内に日本は大不況に突入するかも。国民保険料、介護保険料、所得税、県民税・市民税、消費税、ガソリン税。身の回りは税金でがんじがらめ。どれだけ働いても豊かになるどころか貧しくなる実感の方が大きい。
0 0
返信0
x... | 15分前
過剰供給なのに高値で吹っかけてたら、そりゃ売れないでしょうよ。
今すぐ買わないと住むとこないって人以外、オリンピック後まで値崩れを待つでしょ。
0 0
返信0
mda***** | 20分前
日本人の可処分所得は横ばいなのに、不動産価格だけ高騰しても、取れるパイは最初から限られていたはず。バブルは有限だからバブルなのですよ。底を打った、ということでしょう。一年早まりましたね。
2 0
返信0
一般市民 | 21分前
タイトルに笑った!
オリンピックが終われば、次は南海トラフ対策だろww
0 0
返信0
tos***** | 23分前
不動産屋が儲けすぎに気づいたから。
0 0
返信0
inu***** | 39分前
東京都の23区外です。市です。駅徒歩2-3分の好立地だけど80平米弱の新築マンション8000万します。強気すぎる。8000万出すならもっと都心に住みたい。
2 0
返信0
** | 49分前
五反田から泉岳寺周辺の期待値が高いとの記事ですが、この地域は羽田空港の新航路が運行を開始すると地上300メートルの低空で飛行することが予定されている地域です。
午後から夜に掛けて2分に1機の間隔で飛行します。高さ150メートルのタワーマンションの最上階からの距離は僅か150メートルしかありません。
子供が家での学習が必要な時間に飛行が予定されています。
騒音もありますが、車輪を出すタイミングの地域なので、上空で水が凍結して氷になったものが落下する危険もあります。
1 0
返信0
tom***** | 51分前
より高い値段で買ってくれるカモを狩り尽くしたんだろ(笑)
0 0
返信0
june | 54分前
中古は半値スタートやな
0 0
返信0
tku***** | 56分前
湾岸のタワマンなんて大規模修繕で確実にもめると思う。
都下の小規模マンションでさえ積み立て不足で問題になってるのに。。

気をつけろ! 日本株市場「大崩壊」の不気味すぎる予兆が出てきた
7/16(火) 8:00配信
現代ビジネス
気をつけろ! 日本株市場「大崩壊」の不気味すぎる予兆が出てきた
写真:現代ビジネス
株価の大きなトレンドを「見る方法」
米国の利下げの観測に振り回されながら、株式市場は上にも下にも動きにくい日々が続いている。強い雇用統計と利下げ観測が目まぐるしく入れ替わる格好だ。
【衝撃の結果…!】リーマン危機から10年、日本企業「株価下落率」ランキング500
しかし、これはあくまで目先のイベント需給に対する反応であり、無論、米国の金融政策が世界経済の鍵を握っていることは疑いない。
一方、仮に本質的に景気がピークアウトして後退局面へと突入してしまえば、金融政策はその悪影響を軽減させる程度の効果しかないのもまた事実。米国の金融政策といえど、大枠としての経済の崩壊の方向性を逆転させるほどの力は持たないともいえる。
そうした中にあって、いま株価の大きなトレンド把握に利用できる可能性が高いものがある。それは、証券会社のアナリストの業績予想だ。
証券会社のアナリストの分析の精度については賛否があるが、それらを集計した数値の傾向は、金融業界における業績予測のトレンドの「集合知」としての利用価値があると考えられる。
このトレンドを見るための代表的な指数が、「リビジョン・インデックス」と呼ばれるものだ。
気をつけろ! 日本株市場「大崩壊」の不気味すぎる予兆が出てきた
写真:現代ビジネス
ピタリと一致する
これは、複数名のアナリストが分析(カバー)対象とする銘柄について、業績修正(リビジョン)のトレンドを見るものだ。計算方法はいくつかのパターンが存在するが、
----------
(上方修正したアナリスト数―下方修正したアナリスト数)÷カバーアナリスト数
----------
とするのが一般的だ。つまり、カバーアナリストの上方修正と下方修正のどちらが多いのかを割合として算出する、という設計である。
それでは、まず実際に値の推移を見てみたい。期間は過去15年間(2004年6月~2019年6月)とした。
----------
図:日本株のリビジョン・インデックス
----------
御覧の通り、前回の好況であった小泉郵政相場から現在の米中貿易摩擦による混乱に至るまで、基本的に各局面を適切に捉えていることがわかる。
重要なのは、このインデックスは特に平滑化処理を施していないにもかかわらず、ひとつの局面が一定期間の方向性を持ち続けることだ。
単にアナリストの見方が目先の見通しの変化に一喜一憂するならば、値は月替わりで乱高下を見せてもおかしくない。実際に個別銘柄でリビジョンを追うと毎月バラついた動きになるが、全体を集計するとこのように景気の局面を適切に捉えることが可能となる。
しかし、これだけでは、単に過去の景気の局面を分類できているだけにすぎない。また、各時期の上昇ラリーや低迷期で水準感も異なっており、テクニカル指標としての機能も期待できそうにない。
しかし、この指標をある区分で分けると、このリビジョンが一定の規則性を有し、今後の見通しの変化や転換点を見出すのに有用となる可能性を秘めることが分かる。
それが、シクリカル業種、ディフェンシブ業種の観点だ。
ピークアウトの入り口
シクリカル業種は、一般に景気敏感業種と呼ばれ、その名の通り景気の回復・低迷の変化に業績が敏感に反応しやすい業種を指す。
製造業や資源などがこれに該当し、為替や資源価格、海外需要などの世界経済の見通しの変化に応じてアナリストは業績予想を上方、下方に目まぐるしく修正する。
しかし、このシクリカル業全体を集計すると、下図のように一定期間の美しい循環を描くことが分かる。
----------
図:シクリカル業種のリビジョン・インデックス
----------
ピークの高さはサイクルによって若干異なるうえ、株式市場の騰落に対してやや遅行する動き(これはアナリストの推奨行動の特徴でもある)を見せるが、重要な点は3年程度のほぼ等間隔での循環を描くことと、積み上がった分の上方修正分をプラスマイナスゼロまで吐き出さないかぎり、上昇トレンドには転じないことだ。
各サイクルともに例外なくゼロ線を下回った段階で反転を見せていることが分かる。そして、現状は米中貿易摩擦によってピークから典型的な下落のトレンドの最中にあり、3~4割程度の進行具合といったところか。
そして、一方のディフェンシブ業種は、主に生活必需品や消費、公益などが該当し、短期的な景気変動よりも中長期的な経済のトレンドを追随する業種である。景気が構造的に変化しないかぎり、アナリストの業績修正も一方向へのトレンドを持ち、緩やかな動きを見せる。
また、シクリカルと異なり、ゼロ線を挟んで対称的な大きな波を描くのも特徴だ。低迷期を参考にすれば、ひとつのサイクルは10年弱程度にもなる。
----------
図:ディフェンシブ業種のリビジョン・インデックス
----------
こちらは、前回の好況からの恐慌までの動きに倣えば、ちょうどピークで頭打ちとなり、横ばい状態から下落の動きが見られ始めている。2015年のチャイナ・ショックの際にも一瞬だけ軟調な時期は見られたが、水準感としても前回ラリーと比較すれば半分程度であり、下落に転じず地味に上昇は継続していた。
言い換えれば、今回の頭打ちは長期循環における構造的なピークアウトの入り口と見るべきかもしれない。
強いショック相場に身構えろ
そして、このシクリカル、ディフェンシブの両者を並列で比較することで、ある関係性が浮かび上がる。
前回の金融危機の入り口であった2007年後半と、2019年7月現在は、2つのインデックスの推移の観点から共通点として、シクリカル、ディフェンシブ双方のリビジョンが同時にピークアウトの動きを見せていることだ。
----------
図:シクリカル、ディフェンシブ業種のリビジョン・インデックス対比
----------
この長短循環の観点からは、前回のサブプライム危機以降の流れは、この両者が同時にピークを迎え、そして同時に下落へと反転したことで深刻な状況へと陥ったと見られる。
定性的に捉えれば、「シクリカルもディフェンシブも崩壊し、市場の支えがない状態」と考えられ、これが金融危機につながるというのは納得感がある。
また、下落フェーズだけではなく、2013年や2017年などは短期・長期が双方ともに上昇したが、その期間は株式市場が強烈な上昇を見せたことは記憶に新しい。上でも下でも、長短循環が同方向を向く場合に株式市場はそれに沿った強い反応を見せるようだ。
そして足元は、ディフェンシブは完全にピークアウトしてはいないものの、シクリカルを追うように頭打ちからの下落の動きが見え始めた。今後、仮にディフェンシブ業種の下方修正が本格化すれば、日本株市場は構造的な崩壊を見せる恐れがある。
考えてみれば、ディフェンシブの支えになる消費動向については、今年10月に消費増税が実施されることが確定している。この影響度合いは未知数だが、少なくとも内需および消費を中心としたディフェンシブの見通しを押し下げることだけは確かだ。正確なタイミングを見計らうのは難しいが、備えあれば憂いなし、強いショック相場に対して身構えておくのが吉だろう。
最後に、参考までに長短循環がともに下落している局面で底堅く推移する銘柄の一覧を掲載しておく。
気をつけろ! 日本株市場「大崩壊」の不気味すぎる予兆が出てきた
写真:現代ビジネス
下落局面で底堅く推移する銘柄一覧
大川 智宏