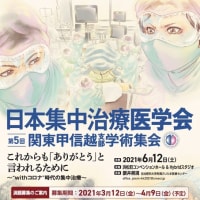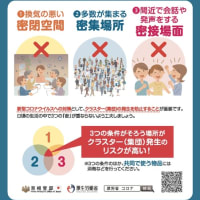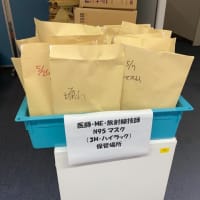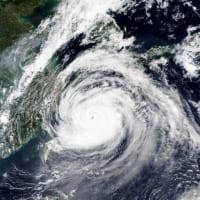前回は、日本と欧米の急性期医療がかくも違う理由として、両応援派の理論が二項対立したまま、それぞれの応援派が思考停止に陥ったままである現状とその背景を述べた。その背景には、三つ子の魂百まで、刷り込まれたことは変更しにくいこと、患者が重症で、その治療の有効性と安全性が担保されていなくてとも、「ポテンシャル」という基準で治療を選択しやすく、その背景にそのような治療は臨床医のココロの鎮静作用があること、各種のコネクションがあることを述べた。
両派は二項対立という枠組みを脱却することができるのであろうか。
まずは欧米派の本場に飛び込むこと、海外留学について考えてみたい。研究留学と臨床留学の2種類があるのは異論のないところであるが、両留学がその後の医者人生に及ぼしうる影響の違いは大きい。
卒業してすぐのレジデント時代に染まった“自分色”を変更する(前回と同じ用語を使わせてもらえば“転向する”)のは、とてつもなく大きな外力を必要とする。研修医から永久就職先であるどこかの病院に至るまでの医師引越し人生の間、異動のたびに、転向とは言えない程度の「修正」を繰り返しながら“自分色”を変色、熟成させていく。みな、各病院を、各科をローテしてジャブを浴びながら、すなわち軽く否定されながら、なんとか折り合いを付けていく。しかし、ジャブはジャブであって、その医師に決定的ダメージを与えるまでには至らない。二項対立の片側から片側へと移るような転向には至らない。
しかし、ひとたび欧米の臨床現場で仕事をすると、強烈なフックやボディやアッパーを毎日のように浴びせられる。同じ西洋医学の範疇、同じ人間のやることなので、診療行動上のルーチーンに大きな違いはないが、そのバックグラウンドにある考え方や求められる発言に大きな違いがあるからである。朝から晩まで次から次へと、日本と異なる発想、考え方、それにもとづく行動を提示され、自分の一挙手一投足に説明責任が求められる(しかも、それを外国語で)。見た目そんなに変わらないことをやりながら、実は何もかもが違う。
そんな全否定の毎日の中、“個”として生き延びなければならない。職業人としての責務を果たさなければならないと言えばかっこ良いが、実は、単なる生物として生き延びなければならないだけである。そうしていくうちに、いつの間にか洗脳され、いつの間にか転向している。つまり日本派から欧米派に手っ取り早く転向するためには、根底から揺さぶられるような衝撃、および生物としてのサバイビング能力が自然に引き出されるような外力、体験が必要なのだと思う(注1)。
一方、研究留学はそこまでの強い外力を与えない。欧米のナマの医療文化に自分のアイデンティティーを否定されることがない。自分の今まで持って来た日本的臨床文化はポケットにしまっておける。その間、ただひたすら研究することによって研究者魂が身に付く。しかし、この研究者魂は、諸刃の剣とも言えるよい面、悪い面を持っている。
研究者魂のよい面は、研究のプロセスを通して、自分の研究テーマに関して、おそらく世界で一番“好き”と宣言できる、一番とは言えなくとも十指に入る確信を持てることができることであろうか。研究者としてある疑問が生じると、それを解決し最終的に公表するために、自分の人生を投げうってありとあらゆることを考え、実行するようになる。自分の望む結果が出ればそのときはもちろんであるが、それを求める過程においてさえ、エクスタシーを得ることができる(注2)。この精神、執拗さ、探求心は研究者としてきわめて重要な資質である。
しかし、海外派遣研究者を辞め帰国した後に、研究者魂をそのまま、臨床の不確実な世界に持ち込もうとすることは危険である。均一な動物を使って完全にコントロールされた介入を行って得られた結果は人間には通用しないことは、もちろん研究者自身も知っている。確かにアタマはそう意識している。しかし、ココロとカラダは否定されることを避ける。エクスタシーは捨てたくない(注3)。
真の科学者は、自分の信じる見解が質の高い証拠によって覆されてしまったら、その見解をアジャストするか、捨てなければならない(注4)。客観的証拠を重視する正しい科学者の資質である。しかし、上記の理由によって完全に否定される危険のあるシロかクロかの勝負を避け、「ポテンシャルのまま」であることを無意識的に望む心理が働く(もちろん勝負を避ける理由は他にもたくさん想像できるが)。あるいは惚れたテーマが生き残れる新たなニッチを探す。その結果、どんどん深みにはまり細部を求めようとしてしまう。新しく惚れた研究テーマが出現するまで、知らず知らすのうちに、このような言動をとるはずである。これは研究者魂の悪いサイドと言ってもよいかもしれない。
このような研究者魂のよい面、悪い面は、留学しなくても日本にいながら身につけることが可能である。全く同様に、基礎実験や臨床試験の初期段階から深く関わる治療法や、たまたまある患者に適応して驚くべき効果を発見したような治療法に惚れてしまうと、同じ轍を踏む危険性がある(注5)。
このように、研究留学は、否応なく自己否定されいつのまにか転向してしまう臨床留学と大きく違う。この筆者の直感は当たらずとも遠からずと思う。その理由は、もし、日本のアカデミック急性期医療を担う医師の大半が上記の臨床留学の如き過程を経て“転向”していれば、今頃日本の急性期医療は多少違った道を歩んできたのではないかと思うからである。
つづく。
以下、注釈
注1:こう述べると臨床留学はいかにも悲惨な精神修行のように感じるかもしれないが、体験者に悲壮感はまったくない。おそらく、毎日やるべきことが指定されており、いかにそれをやり過ごすかだけを考え、何も余計なことを考えないで済むこと、つまりはルーチーンをこなすことは、結構楽しくてラクなことだからである。軍隊で教練を受ける一兵卒(コトバが古い)、看守に見守られながら毎日の作業を続ける囚人と言ってもよいか。こう書くとまた悲惨な感じがするが、何となくわかっていただけるでしょうか。だからどんどん海外で臨床を経験してくださいね(説得力ない?)。
注2:筆者もレジデント期間中に6ヶ月のリサーチ期間をもらいリサーチ生活をかじったことがある。リサーチはとにかく楽しかったが、いばらの道であり、いろいろな意味で臨床より逃げ道がなかった。そういう険しい道なので、得られるエクスタシーもでかい。
注3:筆者も前述の6ヶ月間およびその後のフェローの期間を使ってバゾプレッシンの動物実験を行い、臨床的にも使いまくっていたので、なかなか研究者魂の悪いサイドを捨てられなかった。これを捨てるためにはまた別な衝撃的体験が必要であった。
注4:2001年にIntensive insulin therapyで世界の注目を一身に集めたベルギーのVan den Bergheは、その後この“惚れたテーマ”を否定され続け、現実世界の中にそのニッチを少しでも残したいと望んで開始した2011年EPANIC trialによって自らその“惚れたテーマ”を葬り去ってしまった。しかし彼女はすでにEPANIC trialによって得られた結果の裏付けを取るべく基礎研究を行い、自分のもともとの見解の否定につながるようなデータも提出しているという。ある先生は彼女の変わり身の早さにびっくりしたと言うが、私は彼女こそが真の研究者であると思う。
注5:研究留学でも、臨床現場で行うものから完全な基礎実験までもちろんいろいろなタイプがあるし、異国生活という自己全否定の体験は病院外でも可能といえば可能なので、チャンスがあれば是非。前述のように研究は研究の臨床と違った“いばらの道”が待っている。