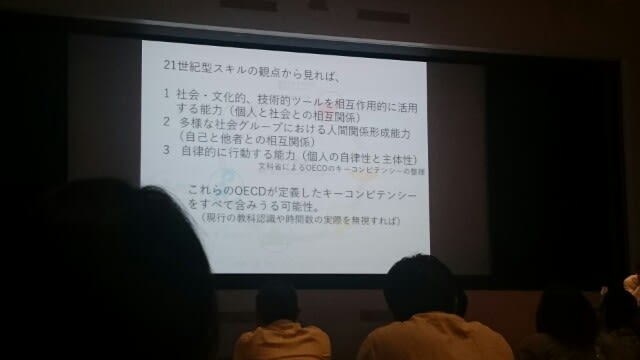夏休みの自由課題。
今年もうちの娘は図画がいいんだそうな。

父親に似て絵が得意…というわけでは全然ない子なのですが、きっと色々新しいことを教えてもらいながら二人でじっくり仕上げる工程が楽しいのだろう。
とっても意欲的に、何時間も描き続けてようやく完成。
作品全体像はあえて公開しませんが、今回はスパッタリングがお気に入りの様子でした。
スパッタリングは水分調節が命だと思うのですが、娘にはその調節はまだちょっと早いかなと…。よってそこは父親が調合して、娘はシャカシャカするのみだったので、かなり上出来…。

仕上げでほっぺたにチーク入れたいんだそうな。
そこでパステルを教えることに。
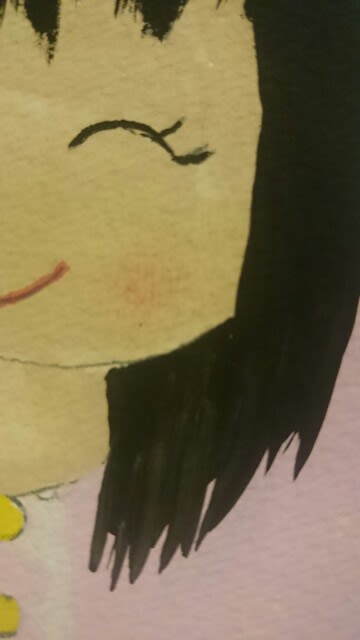
娘は大満足の仕上がりになったようです。
さてと…。
小学生の我が子にどこまで自力で挑戦させ、どこまでを助けてあげるか試行錯誤の取り組みとなりました。
今年はアイディアスケッチから取り組ませることに挑戦。
「どんなことを描きたいのか?」
「どんな思いを表したいのか?」
「どんな表現方法を使いたいのか?」
…考えさせたのですが、なかなか小学生に教えるのは難しかったです。
色々と描いているうちに、結局はパパがアイディアスケッチとは?の意味で参考に描いていた図案が気に入り、それを描きたいとなってしまうのでした。
この際だからと水彩絵の具の使い方も色々と伝授。
ぼかしたり、にじませたり、ムラをあえて生かすようなタッチで描かせてみたり。
水を上手に生かすことは身に付いた気がします。
今後の作品制作に生きるといいな。
とにかく、親が描いちゃった絵にならないいうに、学びながら達成感を味わわせることができるように、制作過程での経験が今後に繋がるように、と意識して頑張った1日でした。
さて、2学期制の本校。もう既に夏休みが明けました。
昨年度考えたことをもとに年間計画を修正し、夏休みの宿題を軽減しました。
昨年度まで「例年通り今年も…」感から無理に取り組ませていた文化祭のポスター制作ですが、今年度はしっかりと授業時間に指導ができる2学年のみの題材としました。
3年生にも描きたい!って子がいるような雰囲気だったので、3年生には事前アンケートをとることに。
アンケートで「制作したい」と答えた数名のみを、授業時間以外の放課後や夏休み中に指導して…という形で参戦してもらいました。
作品数は減ったので、文化祭の作品展示会場は少し寂しくなるかもしれません。それに不満を感じる来場者もいるかもしれません。
しかし昨年度感じた教科経営へのしわ寄せの課題はこれでクリア。これで良かったと思います。
学校事情、周囲からの要望にも耳を傾けはしますが、少ない授業時数を有効に使い、美術の授業で学んでほしいこと、経験してほしいことを優先せねばと思います。
来週末はいよいよ文化祭。
まずは週明け早々に急ぎ代表作品を拡大印刷して、それらを生徒たちに託して近所に配りに出てもらわねば。
今年もうちの娘は図画がいいんだそうな。

父親に似て絵が得意…というわけでは全然ない子なのですが、きっと色々新しいことを教えてもらいながら二人でじっくり仕上げる工程が楽しいのだろう。
とっても意欲的に、何時間も描き続けてようやく完成。
作品全体像はあえて公開しませんが、今回はスパッタリングがお気に入りの様子でした。
スパッタリングは水分調節が命だと思うのですが、娘にはその調節はまだちょっと早いかなと…。よってそこは父親が調合して、娘はシャカシャカするのみだったので、かなり上出来…。

仕上げでほっぺたにチーク入れたいんだそうな。
そこでパステルを教えることに。
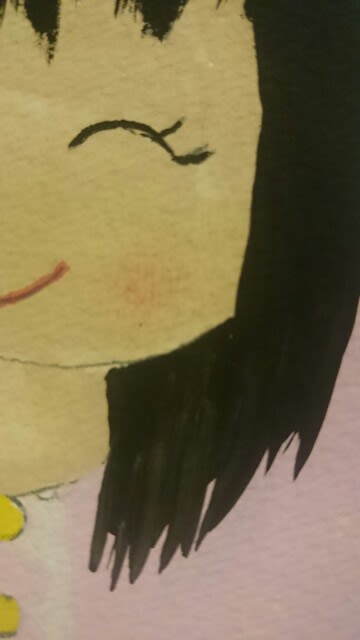
娘は大満足の仕上がりになったようです。
さてと…。
小学生の我が子にどこまで自力で挑戦させ、どこまでを助けてあげるか試行錯誤の取り組みとなりました。
今年はアイディアスケッチから取り組ませることに挑戦。
「どんなことを描きたいのか?」
「どんな思いを表したいのか?」
「どんな表現方法を使いたいのか?」
…考えさせたのですが、なかなか小学生に教えるのは難しかったです。
色々と描いているうちに、結局はパパがアイディアスケッチとは?の意味で参考に描いていた図案が気に入り、それを描きたいとなってしまうのでした。
この際だからと水彩絵の具の使い方も色々と伝授。
ぼかしたり、にじませたり、ムラをあえて生かすようなタッチで描かせてみたり。
水を上手に生かすことは身に付いた気がします。
今後の作品制作に生きるといいな。
とにかく、親が描いちゃった絵にならないいうに、学びながら達成感を味わわせることができるように、制作過程での経験が今後に繋がるように、と意識して頑張った1日でした。
さて、2学期制の本校。もう既に夏休みが明けました。
昨年度考えたことをもとに年間計画を修正し、夏休みの宿題を軽減しました。
昨年度まで「例年通り今年も…」感から無理に取り組ませていた文化祭のポスター制作ですが、今年度はしっかりと授業時間に指導ができる2学年のみの題材としました。
3年生にも描きたい!って子がいるような雰囲気だったので、3年生には事前アンケートをとることに。
アンケートで「制作したい」と答えた数名のみを、授業時間以外の放課後や夏休み中に指導して…という形で参戦してもらいました。
作品数は減ったので、文化祭の作品展示会場は少し寂しくなるかもしれません。それに不満を感じる来場者もいるかもしれません。
しかし昨年度感じた教科経営へのしわ寄せの課題はこれでクリア。これで良かったと思います。
学校事情、周囲からの要望にも耳を傾けはしますが、少ない授業時数を有効に使い、美術の授業で学んでほしいこと、経験してほしいことを優先せねばと思います。
来週末はいよいよ文化祭。
まずは週明け早々に急ぎ代表作品を拡大印刷して、それらを生徒たちに託して近所に配りに出てもらわねば。