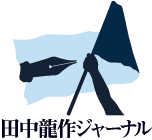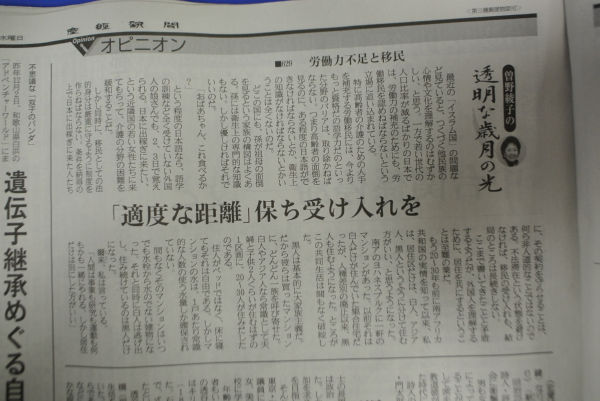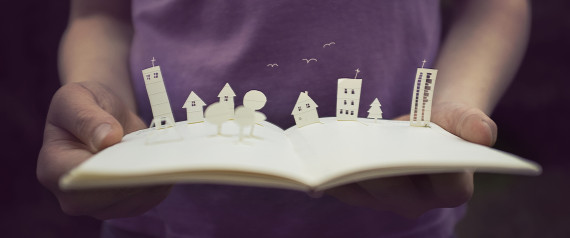リメイク
”積極的平和” とは。
「積極的平和」は第二次世界大戦中の一九四二年、米国の社会学者クインシー・ライト氏が執筆した「戦争学」の中で、「消極的平和」と併せて使ったのが始まりとされる。その後、米国に留学した
ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥング氏が
「消極的平和」を戦争のない状態、
「積極的平和」を戦争だけでなく
貧困や搾取、差別などの構造的な暴力がなくなった状態、
と定義して定着した。
ヨハン・ガルトゥング氏略歴
JOHAN・GALTUNG 30年ノルウェーの首都オスロ生まれ。オスロ大で数学と社会学の博士号。59年オスロ国際平和研究所を創設し平和研究を主導した。87年「もう一つのノーベル賞」といわれる「ライト・ライブリフッド賞」受賞。93年に夫婦で国際非政府組織(NGO)「トランセンド」を創設した。著書に「構造的暴力と平和」「平和への新思考」など。
平和研究
平和学ともいわれ、紛争の原因や背景を基に、その回避の方法や平和の維持などを研究する学問。米国で第2次大戦後、始まったとされるが、ガルトゥング氏が1959年、オスロ国際平和研究所を創設し本格的に学問化した。日本でも広島、長崎などの大学、機関で学問分野として確立。ガルトゥング氏は「平和=戦争のない状態」という考えから転換し、武力による直接的な暴力に加え、貧困や抑圧、差別が社会に根差している場合の「構造的暴力」を提起。構造的暴力がない「積極的平和」を平和の概念として取り入れた。
構造的暴力
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/…/rosaldo/09violencia_estruct…
structural violence, violencia estructural
解説:池田光穂
暴力行使において行為者が特定しにくいものを構造的暴力(structural violence)とよぶ。行為者が特定しにくい暴力行使の特徴は、力の行使と力の観念の間に複雑な関係があり、行使と観念の間に明確な区別がつきにくい ために、ヨハン・ガルトゥング(Johan Galtung, 1969)は人為的暴力や直接的暴力[→彼は後に行為者暴力とまとめる]との対概念として、この概念を提唱している[ガルトゥング 2003:117]。
通常暴力の行為者は、特定の個人や政治集団、警察や軍隊などの国家暴力[執行]装置、あるいは国家そのものや社会制度(司法や裁判)などがある が、それらの主体が特的できうる暴力の行使は、それぞれ、政治暴力、国家暴力、軍事的暴力、司法的暴力(一般の法学者や政治学者はこの概念を容認しないか も知れないが)など、暴力主体や暴力の目的という形容詞を暴力に冠することで、暴力の行為者や意図を指し示すことができる。
それに対して構造的暴力は、どの特定の行為者のどのような意図が、その暴力行使であるか、特定しにくいのが特徴である。つまり、構造的暴力は、 被害者に「非直接的に」はたらくというのだ。ただし、このようなガルトゥングの二分法は曖昧でほとんど「権力」の概念と区別がつかない点で問題がある。
構造的暴力は、国家や権力集団が、合法性を装い持続的におこなわれる、人権・道徳・排外的な暴力の行使である。それゆえ、構造的暴力は、国家、 民族、人種、権利、正義、性別、宗教的ドグマの名の下に行使され、平和的や人道的であると正当化されることがある。
ガルトゥングは構造的暴力の形態を次の3つに分類する[ガルトゥング 2003:118]
1)抑圧――政治的なるもの
2)搾取――経済的なるもの
3)疎外――文化的なるもの
平和維持のための軍隊の派兵や、途上国における当事者たちの同意なしの不妊手術や投薬は、典型的な構造的暴力である[と私は考える]が、このよ うに構造的暴力を捉えると、構造的暴力がはたして通常の暴力的行使と同じものであるがどうかという点については、いまだ議論の余地があり、また、誰がそれ を構造的暴力と認定するかという点で、極めて論争的な概念である。
ガルトゥングの構造的暴力の概念が、権力概念と区別をつかないとか、あらゆるタイプの間接的暴力に適用可能であるということは、彼の理論が、い かに理性 的合理的モデルに依存しており、そのモデルの限界についてガルトゥングは自覚が足らず、これらの概念を鍛えようとも、その背景には奇妙な神学的弁論(=暴 力を理性により理解し、統御する)が見え隠れしている。
この点で考えると、ガルトゥングをより深く理解するためには、その対極的な参照点として、大衆を動員するための神話的暴力あるいは象徴的暴力の 必要性を説いたジョルジュ・ソレルの暴力論について[も]考えることが重要になるかも知れない[→リ ンク]。
「現代の国家観における暴力装置概念をグレマス[一九九二]の「意味の四角形」に配列してみたのが図2である。暴力(S1)の相反項は もちろん非暴力(S2)である。国家は社会契約にもとづき個々の人民が武装し暴力(S1)を行使する権利を国家権力を介して回収する。権力(~S2)は暴 力装置を維持するために不可欠なものにほかならないが、それは国家が人民の合意にもとづき行使されるべきものである。暴力装置が不要になる状態(=警察や 軍隊のない社会)とは、権力が極小化された状況すなわち平和(~S1)に他ならない。このような理想的状況においては、国内の秩序維持に暴力装置(=警 察)を行使することは不要になり、ただ国民を守るためのもの(=軍隊)だけが必要となる」(出典:池田光穂「政治的暴力と人類学を考える――グアテマラの 現在――」『社会人類学年報』,第28巻,Pp.27-54,2002年)
文献
Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3. (1969), pp. 167-191
藤田明史編『ガルトゥング平和学入門』京都:法律文化社、2003年
ガルトゥング「構造的暴力について:西山論文についてのコメント」藤田明史編『ガルトゥング平和学入門』Pp.117-118、京 都:法律 文化社、2003年
池田光穂「テロリズム」(医療人類学辞典)
____「渡日外国人労働者に対する構造的暴力:保健医療への人類学 的アプ ローチ」
____「政治的暴力の概念」政治的暴力と人類学を考える(グアテマ ラの現 在)
____「政治的暴力とくに国家テロについての人類学的分析」政治的 暴力と 人類学を考える(グアテマラの現在)
池田光穂「アーレント暴力論:まとめ」
「新しい芽」平和研究の父ヨハン・ガルトゥング氏
http://www.47news.jp/47topics/bunmei/5.html
「大転換」もたらす震災 軍事・平和の境ない原子力 アジア共同体つくる契機に
差別や貧困など構造的暴力が平和を阻害するとの理論を打ち立て、「平和研究」の父とされる政治学者ヨハン・ガルトゥング氏(80)は、東日本大震災と福島原発事故は日本にとって二つの意味で「大転換」をもたらすと予想した。一つは脱原発。もう一つは、東アジアの中国、朝鮮半島との和解だ。大震災は大きな悲劇だが、ガルトゥング氏は、もう一度「日本のあるべき姿」を見つめ直す機会にしてほしいとの願いを語った。
積極的平和 実現へ日本の貢献は? (東京新聞)
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10087.html
(東京新聞「こちら特報部」10月19日)
日本は「積極的平和主義」を掲げるべきだと安倍晋三首相は言う。「積極的平和」は、半世紀以上前に米国で作られた言葉だ。平和学の専門家によると、「戦争だけでなく、貧困や搾取、差別など構造的な暴力がなくなった状態」を意味する。そんな世界の実現に貢献するのなら、日本人も胸を張れるのだが-。 (小倉貞俊、榊原崇仁)
「安倍さんは『積極的平和』を、もともとの言葉の定義と異なる意味で使っているように思う」。平和学が専門の坪井主税(ちから)・札幌学院大名誉教授はこう話す。
坪井氏によると、「積極的平和」は第二次世界大戦中の一九四二年、米国の社会学者クインシー・ライト氏が執筆した「戦争学」の中で、「消極的平和」と併せて使ったのが始まりとされる。その後、米国に留学したノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥング氏が「消極的平和」を戦争のない状態、「積極的平和」を戦争だけでなく貧困や搾取、差別などの構造的な暴力がなくなった状態、と定義して定着した。
安倍首相は十五日の所信表明演説で、「『積極的平和主義』こそが、わが国が背負うべき二十一世紀の看板」と強調した。続けて、自衛官の海外での活動などに触れ、日本版「国家安全保障会議(NSC)」の創設を意欲的に語った。有識者会議「安全保障と防衛力に関する懇談会」の会合でも、安保戦略の柱に「積極的平和主義」を据えることを確認している。
米国の保守系シンクタンク・ハドソン研究所で先月行ったスピーチでも、安倍首相は「積極的平和主義」に言及した。ただ、スピーチで使ったのは「Proactive Contributor to Peace」。和訳すれば「率先して平和に貢献する存在」となるが、首相官邸のホームページ上では「積極的平和主義」と訳されている。
ガルトゥング氏の言う本来の「積極的平和」は英語では、「Positive peace」。だから、少なくとも英語圏の世界では、安倍首相の発言は「積極的平和」とは受け取られないわけだ。
それどころか、坪井氏は「Proactiveは軍事用語では『先制攻撃』のニュアンスで使われる。米国人は『日本は集団的自衛権の行使容認に踏み切ります』と受け止めるだろう。逆に、和訳によって、日本では『軍事力を行使しない』と誤解する人がいるかもしれない。言葉のマジックだ」と指摘する。
水島朝穂・早稲田大教授(憲法学)によると、ガルトゥング氏の「積極的平和」という考え方は、七〇年代に日本に入ってきた。だが、水島氏ら憲法学者が、「積極的平和」を前面に出して訴えるようになったのは九〇年代に入ってからだ。
九〇年にイラクがクウェートに侵攻し、九一年に湾岸戦争が始まった。憲法九条の規定で自衛隊は多国籍軍に加わらない代わりに、日本は戦費などで百三十億ドルを支出した。一兆円以上の負担だったが、クウェート政府が米紙に掲載した諸外国に対する感謝の広告に日本の名はなかった。以降、自衛隊の国連平和維持活動(PKO)参加の議論が活発になる。
自衛隊の海外派遣に向けた動きに対し、水島氏らは「武力の行使ではなく、貧困や差別などを取り除く国際貢献こそが重要だ。憲法前文には、そう記されている」などと主張した。「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有する」というくだりだ。水島氏は「まさに『積極的平和』を規定している」と話す。
だが、結局、PKO協力法が九二年に成立した。同年、陸上自衛隊の部隊が海外初となるカンボジアに派遣され、その後はイラクなどに派遣されるようになった。
実は保守系の一部の学者も九〇年代から「積極的平和主義」を使っている。九一年の衆院特別委員会の公聴会では、自衛隊の海外派遣が「積極的平和主義」につながると発言した有識者もいた。
本来の意味合いとは異なるため保守系の学者が使うことは少ないようだが、あえて使う学者や団体もある。安倍首相が参与を務める民間のシンクタンク「日本国際フォーラム」もその一つだ。
〇九年発表の政策提言の表題は「積極的平和主義と日米同盟のあり方」だ。「積極的平和」が日米同盟に必要なものに位置付けられ、「日米同盟維持のため、集団的自衛権が行使可能な権利であることを認めなければならない」といった主張をしている。
本来の趣旨とは全く違ってしまっている。では、ガルトゥング氏の言う真の「積極的平和」実現のために、日本はどんな貢献ができるのだろうか。
今月、「平和構築入門」を出版した東京外国語大の篠田英朗教授(国際関係論)は「開発援助や医療など、あらゆる分野で活躍の余地がある。重要なのは、情熱ある若者が関われるように、政府が支援する仕組みを作ることだ」と話す。「日本の政治家は嫌でも、政治のダイナミズムに関心のある若者もいるだろう。紛争地の調停活動に参加し、力を発揮してもらえばよい。就職難の若手弁護士に国際法を教え、国連など国際組織での活躍を後押しする方法もある」と政治や法律の分野でも貢献が可能だ。
また、人道援助の分野で活動する日本の非政府組織(NGO)は少なくないが、メンバーが団体内や業界内で固定化する傾向にあるという。「政府がNGOのリーダーらを国連に推薦したり、外務省で雇用したりすれば、人材育成にもつながる」と提案する。
アジア平和貢献センター理事長で元早稲田大総長の西原春夫氏は「日本がかつて戦争を起こした反省に立てば、真の平和のために米国や中国などの軍事大国を戒め、各地の紛争を仲裁する世界の調整役になるべきだ」と語る。ガルトゥング氏の祖国ノルウェーがパレスチナ紛争で調整役を務め、九三年のオスロ合意を実現させた実例を挙げ、「日本も同じ役割を担える。貧困国支援などの実績などを日本は世界で評価されており、調整役として受け入れられるはずだ」と語る。
紛争地域の復興に、若者を派遣することも提案する。「文化財の補修などに携わり、戦争の傷痕を直しつつ、戦争がもたらす惨状、平和の意義を現地で学べる。新たな平和の担い手を育てることにもなる」
加藤哲郎・一橋大名誉教授(政治学)が説く積極的平和は「核なき世界の実現」だ。「全ての国が核兵器を捨てない限り、真の平和は訪れない。核兵器につながる原発ゼロを含め、核に頼らない日本の将来像を考え、世界に働き掛けるべきだ」と強調した。
<デスクメモ> 湾岸戦争でバグダッドが空爆される様子をテレビで見たことをよく覚えている。映画のようで、どこか感覚がまひしていくように感じた。一九九〇年代には、旧ユーゴスラビア紛争も起きた。八四年のサラエボ冬季五輪が大成功だったのに。戦争がなくならない。まず、目指すべきは「消極的平和」か。 (文)
資料
ミリタリーをどうするか ―憲法9条と自衛隊の非軍事化―
http://www.ritsumei.ac.jp/…/pu…/journal/documents/13_p01.pdf