この消えていく原因となるのが、もっとも人間社会にとって『悪』になるということだといえる。
それは交換機能材であった貨幣の出発時点に、保存機能があるということを最初に利用した人間から始まってしまったといえる。
その社会の出発点(ここでは旧石器時代としておく)にあった平等社会であり、対等社会であり、助け合いの社会であった時代。だが貨幣としての利用は、やがて現代までの長い時間に多くの人間らしさ、多くの優しさを奪ってしまった。
それらの貨幣は人間社会を壊してしまう機能として、保存機能が多用できることにあったということになる。
貨幣に保存機能が無かったなら、人間社会はうまくいっていたはずである。
交換機能だけの社会であったなら、私が書いたA・Eの関係で市中には少量の貨幣だけで労働の交換がスムースに行われていたはずであり、そこにはデフレやインフレも無く、働けるものは他の人が作り出した商品と、自己の労働で得た貨幣と交換すれば生活が成り立つ社会になる。つまり失業もない社会であるといえる。
現在の社会の大罪。それは自身の労働を貨幣に換えることができないための社会にしてしまったことにある。
一部の人間が貨幣の持つ保存機能を最大限に利用して貨幣を取得してしまうことにある。しかも貨幣が持つ保存機能を利用すれば今後さらに多くの貨幣が一部の人間に流れてしまい、市中から貨幣が消えていくことになる。
いくら金融緩和をということから、不足した量の貨幣分を印刷し、市中につぎ込んだとしても、結果はより多くの印刷した紙幣も、一部の人間の懐に入るだけであり、印刷することは一部の人間に渡すだけの行為となる。
市中から貨幣が消えてしまう最大の原因。それは貨幣の機能の中での保存機能にあったということになる。
保存機能を規制する社会、それは社会主義でもなく、当然資本主義でもない社会ということになる。そこから未来に開ける社会が考え出されなくてはならないと考えるが。
貨幣がどのようなかたちの中で、市中から消えていくのかの「Ⅲ」を書いてみたい。
人が商品を買ったとしても支払った貨幣(お金)は市中からは消えない、何度も言うようだが人の手から人の手に渡るだけに過ぎない。たとえそれが株であろうと消えるものではない。それが現在値上がりしている金(キン)であろうとも、AからBに貨幣を通して所有者が変わっていくに過ぎない。貨幣は何度でも交換を通して巡っていくだけである。
では消えてしまう原因は何なのか。消えるということは貨幣量が市中から減少していき、少なくなった貨幣をお互いが取り合う状態になるということになる。つまり取り合うために自己の労働を限界まで下げることになる。そこには不況という社会状態になる。そこで政策として新たに貨幣をつぎ込まなくてはならない。量的には大量にばら撒いたはずの貨幣、その貨幣は誰かが持っていることになる。
次はまたの機会に
それは交換機能材であった貨幣の出発時点に、保存機能があるということを最初に利用した人間から始まってしまったといえる。
その社会の出発点(ここでは旧石器時代としておく)にあった平等社会であり、対等社会であり、助け合いの社会であった時代。だが貨幣としての利用は、やがて現代までの長い時間に多くの人間らしさ、多くの優しさを奪ってしまった。
それらの貨幣は人間社会を壊してしまう機能として、保存機能が多用できることにあったということになる。
貨幣に保存機能が無かったなら、人間社会はうまくいっていたはずである。
交換機能だけの社会であったなら、私が書いたA・Eの関係で市中には少量の貨幣だけで労働の交換がスムースに行われていたはずであり、そこにはデフレやインフレも無く、働けるものは他の人が作り出した商品と、自己の労働で得た貨幣と交換すれば生活が成り立つ社会になる。つまり失業もない社会であるといえる。
現在の社会の大罪。それは自身の労働を貨幣に換えることができないための社会にしてしまったことにある。
一部の人間が貨幣の持つ保存機能を最大限に利用して貨幣を取得してしまうことにある。しかも貨幣が持つ保存機能を利用すれば今後さらに多くの貨幣が一部の人間に流れてしまい、市中から貨幣が消えていくことになる。
いくら金融緩和をということから、不足した量の貨幣分を印刷し、市中につぎ込んだとしても、結果はより多くの印刷した紙幣も、一部の人間の懐に入るだけであり、印刷することは一部の人間に渡すだけの行為となる。
市中から貨幣が消えてしまう最大の原因。それは貨幣の機能の中での保存機能にあったということになる。
保存機能を規制する社会、それは社会主義でもなく、当然資本主義でもない社会ということになる。そこから未来に開ける社会が考え出されなくてはならないと考えるが。
貨幣がどのようなかたちの中で、市中から消えていくのかの「Ⅲ」を書いてみたい。
人が商品を買ったとしても支払った貨幣(お金)は市中からは消えない、何度も言うようだが人の手から人の手に渡るだけに過ぎない。たとえそれが株であろうと消えるものではない。それが現在値上がりしている金(キン)であろうとも、AからBに貨幣を通して所有者が変わっていくに過ぎない。貨幣は何度でも交換を通して巡っていくだけである。
では消えてしまう原因は何なのか。消えるということは貨幣量が市中から減少していき、少なくなった貨幣をお互いが取り合う状態になるということになる。つまり取り合うために自己の労働を限界まで下げることになる。そこには不況という社会状態になる。そこで政策として新たに貨幣をつぎ込まなくてはならない。量的には大量にばら撒いたはずの貨幣、その貨幣は誰かが持っていることになる。
次はまたの機会に










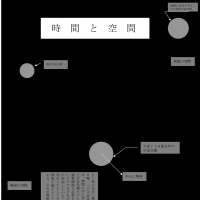
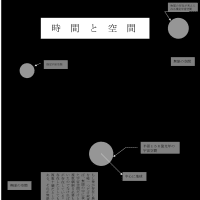



巨大損失はデフォルトでしか解決できない。ロシヤのようにデフォルトを行えば直ぐに復活できる。武力のあるところは強い。やくざの世界と同じだ。
米国はITバブルを解決せずに、次の住宅バブルとレバレッジで復活した。こんどはどんなバブルを仕掛けるのか。
バブルとデフォルトを繰り返すことで、都市が生まれ文化が生まれてきた。
球根が高値で売れたので、家を買い車を買う。住宅関連産業は潤い、車関連産業は潤う。その購入した球根を高く次の人に売る。売ったもうけから家を買い車を買う。住宅関連産業は潤い、車関連産業は潤う。オランダでは球根一個で家が買えた歴史がある。上がると思うから高値がつく。しょせん球根である。値段が上がりつづけることはできない。上がると思うから高値がつくが上がらないとなると本来の球根の値段になる。最後に球根(ババ)を持った人が損を背負。損失が大きくなれば、ババを持った人はデフォルトになる。でもそれまで潤った住宅関連産業、車関連産業の資産は残る。急速な社会発展はバブルで生まれてきた。
だれもババを引きたくない。そこで保険を考えた。保険があるから大丈夫、安心して新種の球根を買いましょう。 新種の球根は保険があるから売れに売れた。また住宅関連産業は潤い、車関連産業は潤った。 しょせん球根、買った値段より高値になることの限界はある。一斉に球根の価値は下がった。 そのときのための保険に一斉に走った。 一斉に請求されたら保険は自力では払えない。 このまま保険が破産したら大混乱が生じますよと政府をおどした。 国が保険の尻拭いをすると宣言して当面の大混乱は回避した。米国はじゃぶじゃぶ紙幣を発行して、保険をたすけている。保険の損を埋めるうちは、金は氾濫できない。
国をおどした金の遊び人は、次の金儲けに動いている。安くなった土地を買う。安くなった会社を買う。次の金儲けの水源地を買い占める。
球場の名前をお金に換えたように、海にも不動産価値をつける。 空気にも不動産価値をつける。 CO2と同じこと。またバブルが発生する。住宅関連産業は潤い、車関連産業は潤う。 こんなことは持続可能ですか?
こんな成長はいらない。
価値を転換しよう。
子孫のために、持続可能性のあることに価値をつけましょう。
持続可能性につながらないことは、税金をかけましょう。
>バブルとデフォルトを繰り返すことで、都市が生まれ文化が生まれてきた。
残念ながら私はこのようには考えていませんでした。認識不足でした。
ここには新しい文化(はたしてこれが文化なのでしょうか)が生まれたと同時に多くの犠牲者も生まれたといえます。投資をした人は欲で投資をしたのでしょうが、この状況のなかで職を失い、一度しかない人生を無理やりあの世での楽しい生活を夢見て、命を自ら落としていく。どうしたらいいのかを考えます。
私が書いたことは事実を書いてきたと自負しています。真実の前に人は逃げることはできないはずです。なんとか皆さんと一緒に、どのように生かせるかを考えて行きたいと思います。
>その量を推し量る議論でなければ、貨幣は巷にあふれていますので、「消えてしまう」とは「消費した」という解釈なら理解できます。
昨夜、阿修羅に入れたA・Eの関係の中では1枚の貨幣は物を買っても消えてはいません。
ただ人の手から人の手に渡っていくだけです。つまりお互いの労働によって作られた商品と商品が貨幣によって交換されていくだけです。
そのような流れのとき誰かがその一枚の貨幣を蓄蔵したら交換という流れは止まってしまい。そこには労働が交換できないという、失業という状態に追い込まれてしまいます。
つまり蓄蔵(この状況は色々あります)が貨幣が市中から消えてしまうことです。
企業通貨は生産性に裏付けられているから通貨バブルもおきにくい。