東北地方太平洋沖地震に対し国が巨額の復興資金を投入するという。
ただ単に巨額の資金を投入したとしても、やがてはその資金も市中から消えてしまい新たな資金を必要とする事態となることははっきりしている。
なぜ市中から消えてしまうのかはさておき、その投入された資金がやり方によって際限なく回れば、小額の資金であったとしても絶えることなくなく人から人へと 回っていくのであれば、多くの復興ができ、それはやがては日本全体に広がっていくことになると考える。
貨幣とは何か今一度検証してみる必要があると考え、そこで以前私が書いた文章
「A・Eの関係」からどのように貨幣を生かせばいいのかを考えてみた。現在の社会では実現は不可能とまず考えるが、いくらかでも貨幣を理解する手がかりになればと願い考察してみます。
「A・Eの関係」
たった1枚の貨幣(お金)が作り出すもの。最初の出発は1枚だけの貨幣と考え。
Aが自己の労働を1枚の貨幣(お金)に換え、AはBの労働で作り出した商品と交換します。そこにはAが持っていたお金がBに渡ります。Bはそのお金でCの労働で作り出した商品と交換します(つまりCの商品を買うという行為です)Aが所有していたお金がBを通してCに渡ったわけです。CはDの持っている商品(Dの労働で作り出した商品)を買います。DはEの持っている商品(Eの労働で作り出した)を買います。そしてEはAが持っている商品を買います。 つまりここでは簡単な例ですが最初にAが持っていた1枚のお金がB、C、D、Eを通してAに戻ってきて一巡したわけです。そしてお互いに作り出した商品が売れたということになります。 さらにまたAがBの商品を買い、その関係がEまで続きAの元へ戻ってきたとします。そこにはAからEまで2回商品を製造しなくてはなりません。たった1枚の貨幣(お金)が2回の商品製造をさせたことになります。この関係がさらにAからEを通してAまで戻ってきたとき1枚の金が3回の商品を各自に作り出させたわけです。 このことが貨幣と労働との関係だと捉えています。ただ、そこには現実の経済社会では簡単なA・Eの関係ではなく複雑な貨幣と労働との関係が行われているということです。つまり1000万の購買があれば1000万通りの貨幣(お金)と労働との交換があるということです(そのことが今まで経済をわかりにくくしてきた原因です)働くことのない子供は物を買うために親から小遣いを貰うとか、老人では現在の社会では年金というかたちで貨幣を手に入れ貨幣と他者の労働で作られた商品と交換し手に入れます。
ここで私がA・Eの関係を取り上げた意味は、貨幣が持つ機能のうち交換機能のみが人間社会にとって重要であるということです。つまり保存機能を取り除いたとき貨幣は市中に留まり、上記のように限りなく人の労働と労働の交換の仲介物として周り続ける。そこには今回の震災においても人々の労働が喜びを持って復興への手助けとなっていくと考えます。
ではどのような方法があるのかということになりますと、簡単に言えば地域通過と同じような性質を持つ復興通貨の発行です。現在流通している「円」という通貨とは別に、同じ価値(1円に対し1復興円)を持たせた「復興円」を別口で発行し、市中に供給する。ただしあくまでも交換機能のみに限定された通貨ということになります。
これはどういうことになるのかと言いますと、まず保存機能とはどのようなものなのかということから説明します。現在発行されている円は預金ができ、日本では少ないながらも利息を生むという通貨であり、また銀行等を通し貸付という形で使われている通貨。当然貸付には金利という金が金を生む性質が与えられています。企業が金融機関から借り入れを起こし設備資金・運転資金として使う。だがやがては返済をしなくてはならない。返済された分は当然市中から減少していくことになります。つまり貸付をおこなった当時は一時的に市中にお金は増加し、交換に回る形でゆとりをもっていますが、返済していく段階では新たな貸付を行わない限り市中からお金が減少していきます。
ましてや現在の日本の経済状況では、企業に新たな貸付というリスクを金融機関がおうことになるよりは、国内で貸付を行うより、海外でより有利なリターンを求めていくかたちで銀行や金融機関が主導して日本国内からお金を逃がしていくことになります。
そこで復興資金として新たな財源を組み(円)を大量に増刷し市中にばら撒いたとしてもやがては貸付金の返済、または金融機関への預金、そのほか金融機関を通してよりリターンを求めて国内からお金は逃げてしまい、市中ではお金が減少してしまうことになります。
そこで減少させない方法、それは発行された貨幣から保存機能を取り上げるしかないといえます。ただ現行発行されている通貨で保存機能を取り去ることは不可能といいうことで…。
ここで保存機能を持たない、いや持たせない通貨を新たに別枠として発行するという手があります。たとえばその呼び名を前に書きましたが「復興円」という形の地域通貨的性質を持った交換機能に特化させた通貨を市中に供給する。その復興円は銀行に預金することはできません。また現行通貨「円」の代わりとして借り入れの返済にまわすこともできません。つまりA・Eの関係で書いたような交換機能のみの流通しかありえないかたちでの市中投入です。それは生活支援的目的を持ったお金の投入であり、その新たな復興円に対しては返済猶予期間を長期に設け、当然のこと現行貸付金(円)も返済猶予を持たせる。
二つの通貨の同時流通で問題となるのは、どちらかの価値に比重が移ること、つまり現行流通通貨の円は保存機能としての金利等を生ませることができ、また株等の投資にも使えるが、もう一方の復興円では保存機能が無であるとすれば円を持ちたいと人は考え復興円では受け取りを拒否する等(今までの地域通貨の失敗)の反応となって現れる。だがその復興円はある意味ボランティア的要素を持つ通貨であるため人はその通貨を流通(注1。商品を通して労働を売る側、また労働を買う側)させることに喜びさえ感じるのではないでしょうか。
注1 商品は人の労働を通して作られるものであり、貨幣はお互いの労働の交換をスムースにさせる仲介物にすぎない)

私のコレクション。ヒスイの原石










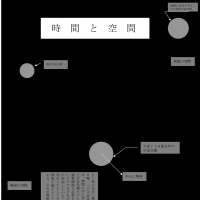
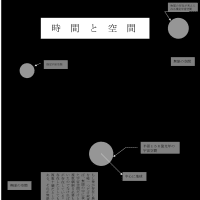



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます