貨幣はモノの価値を持続させるために自然に発現されてきたものと言える。
物々交換の時代には交換する物が相手が必要とするものであればたとえ野菜とか魚であったとしてもなんでもよかったが、それ等は消費期限が限られてしまう。つまり腐敗してしまうもので保存価値としてはゼロに等しい。
過去の時代それ等の淘汰の中から残ってきたものが最初時は貝殻等であったが、やがては腐敗しない物、いつまでも品質を保てるもの、保存ができ希少価値に優れているものとして唯一残ってきたものが金でありそれに続く金属となった。
ただ時代変遷の中でやがて管理する者が現れその地位が親から子そして孫へと世襲されてきた。それ等は保存機能に裏打ちされた物であり、保存された量がより多くまた価値の高いものであれば、それらを利用して人々の上に君臨することができた。
だが時代の進む中で産業が高度化され、当然そこで作り出された商品を多くの人が手に入れる時代となると、全ての商品なり他者の労働といつでも交換することができる利便性が優先され、金属貨幣は価値が減じ得ない物として一部の人たちの保存先として優先されてしまう。当然交換価値から始まった貨幣であるから、市中の量は限られたものであり、そこに一部の人々が保存してしまえば市中の貨幣は減少してしまう。その状態をデフレというのかもしれない。
金属には限界があることから大量に市中に出すことはできない。少量となった貨幣を人々は争って求めることになるが、貯められてしまった貨幣を再度市中に呼び戻すか、停滞していく経済状態に甘んじていくかの選択となる。
そこでは経済停滞の原因をつくつた者が一部の人間であることが分かったとしても、いや太古の時代から飼い慣らされてきた人々にはその原因は理解することができないのではないだろうか。
当然労働と労働の仲介物である貨幣の減少は経済停滞を招く、つまり貨幣が手に入らない状態は商品が売れない、売れなければ商品も作れない、やがて失業者の増大となり、ある意味社会不安となっていく。
物々交換の時代には交換する物が相手が必要とするものであればたとえ野菜とか魚であったとしてもなんでもよかったが、それ等は消費期限が限られてしまう。つまり腐敗してしまうもので保存価値としてはゼロに等しい。
過去の時代それ等の淘汰の中から残ってきたものが最初時は貝殻等であったが、やがては腐敗しない物、いつまでも品質を保てるもの、保存ができ希少価値に優れているものとして唯一残ってきたものが金でありそれに続く金属となった。
ただ時代変遷の中でやがて管理する者が現れその地位が親から子そして孫へと世襲されてきた。それ等は保存機能に裏打ちされた物であり、保存された量がより多くまた価値の高いものであれば、それらを利用して人々の上に君臨することができた。
だが時代の進む中で産業が高度化され、当然そこで作り出された商品を多くの人が手に入れる時代となると、全ての商品なり他者の労働といつでも交換することができる利便性が優先され、金属貨幣は価値が減じ得ない物として一部の人たちの保存先として優先されてしまう。当然交換価値から始まった貨幣であるから、市中の量は限られたものであり、そこに一部の人々が保存してしまえば市中の貨幣は減少してしまう。その状態をデフレというのかもしれない。
金属には限界があることから大量に市中に出すことはできない。少量となった貨幣を人々は争って求めることになるが、貯められてしまった貨幣を再度市中に呼び戻すか、停滞していく経済状態に甘んじていくかの選択となる。
そこでは経済停滞の原因をつくつた者が一部の人間であることが分かったとしても、いや太古の時代から飼い慣らされてきた人々にはその原因は理解することができないのではないだろうか。
当然労働と労働の仲介物である貨幣の減少は経済停滞を招く、つまり貨幣が手に入らない状態は商品が売れない、売れなければ商品も作れない、やがて失業者の増大となり、ある意味社会不安となっていく。










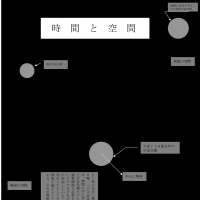
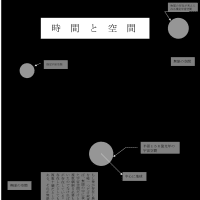



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます