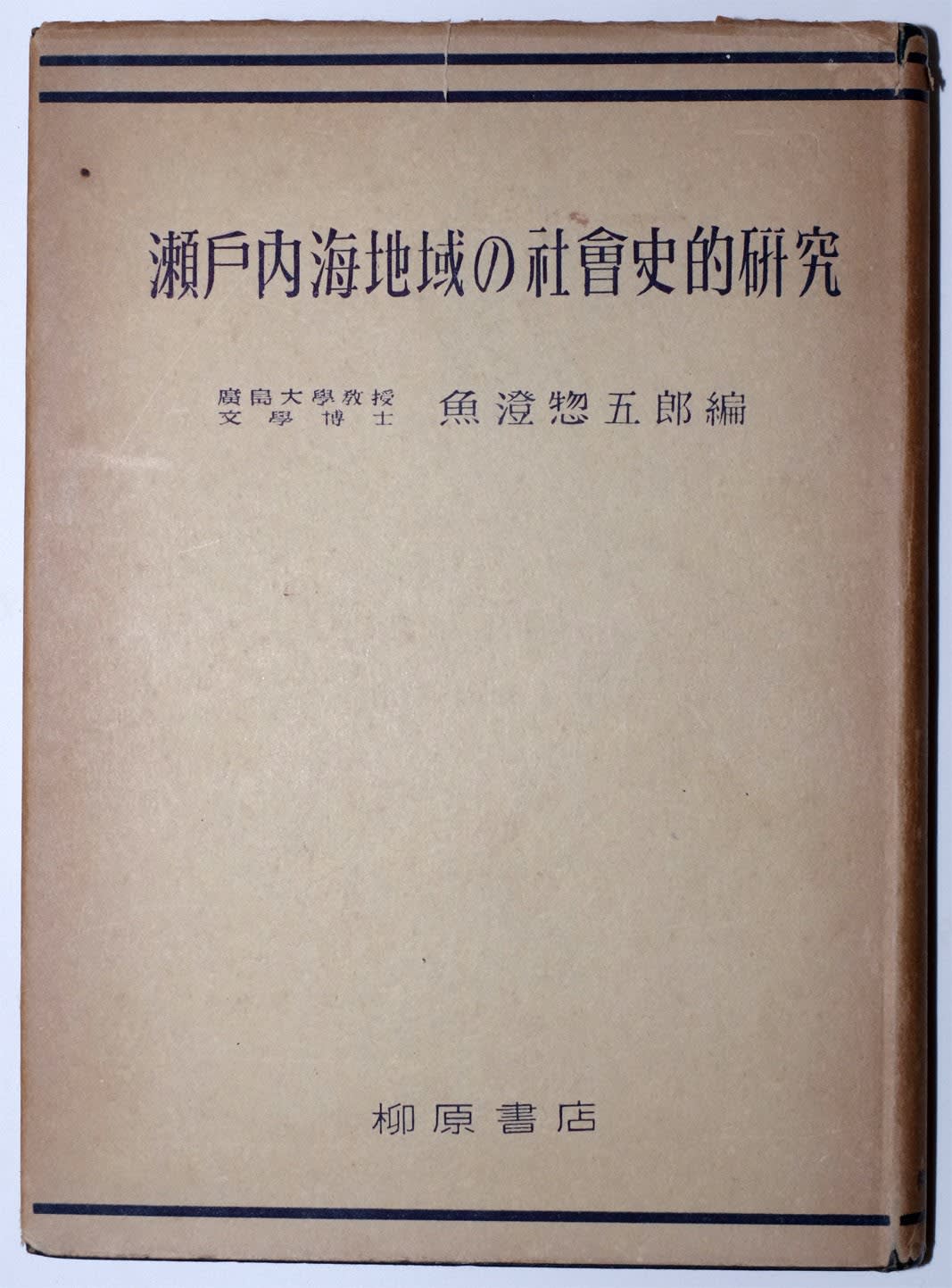
魚澄惣五郎『瀬戸内海地域の社会史的研究』柳原書店、1952
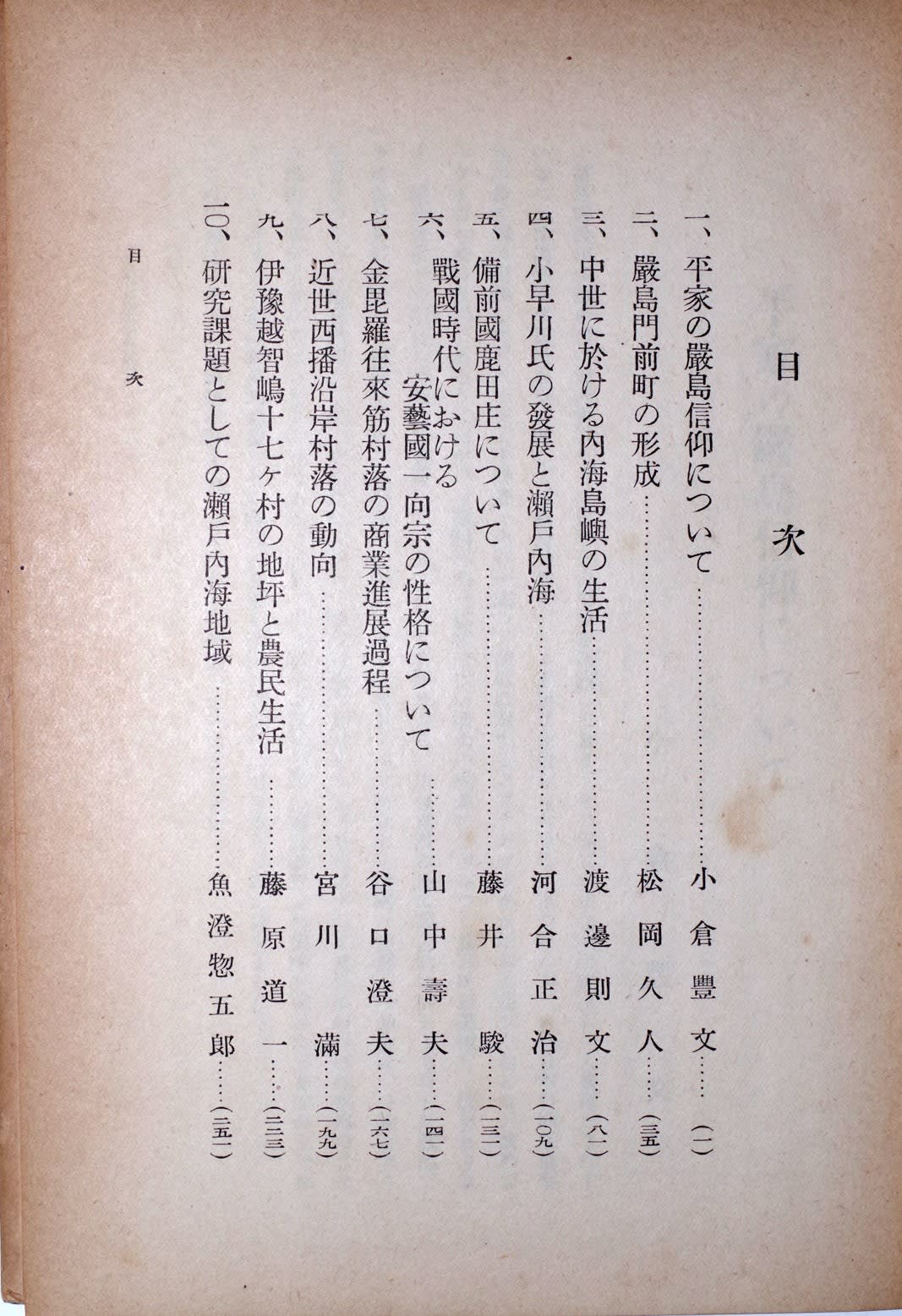
研究者をまとめ上げる定評ある魚澄の手腕。1950-1960年段階の地域史研究の一つの到達点を示す本書を紐解くことにした。
「研究課題としての瀬戸内海地域」。
こんなことをいまどき口にすると誰かから苦笑されそうだが、いまなら『方法としての中国』とか『思想課題としてのアジア―基軸・連鎖・投企』風にリニューアルする必要がある命題設定かもしれない。
類書のサンプル

図中(A):下組(下条)、(B)戸崎・・・A-Bが浦崎半島
松永湾を塞ぐ形で東西に拡がる浦崎半島(尾道市浦崎町、旧沼隈郡浦崎村)を歩いて気づくことはわたしの認識の枠組に欠落した海と結びついたというか、要するに海洋性の何かがここには息づいているという点だった。

松永湾浦崎下組串ノ浜より戸崎方面を望む。海浜の地割はアサリ育成場(最近はアサリの生育が悪く不作)
松永湾岸における地域史研究の課題を「渚の営み」の解明だと見ていたのが地方史研究者村上正名だったが、戦後世代の我々というのは、戦後経済の発展の中で連絡船が連絡橋に置き換わり、海辺の芦原が臨海工業地帯へと生まれ変わり、生活世界自体が徐々に遠自然的もの(ライフスタイル的には身近な海や山に背を向けるあり方)になっていった。私としてはそういう反省点を踏まえて過去の再構成作業を進めようと思っている次第である。
わたしがこれまで取り上げてきた海関連事項
 沼隈郡神村和田石井家に関連した妖火伝承「おやや伝説」の中には神村石井一族が海運と結びついたことを示唆するプロットがある(しかも、姻戚関係を通じてこの石井一族は備後国の島嶼部臨海部と深い結びつきを持つ)。
沼隈郡神村和田石井家に関連した妖火伝承「おやや伝説」の中には神村石井一族が海運と結びついたことを示唆するプロットがある(しかも、姻戚関係を通じてこの石井一族は備後国の島嶼部臨海部と深い結びつきを持つ)。魚澄惣五郎『瀬戸内海地域の社会史的研究』については取り合えず「研究課題としての瀬戸内海地域」だけは読んでおこう(既読)。
方向性としては戦前からの(瀬戸内式気候・多島海、四国と山陽地方、都と西国及び大陸とを結ぶ「海の回廊」的位置といった地理的属性を有する)風土論とか文化史/文化圏的学説を加味しつつ、大塚久雄・高橋幸八郎・松田智雄編, 『西洋経済史講座-封建制から資本主義への移行-』, 第I〜IV巻, 岩波書店刊,1960からの熱風を背中に感じながら史学研究(気分的には封建的土地所有、共同体、前期資本主義、資本主義の生産様式とその社会的構成の発達などの確認作業)を進める辺りだったろうか。
























