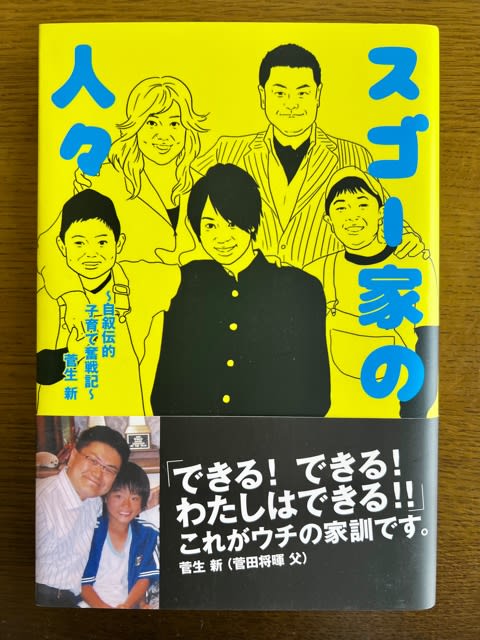





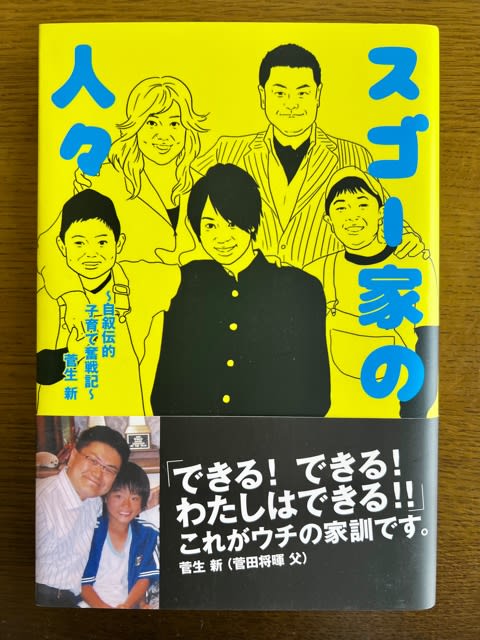





ケチをつけられた、お土産のえびせんですが、主人もけん太も「美味しい~」と、味の違いを楽しみながら食していました。
すでに完食!
「ね?鳩サブレじゃなくてもよかったでしょ?」と主人に言うと、
「いや、やっぱり鎌倉は、鳩サブレだよ。仙台は、萩の月、札幌は、白い恋人(他にもいくつか言ってました )とか決まってるじゃない~それが上手いから定番になったんだし」と。
)とか決まってるじゃない~それが上手いから定番になったんだし」と。
確かにそうだろうけど、保守的すぎる~
いろんな新しいものも生まれているわけだしね。
ここは、これだって決めなくてもいいよね。
昨日、池上さんの番組「意外なデータ60連発!」で、時代の変化を感じる興味深いデータがいろいろありました。
今日は少しその内容を書きだしますね。
【どちらの手でスマホを持つか】

それは、左手に受話器を持って、右手でダイヤルを回し、メモをとるという「固定電話」の名残だそうです。
私はもちのろんで、左手です(笑)しかし、そんな理由で?染みついているのですね(笑)
けん太は右手でした。やっぱり、若者だ~
けん太のスマホは、アイフォンのミニサイズですが、右手持ち、右手打ちが楽にできることもあって、そうしているそうです。
画面を消す「✖」も右上についているんだから、右手仕様に作られているんだよと言っております。ほんとですか?
【今は多くの若者が海外に興味がない!?】
インターネットの普及で情報が手軽に届き、行かなくてもわかる。
行く意義が見いだせないのかも?
情報が豊富なことで、危険までデータで知っているし、水が飲めないとか、食べ物がおいしくないとか?
あえて行きたくないという人も増えている?
確かに・・・それと、私が思うに、今はゲームだったり、家で楽しめるものも増えている。
出かけるより、家にいることの方が好きな子も増えている印象があります。
パスポート保有率ですが・・・

企業でも、急な海外出張の仕事があっても、パスポートを持っていなくて対応できない人が増えているそうです。
日本人の海外旅行離れの対策として、18歳の新成人に、パスポートを無料で交付する案が出ているそうです。
【若者の身長の低下が始まっている】

ずっと伸び続けていたが、40年前くらいから、ほぼ横ばい。最近は「低下が始まっている」という研究も。


身長は生まれた時の体重が関係しているのでは?と言われている。
今は、スタイルを気にして?痩せている妊婦さんが多いので、生まれてくる赤ちゃんも小さい傾向にある。
出生体重の低下が平均身長に影響している可能性があるそうです。
【週休3日にすると会社は儲かる!?】
イギリスの61企業、約2900人が参加した実験によると・・・
売り上げが、前年同月比で、平均35%増加。
39%の従業員がストレスを感じにくくなった。
71%の従業員の燃え尽き症候群のレベルが低下した。
61企業中56企業がそのまま週休3日を継続してみることに。
そのうちの18社が、週休3日を決定したそうです。
【キャッシュレスだとお金が貯まる!?】
様々な年代で調査したところ、キャッシュレス派の方が現金派よりも、約2.4倍という結果が。
キャッシュレスの方がお金を使っているという現実味がないのかなと思っていたので、ちょっと意外でした。

【紙の辞書で調べものをすると記憶に残りやすい?】
東北大学の実験によると、スマホと辞書では、紙で調べる方が脳が活動しているという結果に。

時間を置いて、調べた内容の意味を聞くと、紙の辞書を使った方が覚えている人が多かったそうです。
OECD(経済協力開発機構)の調査によると、
コンピューターの数が多い国ほど、数学の学力が低い。
インターネットを多く使う国ほど、読解力が低い。・・・という結果に。
タブレットの教科書より、紙の教科書の方が集中しやすい。
国によって学校によって、紙の教科書に戻すところも出てきているそうです。
【オンライン授業は倍速視聴でも理解度は下がらない】
アメリカによる実験。


再生速度が違う映像で学習。見た直後と1週間後にテストでの比較。
2倍速までは、同じ程度の成績。
2.5倍は成績が悪化したという結果に。
学習という明らかな目的がある場合、テンポよくスピードアップした方が注意力、集中力が高まりやすい。
ただ、まったく知らないことの勉強は倍速だと理解が追い付かないこともあるので注意。
講師が事前に収録した講義を、1.5倍速や2倍速で見ることを推奨する予備校もあるそうです。
【マーカーを引いたり一夜漬けはあまり効果がない!?】



マーカーを引くと引かないとの差は・・・点数に差がないという結果に。
マーカーを引くと、引いたところだけに気が向いて、全体の内容を関連付けて理解することが阻害されるのかもしれないと。
文章全体で何を意味しているのか、大事なポイントはなにか考えながら読むのが大事とのことでした。
この他にもいろいろ、興味深いデータが紹介されていました。
食事の写真を撮る人と、撮らない人では、撮る人の方が、食事をおいしく感じられるとか?
ひじきに鉄分が多いと言われていたのも、昔は鉄の鍋で下処理をしていたからで、今はステンレスなので、ほとんど鉄分がないとか?
全部で60個ですから。
時代は変わっていますよねぇ~
こういうものだと思っていたものも、時代の流れでそうではなくなっていたりする。
主人にも見てほしかったです(笑)
昨日の「あさイチ」
「教えて先輩たち!」Vol.4
視聴者のお悩みに先輩たちが答えてくれるというもの。
前回は男性タレントさんの回で、、所ジョージさんの言葉を紹介させていただきましたが、
今回の先輩たちは女性・・・夏木マリさん、竹内まりあさん、YOUさん、でした。
今回も、お~ と思える言葉の数々がありました。
と思える言葉の数々がありました。
いくつか紹介させていただきます。
【世の中のIT化に疲れる。どうすれば?】
YOUさん:息子が一緒の時は、丸投げ方式です。息子にすべてやってもらう。老眼なので読み上げてもらう。
司会者:年齢を重ねるほど人に頼るのを申し訳なく思ったり・・・ということはないですか?
そういう方はきっと立派にやってきたからこそ、言いづらい。
60歳過ぎたら、みっともなくていい。頼っていい。迷惑かけるのを甘えるのは違う。
頼れば、相手も成長できるかもしれない。「今日も老人に優しくしたんだ僕は」と思ってもられたら、老人的にはありがたい。
夏木さん:人間って変わることを嫌う生き物。めちゃくちゃ時間かかるけど自分でやってみる。少しずつ学習していく。成功体験すると出来るようになる。人に頼んでも、丸投げしない。「どうするのかな?」と一緒に見ている。「親切に教えてください。お願いします」って教えてもらえばよい。
【どうしたら他人と比べないようになれる?】
竹内さん:人間みなそうだと思うし、誰しも持っている感情。自分が羨ましいと思っているひとでさえ、違うところに悩みがある。じゃあ、自分はどうありたいか・・・「自分の好き」をみつけることにエネルギーを注ぐ。 嫉妬するだけだと、マイナスの感情だけど、憧れる気持ちはプラスの感情
夏木さん:若いうちは、他人と比べていたけど、40代で自分のやりたい舞台をスタートさせ、自分のやることに一生懸命になったら、周りを気に
しなくなった。
【やりたいことと、やらねばならないことに、どう折り合いをつける?】
竹内さん:やらなければならないことが圧倒的に多い。やらなければならないことを出来る限り、面白がってやる。人生は雑用の連続。楽して見つけている人は1人もない。楽曲制作と家庭。両方うまくやっているのではなく、私はこういう生活がないと逆に書けない。
司会の華丸さんは、やりたくなかったことの方が終わった後に達成感がある。やりたいことは、やっている時がピークで、その後、もう終わってしまったという喪失感がある。やりたくなかったことの方が、終わった後のビールがうまい!・・・と。確かに!!

【更年期を迎えてより感情的になる自分に落ち込みます。】
YOUさん:50過ぎたら、だいたいの人が機嫌悪い。気にしなくていい。「更年期かもしれないんだよね。イライラしているから気を付けて」と、先に言ってしまえば楽。 若い時は恥ずかしかったかもしれないけど、もう、恥ずかしいんで。全然、隠すことない。 人に言いふらして、どんどん解決する。そうやって気にしていることがストレスで大変だと思う。
大事なのは人と人とのネットワーク。更年期の悩みをいうと、たいがい、これがいいとかだの周りはよく知っている。それを教えてもらえばいい。それを後輩にも教えてあげる。シニアの方から「今日イライラしているから」と言われた若者は?・・「了解です」でいい。若者は「あいつ今日、期限が悪いらしいぞ」とみんなで共有し「今日、怒られても気にする必要ないぜ」でいい(笑)
【老後の夫婦の関り合い方】
夏木さん:言うなれば他人ですから、わかるはずがない。違う生活をしていて突然一緒に生活を始めて、やっと慣れてきた。(結婚13年目)
「ありがたい」と思って言葉にする。「こんな私と一緒にいてくれてありがとう」と心から思うと、ずっとやっていけそうな気がする。相手に何かするときは、見返りを求めてはダメ。求めると、「こんなにしたのに何もないの?」になる。自分がやりたいことを相手にする。結果、相手が喜ぶほうが健康的。
YOUさん:一対一で向き合うのって、毎日はなかなか難しい。互いに何かを見つけて、気を散らす。もっと勝手にすればいいんじゃないかな。ずっと一緒に生活をしていて(相手の)テンポや性格を分かっている分、「しょうがねぇな。こいつだったら」ってなるのかな?
竹内さん:夫婦っていうのはお互い様。一方的に相手が悪いと思っていても、悪い部分を引き出してる自分が、たぶんいる。1回、自分も見つめ直す。 以心伝心はない。伝え合うことが大事。 そこに解決策がなかったとしても、話すプロセスがあるかないかで違う気がする。
【受験期でしたいことができないイライラの発散法は?】
YOUさん:イライラする子ほど成長する。私も本当にひどかった。全然、当たっていいと思う。壊していいものは全部、壊したらいい。床でも壁でも天井でも壊して、賃貸じゃない場合ですけど、若い時はしたいことができなくてイライラしている。みんな、それやって大人になる。したくないことをしている状況が勉強。
【人生の終わりに「いい人生だった」と思えるためには?】
YOUさん:ここ10年くらい前から、いつ死んでもいいと思っている。楽しかったので、ありがたかったです。1人暮らしで、倒れて一人で亡くなっても、「孤独ではなかった」と思える。ここまでの60年間、これだけ楽しいと思えたのは、人との出会いかな。そう思わせてくれる人にいっぱい会ったから。
竹内さん:人生が終わる時に後悔ではなくて、「感謝」や「愛」で終わるためには、自分が幸せに生きられたかよりも、自分以外の人をどれだけ 幸せにできたか。自分が幸せじゃないと人を幸せにできない。自分が満ちていないと、人のことまで考える余裕がない。自分を犠牲にして何かを我慢しながらだと、人は助けられない。自分も幸せになれるよう工夫しながら、自分以外の人のことが考えられると理想的。
「人生で心に響いたひと事」(視聴者からの投稿)
〇「きづく」ということは、「傷ついて、気付いて、築く」ということ。何かを築くときは「傷つく」ところから始まる。
〇選んだ道を正解にする。
最後の「選んだ道を正解にする」は10代からの投稿でした。
10代から悟りの境地ですね。凄いなぁ~
人それぞれ性格も環境も違うのだから、これが正解なんてものないですものね。
正解は自分の中にある。
(人がなんと言おうと )自分がよしと思った人生を歩んでいけばいいのだと思いました。
)自分がよしと思った人生を歩んでいけばいいのだと思いました。
少し前ですが、目に留まった記事。
今年の春頃の記事のようですが。
「ほめて育てる」ということが言われ始めた1990年代以降、若者の自己肯定感が高まるどころか、むしろ低下していると。
高校生の意識調査(日本・アメリカ・中国・韓国の比較調査)でも、「自分はダメな人間だ」という項目が「よくあてはまる」と答えた日本の高校生は、「ほめて育てる」ことがあまり言われていなかった1980年には12.9%だったが、「ほめて育てる」ことが徹底して行われるようになっていた2014年には25.5%と2倍になっているとのこと。
しかも、「まあそう思う」も含めて、「自分をダメな人間だと思う」という日本の高校生は、2014年には72.5%となっており、7割以上が「自分をダメな人間だと思う」と答えているそうです。
そうなの?? って思いました
って思いました
『ほめると子どもはダメになる』の著書である、臨床心理学者で、MP人間科学研究所代表の榎本博明氏のインタビュー記事でした。
何故、そうなってしまったかを分析されていました。
「ほめて育てる」は、1990年代に、欧米の教育論の表面だけをまねて生まれた風潮だそうです。
アメリカやヨーロッパには、「子どもをほめるときはしっかりほめる」という感覚が根づいています。「愛しているよ」「大好きだよ」といった言葉がけも積極的にします。
けれどそれは、普段の対応が非常に厳しいからであるからこそ。欧米では、親や教師は絶対であり、子どもはそれに従うのが社会のルール。子どもは小さいうちから親とは別の寝室で寝て、学校の成績が悪ければ容赦なく留年や退学になる。
会社でもそう。アメとムチでいえば、子どもを取り巻く社会環境がムチである。だから親は、適切なタイミングで「ほめる」というアメを差し出し、子どものやる気を引き出したり、親子間の信頼関係を築いたりする。日本ではそうした文化的背景を省みずに、アメの部分だけを取り入れてしまった。
欧米に比べると、日本はもともとが子どもにやさしい社会。子どもと一緒に寝るのは当たり前だし、泣けばすぐにあやします。学校は出席日数が足りなくても、それぞれの学年に見合う学力が育ってなくても、なんとか進級させようとします。
つまり、子どもを取り巻く環境がアメの日本では、親や大人があまりほめずに叱ることでアメとムチのバランスがとれていた。しかし、叱らない子育て、ほめる子育てが普及した結果、子どもはアメだけをもらって育つようになってしまった。
厳しいことを言えば気まずい雰囲気になったり、相手に嫌われたりする可能性もある。そうした事態はできるだけ避けたいと思うのが人情。だからこそ、「子どもはほめて育てよう」「叱らなくてもいい」というメッセージは、多くの人にとって魅力的だった。「やさしいお母さん」「理解のあるお父さん」だと思われたい保護者に支持され、急速に広がっていった。
たとえば身近な例で・・・
食べ物の好き嫌いが激しい子どもに食べるようにどう促すか。まず「食べなさい」と命じるのは共に同じ。それで食べないと、米国の親だったら、だんだん語調を強めて「食べなさい!」と強硬に出る。ところが日本人の親は、お願い調に転じる。「食べてちょうだい」「お願いだから食べて」という具合。さらには「今日食べなくても、明日は食べるよね」と譲歩していく。それでも食べないと「もういい」と最後通牒。
米国の学者に言わせると、上の立場の親がお願いをするのが、日本ではなぜ説得の言葉表現になるのか、と不思議がられる。「もういい」は心理的な一体感や関係性が壊れるよ、という暗黙の脅しである。
「ほめられる」というのは、他人にポジティブな気分にさせてもらっているということ。それに慣れてしまうと、ネガティブな状況に耐えられなくなる。その結果、傷つきやすくて、忍耐力がなくて、頑張れなくなる。正しいやり方を指示されただけなのに、「攻撃された」「自分を否定された」と感じて傷ついて、心が折れてしまう。なかには、開き直って自分を正当化する子もいる。
自己肯定感は、厳しい状況を乗り越え、「自分は頑張った」と思える時に高まる。頑張ってもいないのにただ褒められていい気持ちになっていたのでは、本当の自己肯定感は育たない。常にほめられている子は、「人にほめられるかどうか」で心のあり方が揺れてしまう。つまり、自己肯定感を他者に依存している。ただおだてられて育てられてきたから、がつんとやられたらぽしゃんとなる。だから自己肯定感は低い。
子どもをダメにしないほめ方とは・・・
大したことをしていないのにほめると、子どもは「なんだ、この程度でいいんだ」と思ってしまう。あるいは、「これくらいでほめられるなんて、自分はあまり能力がないのかも」と感じてしまう可能性もある。
勉強でもスポーツでも日ごろの行いでも、ほめるときは「結果」や「能力」ではなく「プロセス」や「姿勢」をほめる。
褒める時は、褒めて、叱る時は叱る。
このメリハリが大事とのことですが、教育現場では、子どもを叱ると保護者からクレームがついたり、大変のようです。
「子どものためだと思っても叱ってあげられない。鍛えてあげられない」という嘆きの声も。
子ども達はどう受け止めているのか・・・
「叱られることに耐性がない自分たちはこのままで大丈夫だろうか」と心配する大学生や、「ほめればいいと思っている自分の母親を見ていると悲しい気持ちになる」「以前は親がほめるばかりの友だちが羨ましかったけど、そういう子はすぐに心が折れるから、今は親に心を鍛えてもらってよかったと思ってる」などと話す学生もいたそうです。
少数ですが、違和感を感じている子どもは一定数いるそうです。
他にも、小学生の問題児が、叱られることなく悪さがエスカレート。ある時、ある先生に呼びつけられ、叱られ、問題行動がなくなる。「あの先生は叱ってくれた」と言っていたそうです。
やはり、アメとムチのバランスが大切なんでしょうね。
私は、かつて、一度、「褒めてみよう」と思って、実行したことがあります。
けん太に「なんの教育本、読んだのか知らないけど、そういうのやめてくれる?」と言われてしまいました。
バレバレ
敵は恐るべし
急に涼しくなりましたね。
一昨日から寝る時のエアコンを消しましたが、昨日はパジャマを半袖から七分袖に。
今朝は、18℃で、上着が必要なくらいでした。
昨日も今日も、けん太は時間に出ています。
そんなことをいちいち報告するのもなんですが
昨日は、主人とお墓参りに行ったのですが、けん太を駅まで送ってあげてから、霊園に向かいました。
たまにはサービスしてあげましょう
主人には出発時間を告げてあったのですが、その5分前にリビングに現れて、「じゃあ、車出して待ってるから~」と、出て行った。
けん太はまだシャワー中
ほんと、全てのことにおいて「せっかち」なんです。
準備万端。計画通り、きっちりこなす。
なのに、その息子は「スロー」過ぎ。
時間の予測がつかない。そもそも、計画なんて立てやしない。。。
足して2で割ってほしいものです
今日は、記事にしようと思いつつ、すっかり忘れてしまっていたことを書こうと思います。
8月に放送された「あさイチ」のお悩み相談、教えて先輩たち・・・の内容。
さだまさしさん、所ジョージさん、松重豊さんという大先輩たちが質問にお答えになっていました。
それぞれに、深い内容ではあったのですが、特に印象に残ったのが、所さん。
なんか視点が違うというか・・・どんな答えが出てくるのか想像がつかず、興味深かったです。
こうやって考えればいいんだなと、気付きを与えてくれたので、
一部ですが、ここに書きだしてみたいと思います。
番組を観た方は思い出していただければ
Q:落ち込んだ時は?
A:落ち込まないからね(笑) 自分を高みに置いてる人が落ち込む。始めにうまくいかないことは失敗じゃない。うまくいくまでやる。そしたら失敗は一個もない。
Q:ロックな反抗期なこども
A:反抗期は酷けりゃ酷いほど良い。やがて気付くから。もっと返してくれるから。親孝行への貯金。
Q:若い世代とのコミュニケーション
A:同等に接する。
Q:50代からの生き方
A:年いくつだとか思ったことがない。楽しそうな人のところにしか人は集まらない。自分を見てるのは周りの人、自分のことを見るのは朝(鏡)だけ。周りの人に「良かれ」ということをするのが生きること。
Q:結婚10年、「美味しい」と言わない夫。足りない時はカップ麺を食べてる。切ない・・・
A:初めからカップ麺、出しとけばいい(笑) 価値観なんか違うにきまってる。自分と結婚したんじゃないんだから。2つ人生楽しめる。
Q:輝き続けるヒミツ
A:いつも楽しそう。1973年が僕の未来。過去を理想の未来として暮らしている。