先日、けん太と夕食に、ピザを食べました。
冷凍ピザ生地を利用しての3種類。

この3枚目のピザをカットしたら・・・
「ねぇ〜ケーキの切れない大人なの?」と。
「へ???」
「認知ゆがんでない?大丈夫?」
「は???」
確かに、トマトとアスパラを切断しないようにと切ったら、いびつな6等分になってしまったんです

そのことを言われているんだろうなとはわかったんですが、
認知のゆがみ??・・・はい??? でした。
でした。
 でした。
でした。そして、見せてくれた画像が、この本でした。
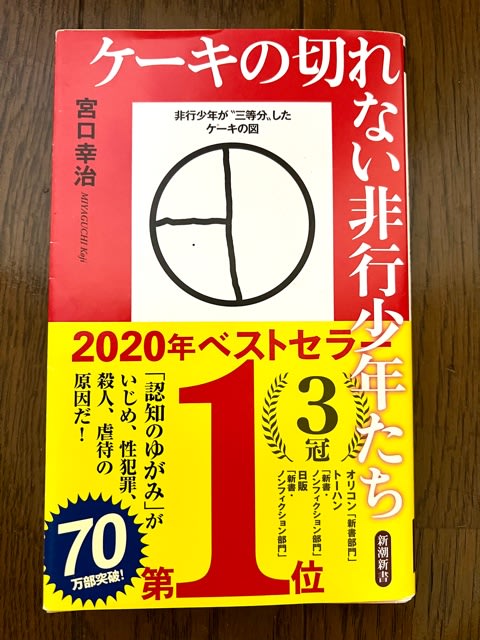
なんとなくタイトルに聞き覚えはありました。
ケーキの切れない非行少年って?
これが、3等分?というケーキの図にも興味を持ち、
気になって、さっそくその日にメルカリで購入しました

非行少年に、ケーキの図に3等分、5等分の線を引かせてみたら、悩んでしまい、全く書けない子がいる。
書けてもこんな感じだったり・・・
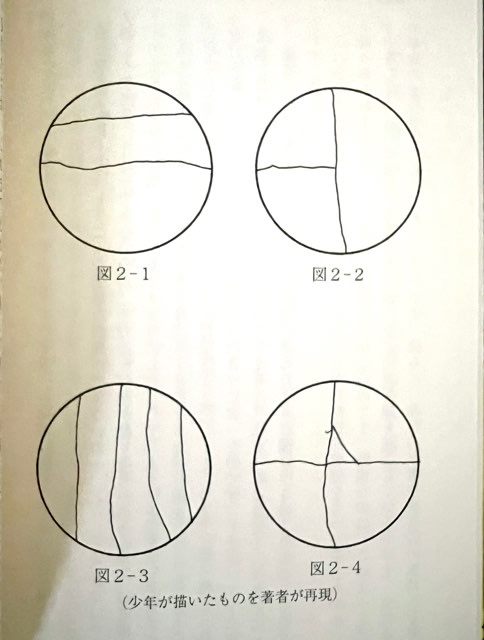
そもそも、等分になっていない

こんな線を引く子がいることに、まずびっくり

少年院の子は、漢字を書くことや計算ができない子がほとんどだそうです。
「後先のことを考える」には、計算能力が必要とのこと。
それがないために「ゲーム機が欲しかったから、人を刺してお金を奪った」となる。
人に借りるとか?、他の選択肢が思いつかない。
いろんな選択肢を思い浮かべるには、先のことを見通す力が必要。
でも、それがない。
「どうしてそんなことをやったのか?」と聞いても、答えられない。
更生のためには、自分のやった非行と向き合うこと。被害者のことも考え、内省すること。自己洞察が必要。
そもそもその力がない。
つまりは「反省」以前の問題なんだそうです。
そういう少年は、見たり聞いたり想像したりする「認知機能」が弱いそうです。
相手が睨んできた・・・と思っても、実際は、相手はそんなつもりは全くなかったり、
俺の悪口を言っていた・・・と思っても、実はブツブツ独り言を言っていただけだったり、
「認知機能」が弱いことで、5感から入った情報が間違っていたり、受け取った情報を間違って整理してしまったり、一部しか受けとれなかったり・・・そういうことが起きてしまう。
それが「不適切な行動」に繋がってしまうと考えられている。
矯正教育を行っても反省ができなかったりもする。
なのに、ひたすら「反省」を求められる。
ただ、これは非行少年だけの話ではないそうです。
人口の十数パーセントは、検査しても病名がつかない「境界認知」にいるとされ、
学校でもクラスに5人くらいの割合でいるそうです。
それぞれがいろんなストレスを抱えていて、場合によっては、非行に走ってしまうケースも。
そういう子たちは、成功体験が乏しいので、自分に自信がない。
なので「いいところをみつけてあげる」「褒めて育てる」「話をよく聞いてあげる」・・・そういう対応が望ましいと思われがちですが、
それだけでは根本的な解決策にはならないのだとか。
問題を先送りしているだけ。また戻ってしまうことが多い・・・と。
この言葉に問題の根深さを感じました。
例えば、勉強できなくてイライラしている子に「走るのは早いよ」と褒めたり、「勉強できなくてイライラしていたんだね」と話を聞いてあげたとしても、勉強ができない事実は変わらない。
小学生はなんとかそれで乗り越えられたとしても、中学生、高校生、社会でもそれでうまくいかなかった場合に、
「誰も褒めてくれない」「誰も話を聞いてはくれない」となってしまうことも。
直接的支援で勉強ができるようにならないと、根本解決にはならない・・・と。
勉強が苦手なら、他の得意なものを探して・・・
これまで、それでいいのでは?とは思っていました。
でも、現実問題もあるし、得意分野を探せといっても、できない場合もある
やはり、その子、その子なんだろうと思いました。
では、どうしたらいいのか?
実際に劇的に変わった非行少年の例もたくさん書かれていました。
親はどう関わればいいのか・・・
発達のことも。
医療少年院でも勤務されていた著者の、現場でのたくさんの事例・・・
とても参考になりました。
我が子が少しでも、もしやと思えるところがあるのなら、もちろんのこと、
そうでなくても、学校や社会に出れば、必ずそういう子と接する機会があるはず。
全ての方に読んでもらいたいと思いました。
理解されない子が少しでもいなくなりますように・・・
いつもありがとうございます。














