昨夕、ニュースを見ていたら、前橋市のホテル女性従業員への
強姦致傷容疑で逮捕された高畑裕太が「不起訴・釈放」となり、
警察署前の報道陣に向けて、大声を張り上げ、謝罪をしていた。
その謝罪ぶりは、文字通り「絶叫謝罪」で、
まるで高校野球の開会式の「選手宣誓」での、
「宣誓! 我々はァ、正々堂々と戦い!…」みたいな調子でもあり、
また、やけくそで、心にもない謝罪を怒鳴っているようにも見えた。
「謝罪」したあと、車に乗り込むまで、
周囲を睨みつける目つきで歩いていた。
(普通は、申し訳なさそうに歩くだろ)
状況に合わない、ふてぶてしい態度だった。
不起訴の理由は、被害者との示談が成立したとのことだが、
驚くほど多額の示談金を積んだのだろ…と思われるよね~
もっとも被害者側も、示談に応じなければ、これが裁判となり、
その間ずっと事件が蒸し返され、心の傷が癒えないかも知れない。
まあ、こういう筋書きになるだろうことは予想できたけど、
それにしても高畑裕太に反省の色は全く見えなかったなぁ。
さて、話はコロッと変わって「不信のとき」のことですが…
石田純一の都知事選がらみで放送中止になったこのドラマ、
先月の23日から、改めて第1話からの再放送がはじまり、
今週の水曜日に、全12話の放送が完了しました。
夫の石黒賢をめぐって、妻の米倉涼子と、
愛人の松下由樹の壮絶な女の争いがテーマだったが、
最後は、石黒賢が進行性の胃がんにかかり、亡くなる。
「夫に天罰が下ったのである」とのナレーションが流れた。
米倉涼子と松下由樹…2人の迫真の演技には惹かれました。
なぜか僕は映画もTVドラマも、こういう傾向のものが好きだ。
前回の「マディソン郡の橋」も、クリント・イーストウッドと、
人妻であるメリル・ストリーブの、まぁいわば、不倫の話である。
いや、あの~別に不倫じゃなくても、恋愛ものが好きなんです。
(…と、あわてて訂正!)
ドラマが終わり、余韻を楽しんでいるとき、
ふと「原作を読んでみようか」と思い立った。
原作は有吉佐和子さんだから、ハズレはないだろう。
僕は、有吉佐和子さんの著作では、
「華岡青洲の妻」
「恍惚の人」
「複合汚染」
という3作しか読んでいないが、
いずれも大学生の頃だったと思う。
で、「不信のとき」が書かれたのは1968(昭和43)年だから、
僕が19歳で、これも僕が大学生だった時の作品だ。
しかし、この小説については、全然知らなかった。
10代後半の頃は、長編小説でも、
2日で1冊を読みきるほど、
大の読書好きだったけれど、
ほとんど外国の小説ばかりだった。
さすがに学生時代は「不倫もの」に関心なかったわけで(笑)
そんなことで今回、ドラマに惹かれたので、
その「不信のとき」を読んでみようか…と、
図書館へ行ったけれど、見当たらなかった。
そこで、書店へ行ったら、新潮文庫の棚にあった。
それは、文庫本で上下2冊だった。案外長編なんだ。
値段は2冊で約1,200円。 文庫なのにいい値段だ。
どうしても読みたい本、というわけでもないし…
そこで、ブック・オフのほうへ行ったら、やはりあった。
上下2冊とも新刊書同様きれいな本だったので購入した。
1冊100円、2冊で消費税込みでも200円ちょっと。
ブック・オフは、ありがたい存在ですね。

この文庫本2冊で合計800ページもある長編です。
昨日買ったばかりでまだ読んでいないが、
パラパラと拾い読みをしていると…
ひとつ、面白いことを発見した。
主人公の一人、愛人のほう…松下由樹が演じた役だが、
この女性の名前が、ドラマでは「野上路子」だった。
ところが本を読んで、驚いたことに、
原作ではこの女性の名前が…
米倉路子…だったのである。
ふつう、ドラマでも原作から名前を変える必要はないが、
妻の米倉涼子の敵となる愛人が「米倉路子」ではねぇ…
視聴者もズッコケるに違いない。
で「野上路子」にしたんでしょうね。
妙なところでひっかかってしまったけれど、
ぼちぼち、この長編小説を読み始めてみよう。






















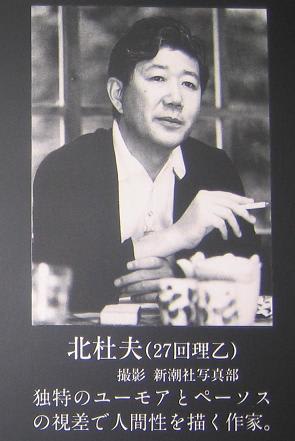
 。
。





