

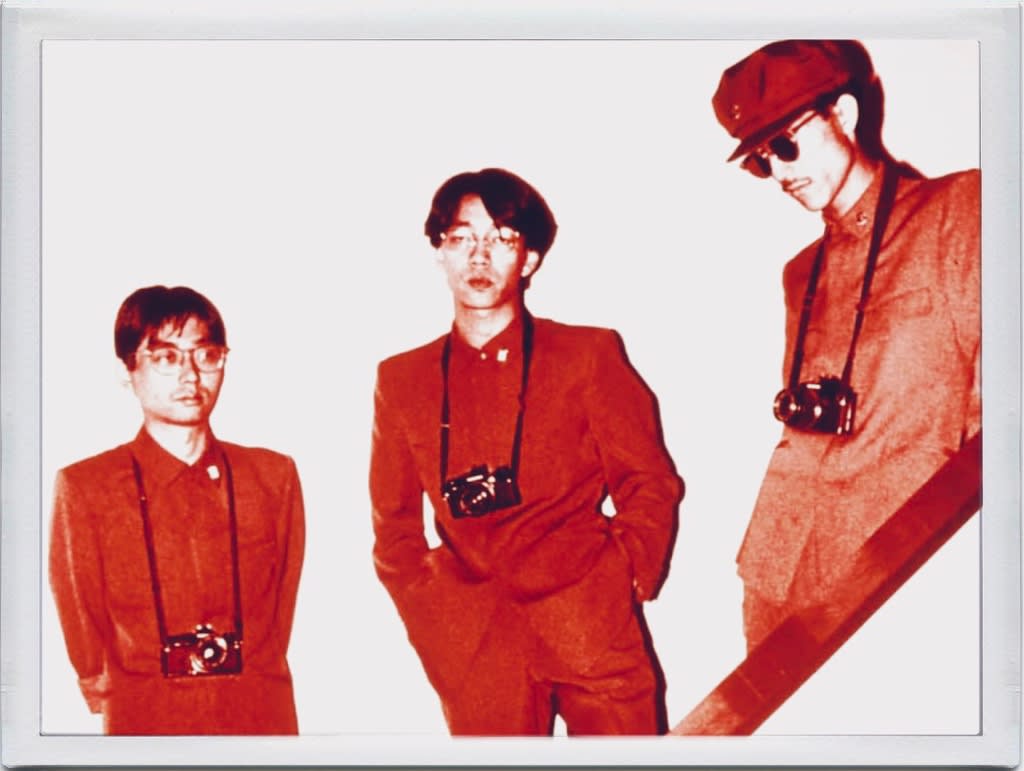
またまた暗記用機能性音楽。今回は元素記号の周期表を覚える歌。
僕が受験生のときは「水平リーベ僕の舟七曲りシップスクラークか」で20番Caまでは覚えた。
この曲でも、受験で要るのは20番までかなと思って作り始めたが、例によって尺が余ったので、21番以降の使いそうな元素も入れている。
途中で番号も必要だと思って5番ホウ素から番号も付け始めたのだが、出だしの「水素エッチー、ヘリウムエッチイー」のフレーズが捨てがたく、やむを得ず1~4番は途中で違う形で入れることにした。
歌っているのは初音ミクと、低い音域でのIA ROCKS。オケは例によってKORG GADGET for iOS。
周期表のうた
作詞作曲:msknst
水素H ヘリウムHe
リチウムLi ベリリウムBe
5番ホウ素B 6番炭素C
7番窒素N 8番酸素O
9番フッ素F 10番ネオンNe
11番ナトリウムNa 12番マグネシウムMg
13番アルミニウムAl 14番ケイ素Si
15番リンP 16番硫黄S
水素H ヘリウムHe
リチウムLi ベリリウムBe
5番ホウ素B 6番炭素C
7番窒素N 8番酸素O
9番フッ素F 10番ネオンNe
11番ナトリウムNa 12番マグネシウムMg
13番アルミニウムAl 14番ケイ素Si
15番リンP 16番硫黄S
水素1番 ヘリウム2番
リチウム3番 ベリリウム4番
17番塩素Cl 18番アルゴンAr
19番カリウムK 20番カルシウムCa
22番チタンTi 25番マンガンMn
26番鉄Fe 29番銅Cu
水素H ヘリウムHe
リチウムLi ベリリウムBe
5番ホウ素B 6番炭素C
7番窒素N 8番酸素O
30番亜鉛Zn 35番臭素Br
47番銀Ag 53番ヨウ素I
78番白金Pb 79番金Au
80番水銀Hg 82番鉛Pb
北海道苫小牧市の実家の前に公園がある。
その公園では、夏休みになると屋台が出て、盆踊り大会みたいなのが行われていた。
なので、夏は毎日夕方から盆踊りの音楽が嫌でも聞こえてきた。
盆踊りの曲は「苫小牧おどり」という。
最近の人はどうかわからないが、苫小牧出身者なら耳にこびりついている曲である。
町内会とか小学校で強制的に踊らされながら、僕は4番の歌詞に一人突っ込みを入れていた。
「“冬はスケート”はわかるが、“夏ならキャンプ”は違うだろ。キャンプ場ないじゃん」
今はアルテンというキャンプ場があるのだが、当時はキャンプできるところがなかった。
それから数十年後、ボーカロイドで実験的音楽を作っていてひらめいた。
あの盆踊りをやればいいじゃん。
あの曲をボカロでやってる人は多分皆無だ。作れば世界初だ。多分。
苫小牧出身者しか知らない曲だ。苫小牧にボカロPが何人いるかって話だ。
懐かしいので、単に作るのが楽しそうでもある。
しかし、資料がなかなか見つからなかった。
実は曲名が「苫小牧おどり」だというのも、このプロジェクトで調査して初めて知った。
子供のころからずっと「苫小牧音頭」だと思っていた。
歌詞は何とか見つかったが、楽譜がない。
YouTubeに少し上がってる動画と記憶を頼りに耳コピするか。
しかし音程が取れない。スケール(調)も分からない。
しかたなく、僕より音感のある奥さんに頼んだら、最初のフレーズが判明。
そこからは記憶でつなげた。
民謡的なものはリズムが難しくて、耳にこびりついてるとはいえピアノロールに落とすのは大変だった。
オケはもっと大変だった。
太鼓はともかく、バックで鳴ってるのは笛とブラスセクションみたいなのか?
歌メロだけでも難しかったのに、あのオケを再現するのは無理だ。
KORG Lisbonのオートアルペジエイターでごまかした。
コード進行はめちゃくちゃである。絶対原曲とは違う。
ドラムはパーカッションをちりばめて、自分なりに祭りっぽくしてみた。
結果、やっぱりテクノっぽくなってしまった。
歌と歌の間の部分は、なんとか原曲っぽいフレーズにしてみた。
ボーカルは、最近導入したIA ROCKSと初音ミクが交互に歌う。
IA ROCKSは、初音ミクにはないパワーを求めて購入したが、VY1と似ててちょっとがっかり。
この曲では両名とも同じものを2トラック重ねる、いわゆるダブルトラッキングを行っている。
ビートルズがよくやってた、同じ人が同じフレーズを2回歌う一人コーラスね。
人が2回歌うと同じフレーズでも絶対微妙に変わるのでコーラスになるのだが、
ボーカロイドの場合、何度歌っても同一だから、単に重ねても意味がない。
色々試した結果、ポルタメントタイミングを少しずらしてコーラス感を出している。
苫小牧おどり
作詞:石本美由起
作曲:和田香苗
編曲:msknst
踊り浴衣は太平洋の
波の模様が一番似合う
わしが港の晴れ姿
今日来な明日来ないつも来な
ぱっと踊りの花が咲く
来な来などっと来な苫小牧
さっと開いた北海道の
ここは要さ扇の要
明日へ広がる苫小牧
今日来な明日来ないつも来な
ぱっと踊りの花が咲く
来な来などっと来な苫小牧
町の自慢は工業地帯
俺の力が親父の汗が
明日の希望を作るのさ
今日来な明日来ないつも来な
ぱっと踊りの花が咲く
来な来などっと来な苫小牧
冬はスケート夏ならキャンプ
街の恋人白鳥娘
逢いにまた来るウトナイ湖
今日来な明日来ないつも来な
ぱっと踊りの花が咲く
来な来などっと来な苫小牧
波の太鼓で景気を付けりゃ
東京飛び立つジェット機さえも
踊り見たさに飛んでくる
今日来な明日来ないつも来な
ぱっと踊りの花が咲く
来な来などっと来な苫小牧















