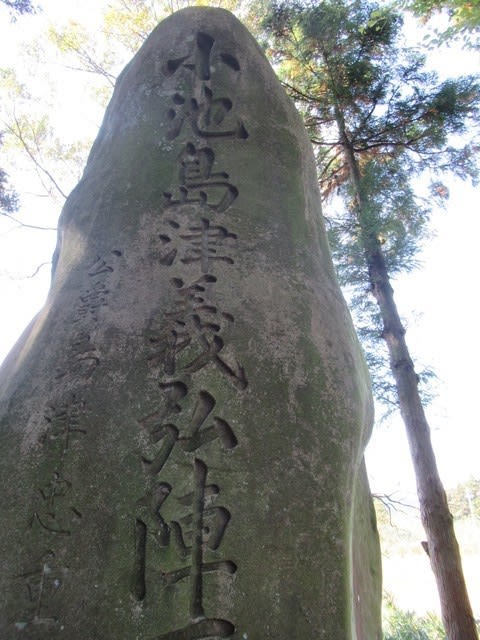篠山城跡や城下町を回る前に腹ごしらえをした。篠山に近づいたあたりで、助手席に座った同行のT氏がスマホで店の検索を始めた。
歴史美術館の斜交いにあった店に決め、駐車場は向かい側にコインパーキングがあったのでそこに停めた。

料理旅館とのことだが、外装はどこかの高原にあるロッジ風。しかし、入ってみると玄関脇の小さな間取りの応接室らしき部屋には瀟洒なテーブルとイスが置いてあった。和服を着るか、正装でないと絵にならない感じだ。

食事処は5卓ぐらいで満席だったのでカメラは控えたが、落ち着いた和風モダンな感じか。どじょうと思われるメタルのオブジェの置かれた籐のムシロの下は井戸のようだ。

昼食メニューはセット物が5~6種類あったので、ステーキ丼を選んだ。地元産なら丹波牛か?

山椒味噌仕立てで、山の芋の角切りが散らしてある。蕎麦にしようか迷ったが、こちらで正解だった。
旅館なので宿泊も可能だが、その場合の夕食にはボタン鍋を選びたいところだ。

帰宅して公式ホームページをのぞいて見たが、落ち着いた和風の部屋の雰囲気がよさそうが。家具や調度品を見るだけでも楽しそうだ。
歴史美術館の斜交いにあった店に決め、駐車場は向かい側にコインパーキングがあったのでそこに停めた。

料理旅館とのことだが、外装はどこかの高原にあるロッジ風。しかし、入ってみると玄関脇の小さな間取りの応接室らしき部屋には瀟洒なテーブルとイスが置いてあった。和服を着るか、正装でないと絵にならない感じだ。

食事処は5卓ぐらいで満席だったのでカメラは控えたが、落ち着いた和風モダンな感じか。どじょうと思われるメタルのオブジェの置かれた籐のムシロの下は井戸のようだ。

昼食メニューはセット物が5~6種類あったので、ステーキ丼を選んだ。地元産なら丹波牛か?

山椒味噌仕立てで、山の芋の角切りが散らしてある。蕎麦にしようか迷ったが、こちらで正解だった。
旅館なので宿泊も可能だが、その場合の夕食にはボタン鍋を選びたいところだ。

帰宅して公式ホームページをのぞいて見たが、落ち着いた和風の部屋の雰囲気がよさそうが。家具や調度品を見るだけでも楽しそうだ。