手はただ動くのではなく、いつも奥に心が控えていて、これがものを創らせたり、働きに悦びを与えたり、また道徳を守らせたりするのであります。そうしてこれこそは品物に美しい性質を与える原因であると思われます。それ故手仕事は一面に心の仕事だと申してよいでありましょう。
柳宗悦「手仕事の日本」より
柳宗悦「手仕事の日本」より
-----
Labor Dayで休日なので家にいる(アサインメントたくさん)。
上のは、いい文章だなぁと思ったのでメモ。
今、私たちのグループでは、チームのアイデンティティをかため、文章やデザイン、プロダクトとしてアウトプットしていく作業が行われており、それゆえ「自分たちがやっていることってなんだろう」と考えざるをえない日々が続いています。
自分のチームのアイデンティティを思うとき、まっさきに思うのは「手で考える」ということ。私たちの誰もが、誰かの教えやレクチャーでは学ばず、常に自分で何かをつくろうとし、行き詰まり、壁にあたり、でもそれをどうにかこうにか乗り越え、カタチにすることで学んでいる、そんな集団なのです。
そのとき一番頼りになるのが、自分たちの手。
昔、河井寛次郎さんが言った「手考足思」という言葉が好きだったけれど、あの頃よりも今はもっとビビッドにこの言葉をとらえることができている気がするなぁ。「手を動かして考え、自分の足で歩きながら思いをめぐらせる」そのとき頭でっかちに考えたことなんて、二の次、三の次なのだ。たぶん。
実際に動くこと、身体のなかでも実際に動かせるところから、ものづくりって始まるのだと今はつよく思う。手から生まれたもの、ひとの手仕事をリスペクトしたい気持ちはふだんから持っているけれど、冒頭のような文章を読み直すと気持ちも新しくなるもの。
-----
あぁ、こんな現実逃避のブログ書いてないで、さっさとやることやらねばー!










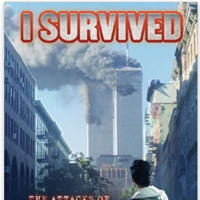



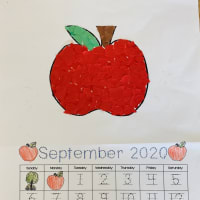











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます