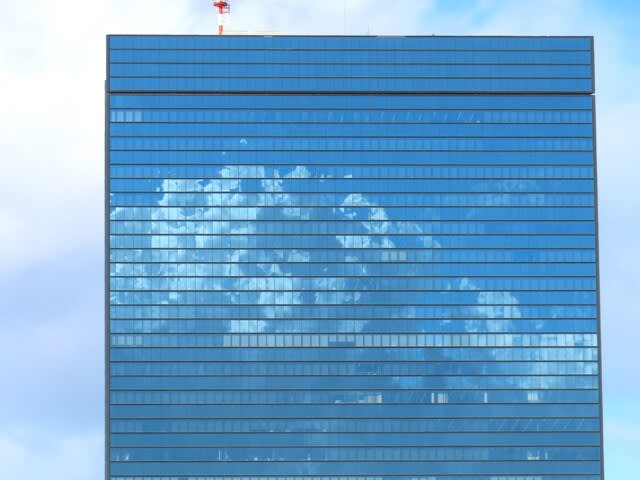毎日新聞の朝刊に「まいにち言葉」というコラムがあり、間違い易い言葉などが記載されていて楽しみにしているのですが、先日このコラムに「完璧」という言葉が載っていました。
確かに「完璧」という漢字を見れば、「かんぺき」と呼べるのですが、逆に「かんぺき」を漢字で書けと言われれば、「完璧」という漢字は浮かんでこずに「完壁」と書いてしまう人が多いのではないでしょうか。
「完璧」の璧は壁(かべ)ではありませんので、注意が必要です。
確かに「璧」も「壁」も共に「へき」あるいは「ぺき」と呼びます。
共通する『辟』の下が、『玉』か『土』かの違いだけなのですが、どのように違うのか気になり調べてみました。
以下、主に<風船あられの漢字ブログ>を参照させていただきましたが、結構長いのでポイントだけを記します。
◆基本の漢字は『辟』(部首は、「辛(しん)」)で、読み方は『ヘキ』か『ヒ』、その意味は元々は<刑罰>ですが、これから色々に転じて<避ける、横にさける、腰を切る、平伏する、丸く切る>など色々あります。
尚、この『辟』という漢字は常用漢字から外れていますので、余り使用されません。
この『辟』を使う言葉で、良く使われるには「辟易」ですが、この元々の意味は<道をあけて場所をかえる>なのですが、これから転じて、現在では、
1 ひどく迷惑して、うんざりすること。嫌気がさすこと。閉口すること。
2 相手の勢いに圧倒されてしりごみすること。たじろぐこと。
という意味で使われることが多いです。
◆『璧(ヘキ)』(部首は「玉(たま)」)で、漢音が『ヘキ』、訓読みは常用外に『璧(たま)』があります。
平たい宝石を表す形声文字で、意味は<宝石、すぐれたもの>です。
傷の無い宝石を「完璧(カンペキ)」、一対の宝石で二つ共に優れたものを「双璧(ソウヘキ)」といいます。
※ 形成文字:意味を表す文字と,音を表す文字を組みあわせてつくった文字を言います。
判りやすい例は、「銅」「胴」「洞」など。右側がわの「同」が音(どう)を表し,左側がわの「金」や「月(肉)」「(水)」がそれぞれ金属きんぞく・身体・水に関係かんけいがあるという意味を表している(<キッズネット>より)
◆『壁(ヘキ)』(漢字の部首は「土」)で、漢音が『ヘキ』、訓読みは『かべ』です。
壁の映像を示す形声文字で、意味は<壁(かべ)、砦(とりで)、壁の様な崖(がけ)>です
壁に描いた画を「壁画(へきが)」、船着き場の壁を「岸壁(がんぺき)」、壁(かべ)の外側を「外壁(ガイヘキ)」、壁用の紙を「壁紙(かべがみ)」といいます。
◆なお、「辟」から生まれた形成文字は結構多くて、「壁」「璧」以外にも結構ありますが、主なものは、
避(ひ):災いや難儀をこうむらないように、わきによける。さける。「避暑・避難・避妊・回避・忌避・待避・退避・逃避・不可避」
臂(ひ):
肩から手首までの部分。腕。「猿臂・短臂・断臂・半臂・三面六臂」
癖(へき・くせ):
①かたよった習性。くせ。「悪癖・奇癖・潔癖・酒癖・習癖・書癖・性癖・盗癖・病癖」
②くせ。 「口癖・酒癖・手癖・難癖 (なんくせ) 」
僻(へき・ひがむ):
①本筋からずれて、正しくない。一方に偏する。「僻見・僻説・僻論」
②場所が中央から離れている。「僻遠・僻陬 (へきすう) ・僻村・僻地」
[難読]の言葉としては、僻耳 (ひがみみ) ・僻目 (ひがめ)
その他にも、擘(はく=おやゆび)、襞(へき・ひだ・しわ)、躄(へき・いざる =足の不自由なこと)などと色々あるようです。(まさ)
(今日の夕食)

湯豆腐/刺身/酢豚

刺身 美味しそうだったのではり込みました

酢豚 歯が悪かったので久しぶりです