近代日本における哲学は、西田幾多郎氏に始まると言われています。そして、哲学者の西田は、「哲学は、宗教を語ることによって帰結する」と言っています。
つまり、哲学にとって「宗教」は、帰着点だというのです。ただし、ここでいう宗教とは、現代人が考えている宗派的宗教とは異なるもので、宗教心とは、“信仰”とか“悟りへの道”いう言葉に置き換えた方が分かりやすいのかも知れません。
悟りとは、辞書を引くと迷いの世界を超えて修行し、真理を体得することのようです。この修業で思い出すのは、比叡山で行なう“千日回峰行”です。
1日に30キロを6時間で歩く荒行は、1~3年目は年間100日間、4~5年目は、200日間の修業となる。6年目は約60キの工程を100日間歩き続ける。雨の日も荒らしの日も、夜中に寺を出て比叡山を歩き回り、午前中に寺に戻る荒行で、しかも歩く道は山道です。
死出の旅を意味する白装束に身をくるみ、迫りくるあらゆる限界に堪え、ひたすらに歩き続ける荒行である。
この荒行をテレビで見ていたのですが最後には、弟子に抱えられての荒行で、生死をさまよっているように感じました。こうした荒行を乗り越えて僧侶は、悟りを開くことが出来たのでしょう。
西田は、家族の死が続く中で『善の研究』なる本を執筆し、その中で純粋経験(自覚的事実)や直観・直覚を重視しています。自己の根底には、意識的自己(自我)とこれを超える自覚的事実(真の自己)があるようです。
人生、喜怒哀楽、艱難辛苦、波乱万丈のなかで己を知ること、悟りに近づこうとする修行は極めて大切なことだと思っています。
自分は悟りを開けるような器ではないが、本当の自己に出会うこと、真のありように気づくことができればと常日頃から思っています。
また西田は、想像力を活かし人間の壁を超えた“霊性”の目覚めがなければならならと言っています。この霊性には、目には見えない神を認識するはたらきあるそうです。
大自然と共に生きるアイヌ民族は、動植物、山や湖などの自然と自然現象のそれぞれに「神(カムイ)」が宿るとして敬い、人間も自然の一部であると考えていました。大自然と共生し多くの神に祈り感謝し、生かされていることを体得していたのでしょう。
「十勝の活性化を考える会」会長
注) 信仰
信仰のことを仏教においては「信心(しんじん)」と呼ぶことが一般的である。
このように、この語は多くの場合宗教的概念、例えば神、教義などを信じることに対して用いる。 広辞苑によれば、信仰は一般に、畏怖よりも何らかの親和の気持ちが根源にあるとしている。
「宗教」という語が、組織や制度までも含めて指す包括的な語であるのに対し、「信仰」や「信心」は人(あるいは人々)の意識に焦点をあてた語である。また、何らかの対象を絶対のものと信じて、疑わないことを指すこともある。
(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















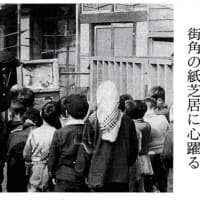


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます