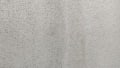北上する飛行機で津軽海峡を見わたした。
本州の青森県竜飛岬の上空。その先には北海道の渡島半島南端が見える。

この辺りは太宰治の小説に出てくる。
さらに数分後、下北半島があらわれる。
恐山は緑がない。
そして下北半島の突端の向こうには函館がのぞく。

その距離わずかである。
ここは国際海峡となっていて、断りなくだれでも通れる。
ロシアや中国の艦隊も通過できる。
日本の生活圏のすぐ目の前。
当然、日本政府やたぶん米軍も監視している。
そして、函館山と市内がきれいに見えてきた。
魚介のおいしい観光都市でもある。平和な日本。

これだけ狭いので、日本の領海とすることはできるらしい。
ただし政府は公海と位置付けている。
その経緯はwikipediaにのっている。
「公海部分は核兵器を搭載した外国の軍艦を含め自由に通過することができる[注釈 5]。」
「これについて日本政府は「重要海峡での自由通航促進のため」と説明しているが、複数の元外務事務次官から得た証言として共同通信社が2009年6月21日に配信した記事では、1977年施行の領海法の立法作業に当たり、外務省は宗谷、津軽、大隅、対馬海峡東水道、同西水道の計5海峡の扱いを協議し、1960年の日米安保条約改定時に密約を交わし、核兵器を積んだ軍艦の領海通過を黙認してきた経緯から、領海幅を12カイリに変更しても米国政府は核持ち込みを断行すると予測した。そこで領海幅を3カイリのままとして海峡内に公海部分を残すことを考案し、核艦船が5海峡を通過する際は公海部分を通ることとし「領海外のため日本と関係ない」と国会答弁できるようにした、と報じている[5]。」
こういう事態にならないことを祈るのみである。
ではまた、ぶらり。