さわめのみなさんがお出で下さいました。みんなで我が家のお庭の様子を見て歩きました。
 スイセン
スイセン
 レンギョウ
レンギョウ
一番最初に咲いた花は白や紫の花だったのですが、ようやく黄色のスイセンやレンギョウも咲き始めました。

池の水の取り入れ口にたくさん咲いています。名前がわかりません。どなたかご存じの方はお知らせ下さい。 お願いします!




他にも、ショウジョウバカマ、カタバミソウ、ヒマラヤユキノシタ、キクザキイチゲなどが咲いています。山野草系統の花はやはり白や紫の色の花が多いようです。
勿論、洋花のチューリップなどは赤なども咲いています。

今日から1株198円で買ってきたハーブの収穫が始まりました。



私が好きなのは右上の「ロケット」です。最初、ごまの味がし、後にほろ苦さを感じます。なかなかに楽しめる味です。

チャービル(右下)やゴールデンレモンタイム(左上)、レモンタイム(左下)もサラダにも美味しいですが、肉料理には欠かせないものになってきました。

ドレッシングは先日、えっちゃんが作って下さいました。あれから5日ほどたち、オリーブオイルや酢に漬けたハーブやニンニク、タカノツメなどの味や香りがほどよくにじみ出し、良い具合になっています。今度は自分の好みのものを作るよう頑張ってみます。えっちゃんご教示を有り難うございました。
まだ6~7種類のハーブが次々と育っています。今はまだ少しの収穫ですが、これからはたくさん収穫できそうで、もしかしたら野菜は買わなくても良いという事態になるかもしれません。
・・・ そういうことは無いですよね 

























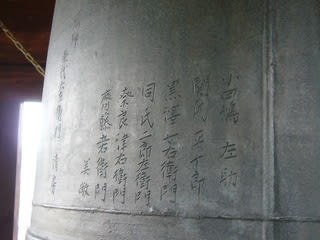






 カモシカの糞です・・・・
カモシカの糞です・・・・ バッカイ沢の水源・・・・
バッカイ沢の水源・・・・





























 キクザキイチゲ
キクザキイチゲ 
 イチリンソウ
イチリンソウ 


 3/28 購入時
3/28 購入時





