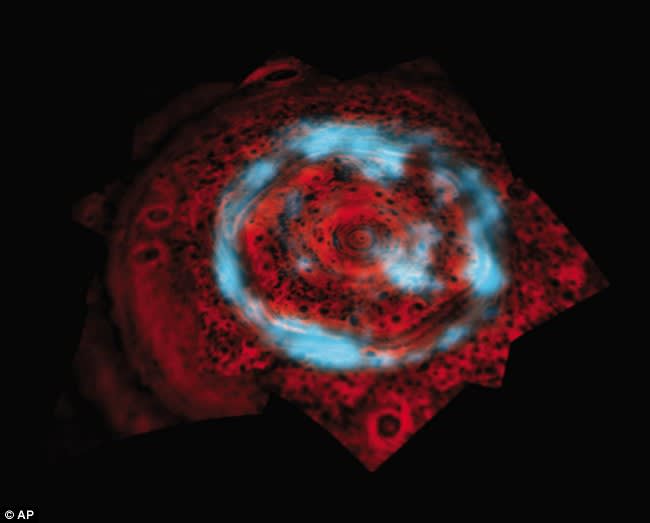放蕩息子の譬(たと)え!!
聖書には、ルカ伝第15章11章から32章にかけて、記されている。内容は概ね下記と同様であるが、宝瓶宮福音書から引用転記した。聖書は御各位ご確認頂きたい。ずっとこの方が分かり易いからである。
<今度は、シロクマとかくれんぼするカメラマン:記事に無関係>
言いたいのは、こうである。
放蕩息子というのは、人間のことである。父とは、主なる方である。万軍のエホバと言っても良いし、ヤハウェー、でも良い。聖書に馴染みのない方であれば、大仏様で良い。正確に言えば、内なる生命である。真我であり、人間を存在せしめている根源のパワーである。
この事は、親鸞聖人の悪人正気説に相通ずる。あの『善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや・・・!』である。
それより、この方がずっと分かり易い。放蕩の報いは、当然、因果律により自ら背負わなくてはならない。本心に立ち返ると言うことは、そう言うことである。雇い人の身に自らを置こうと発心する様を言う。しかし、父なる方はそうではない。やはり、可愛い息子である。死んだと憂えた息子である。諸手を挙げて迎える存在が、父であり、母である。それが『愛』である。
その事は、人間の内なる生命の本質であって、そうではないモノは、本質ではないと言うことである。だから、夢疑う事なかれと訴えかける。人間は、過ち多き者である。しかしながら、自らを愛おしむ事を忘れてはならない。又、その心は、父の心であって、息子を裁かない。愛は常にいかなる場合にも、裁くことをしない。常に受け入れるのみである。
「聞く耳、さとる心ある者は、このたとえの意味が分かるであろう。」
分かる。
分かろうと思う。
分かる人間でありたい。!
《主と弟子たちはガリラヤ地方の町々村々通って旅して、テベリヤに来た。そこで少数のキリストの名を愛する者に逢った。イエスは彼らに内なる生命について多くのことを語ったが、民衆がやって来たので、二つの譬(たとえ)話をした。
「ある金持ちに二人の息子があった。弟が家庭生活に飽きが来て言う。『お父さん、どうか財産を分けて、わたしの頂く分を下さいませんか。外国に行って、自分の運命を開きたいと思います。』父は望みどおりにしたので、青年は外国に行った。
彼は放蕩者で、間もなく罪に身をくずして、財産をみな使い果した。
彼にはもう何もすることがないので、畠に行って豚飼いの仕事を見つけた。飢えても誰も食べるものを与える者がないので、豚に食べさせていたいなご豆を食 べた。幾日かたってから、彼は本心に立ちかえって言つた、『父は金持ちで、雇人がありあまるほど食べているのに、息子のわたしは畠で豚と一緒で、今にも飢え 死にしそうだ。わたしは再び息子として迎えられることを望まない。でもすぐ立って父の家に行き、自分のわがままを白状しよう。そして父に言おう、お父さ ん、もどって参りました。わたしは放蕩者です。財産は、罪を犯してみんななくしました。わたしはあなたの息子と呼ぱれる資格はありません。わたしは今更皇 子として迎えられようとは思いません。どうか雇人のなかに入れて、嵐、を避けて十分に食べさせて下さい。』
そして彼は立って父の家を訪ねた。彼が来ると母親は遠く離れているのに彼を見つけた。(母心は放蕩息子の一番さきのかすかなあこがれを感じ得る。)
父が来た。そして両親は手に手をとり、道を降りて来て子供を迎えて、大喜びであった。
子供は一生懸命に憐れみを乞い、雇人の身分にしてほしいと願った。しかし愛は大きく、この願いなど耳に入らなかった。
門は大きく開いた。彼は心から母に歓迎され、心から父に歓迎された。
父は雇人を呼んで、彼のために一番立派な着物、足には取っておきのサンダル、手には一番よい純金の指環を持って来るように命じた。それから、父は雇人に 言った、『お前たち、行って肥えた仔牛をほふり、祝宴を用意するんだ、おれたちはうれしいんだよ。死んだと思ったわが息子がここに生きている。失ったと 思った宝が見つかったのだ。』
祝宴はすぐととのえられ、一同が陽気になっていたところに、遥か遠くに働いていて、弟が帰ってことをを知らなかった長男が戻って来た。彼はこの陽気なざわめきを聞くや、怒って家に入ろうとしない。
父母はともに弟息子のわがままや道楽を見のがしてくれと、涙ながらに兄息子にたのんだ。しかし、彼は承知しないで言う、『見よ、わたしは何年も家に居っ て、毎日働き、大変無理な命令にも一度もそむいたことがなかった。それなのに、あなたがたはわたしのために、子山羊一匹ほふったことがないし、友人と簡単 なもてなしもさせてもくれなかった。しかし、あなたの息子、家を出て罪を犯し、おとうさんの財産半分を食いつぶした放蕩者が、何もすることができないの で、おめおめ帰って釆れば、そのために肥えた仔牛をほふって、大変な祝宴をするんだ。』
父は言う、『わが子よ、わたしのものは全部お前のものだ。お前はいつもわれわれと一緒におって、われわれの喜ぴなんだ。しかし、われわれにとって至って 親しい愛するお前の弟が、死んだと思っていたのに、無事に帰って来たのだから、喜ぶのは当然のことだ。彼は放蕩者で、浮気な遊び女や盗人と一緒であった が、やっぱりお前の弟、われわれの息子だよ。』」
それから、イエスは人々に聞こえるように言った、「聞く耳、さとる心ある者は、このたとえの意味が分かるであろう。」
それから、イエスと十二人はカペルナウムに来た。<宝瓶宮福音書より>》