
大好きな特殊奏法についてです。ほんとは替え指だとかハーフタンギング、ダブルタンギングだとか地味ながら重要な技もあるのですが、地味なのはすっ飛ばします。だいたいはいつの間にかできるようになってますから。
1)グロウル。唸る奏法です。これは文字どおりサックスを吹きながらウーと唸ります。すると、あら不思議、割れかかったような、歪んだような音色になります。テナーでは常套手段で、チェッカーズの藤井尚之もこの音色でした。むしろ有名すぎて、何も手を加えないクリーントーンではなく、こちらの音色をテナーの普通の音色と思っている方もいるかもしれません。
でも実は、これも奥が深くて、音程をつけて唸る(唄う)手法があり、さらにそれをサックスの出音とユニゾンにしたりハモリにしたりとバリエーションがあります。さらに、うがいをするように喉を鳴らすまで行くとフラッタータンギングという技になります。グロウルを突き詰めようとがんばっていた頃、サックス吹きなのにスタジオを出たら喉が嗄れていました。
2)フラジオ。通常の運指ではハイFかF#までしか上は出ません。でも特殊な指使いで、その上を出すことが可能になります。その原理は通常の運指で出る音の、その倍音(ハーモニクス)成分のみを実際の音として残すことです。なんだか難しそうですが、初心者の方が、思い切り力を込めて吹いたり、間違いでサイドキーに触れてしまった時に、ピーという甲高い音が出ることがままあります。要はあれを飼いならすわけです。
いちおう自分はダブルハイDまでは飼いならせました。ただ、実際の現場ではそこまでは使えてません。せいぜいハイAまででしょうか。複雑な運指もさることながら、どんどん音色がやせ細ってしまって、ロックでは周囲の音に埋もれてしまいます。ただ外国のサックス吹きのCDを聞くと、とても太いフラジオを出していることがあって、修行が必要だなと思っています。
3)サブトーン。ロックではなかなか使い道がなく、自分も高い音域までできるようになったのは最近です。吹き込んだ息の一部のみを管を鳴らすために使い、ほかは息として逃がすものです。”鳴らさない”奏法とでも言うべきでしょうか。特に音の立ち上がりや消え際に目立つシューという吐息の音が特徴です。
ちょっと前に触れた裕次郎「夜霧」のイントロが有名ですが、けっこうジャズではスタンダードな音色です。あの「テイク・ファイブ」のポール・デスモンドの音色も実はサブトーンです。息と実音のブレンド具合もいろいろで、目立つものと目立たないものがあるのです。コツはマウスピースの気持ち斜め上から息を吹き込みつつ、その息の圧を一定に保つことでしょうか。
4)フリークトーン。上記の集大成のような奏法ですが、こちらは長くなりそうなのでまたの機会に。
よもやま話第一回で、サックスを史上最強のアンプラグド・ノイズマシーンと書きました。円錐管(開管)かつ、くねった管体からサックスは複雑でやんちゃな倍音構成を持っています。クラシックや吹奏楽では、それをがっちり固めたマウスピースと均一な奏法によってアンサンブル楽器へと捕縛するわけです。しかし、フリーまで含めたジャズや、R&B/ロックは、その緊縛を解き放ちました。アンプやエフェクターに頼らず、馬鹿でかく多彩な音色を出せるサックスは面白い楽器だなと思っています。
1)グロウル。唸る奏法です。これは文字どおりサックスを吹きながらウーと唸ります。すると、あら不思議、割れかかったような、歪んだような音色になります。テナーでは常套手段で、チェッカーズの藤井尚之もこの音色でした。むしろ有名すぎて、何も手を加えないクリーントーンではなく、こちらの音色をテナーの普通の音色と思っている方もいるかもしれません。
でも実は、これも奥が深くて、音程をつけて唸る(唄う)手法があり、さらにそれをサックスの出音とユニゾンにしたりハモリにしたりとバリエーションがあります。さらに、うがいをするように喉を鳴らすまで行くとフラッタータンギングという技になります。グロウルを突き詰めようとがんばっていた頃、サックス吹きなのにスタジオを出たら喉が嗄れていました。
2)フラジオ。通常の運指ではハイFかF#までしか上は出ません。でも特殊な指使いで、その上を出すことが可能になります。その原理は通常の運指で出る音の、その倍音(ハーモニクス)成分のみを実際の音として残すことです。なんだか難しそうですが、初心者の方が、思い切り力を込めて吹いたり、間違いでサイドキーに触れてしまった時に、ピーという甲高い音が出ることがままあります。要はあれを飼いならすわけです。
いちおう自分はダブルハイDまでは飼いならせました。ただ、実際の現場ではそこまでは使えてません。せいぜいハイAまででしょうか。複雑な運指もさることながら、どんどん音色がやせ細ってしまって、ロックでは周囲の音に埋もれてしまいます。ただ外国のサックス吹きのCDを聞くと、とても太いフラジオを出していることがあって、修行が必要だなと思っています。
3)サブトーン。ロックではなかなか使い道がなく、自分も高い音域までできるようになったのは最近です。吹き込んだ息の一部のみを管を鳴らすために使い、ほかは息として逃がすものです。”鳴らさない”奏法とでも言うべきでしょうか。特に音の立ち上がりや消え際に目立つシューという吐息の音が特徴です。
ちょっと前に触れた裕次郎「夜霧」のイントロが有名ですが、けっこうジャズではスタンダードな音色です。あの「テイク・ファイブ」のポール・デスモンドの音色も実はサブトーンです。息と実音のブレンド具合もいろいろで、目立つものと目立たないものがあるのです。コツはマウスピースの気持ち斜め上から息を吹き込みつつ、その息の圧を一定に保つことでしょうか。
4)フリークトーン。上記の集大成のような奏法ですが、こちらは長くなりそうなのでまたの機会に。
よもやま話第一回で、サックスを史上最強のアンプラグド・ノイズマシーンと書きました。円錐管(開管)かつ、くねった管体からサックスは複雑でやんちゃな倍音構成を持っています。クラシックや吹奏楽では、それをがっちり固めたマウスピースと均一な奏法によってアンサンブル楽器へと捕縛するわけです。しかし、フリーまで含めたジャズや、R&B/ロックは、その緊縛を解き放ちました。アンプやエフェクターに頼らず、馬鹿でかく多彩な音色を出せるサックスは面白い楽器だなと思っています。

















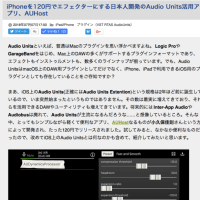

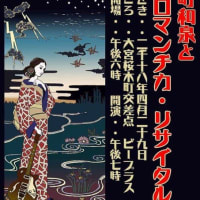
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます