ターキッシュ・クラリネットの微分音について、あらためて研究中。ウードみたいなフレットレスや、サズみたいな移動式フレットに対し、クラリネットはどう対応するのが正解なのか、結構謎です。
ざっと思いつくのは次の方法です。
1) ピッチベンド:口を緩める。
2) 半指孔:指孔を微妙にふさぐ。
3) 変え指:通常の運指に加え、さらに遠くの指孔をふさぐ。
クラリネット奏者のBoja Kraguljさんがノースカロライナ大学に提出した論文『The Turkish Clarinet : Its History, an Exemplification of its Practice by Serkan Çağri, and a Single Case Study.』https://libres.uncg.edu/ir/listing.aspx?id=7442 では、トルコを代表するターキッシュ・クラリネット奏者、セルカン・チャウリに師事した記録が読めます。
それによると、1) 口でコントロールするのが王道のよう。しかしながら、それをフレージングの中で行うのは、とてもとても難しい。
セルカン・チャウリは修士号を持つほど古典音楽に通じているので、9分音のためには口でのコントロールが必須なのでしょう。
習得不可能なほどの、相当な修練と、耳の良さが必須。いさぎよく諦め、3)変え指での微分音を研究中。
AとCのちょうど真ん中って西洋音階では存在しないですが、Bハーフフラットがそれに当たることに気づいて、システマティックだなと、魅力に取り憑かれています。


















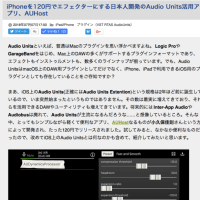

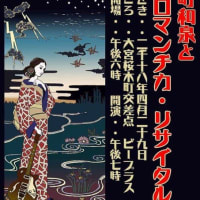
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます