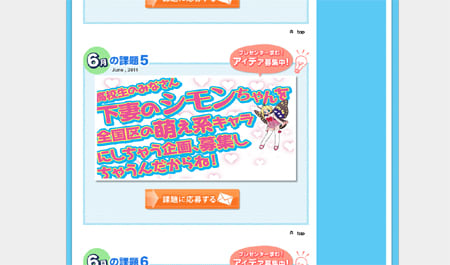東京ビッグサイトでGOOD DESIGN EXPO 2011を見た。

普通の展示会と異なるのは
グッドデザイン賞の審査プレゼン会場をそのまま公開しているため
過剰なまでの商品PRやデモがなく、
コンパニオンのお姉ちゃんもいないこと。
プレゼンは商品そのものと簡単な説明文がつく程度で
使用感などはほぼわからない。
本当に見た目で勝負、ということになっている。
見たかった「個人住宅」だったのだが
さすがに現物展示はできないので
パネルと模型、小型モニターを仕込む程度のプレゼンが延々と続く。
中にはiPadを組み込んでいるところもあり
色々な「プレゼン手法」を見ただけでも非常に参考になった。
住宅に関して言えば
省エネ、エコが大きな流れとしてあり、
その上で大手ハウスメーカー系はライフスタイル別、
特に主婦、子育てをテーマにした企画住宅を出し、
地域ビルダーであれば木材の地産地消費、
工務店、設計事務所系は周辺環境も含めた
コミュニティのある空間づくり
などが提案のポイントになっていた。
MISAWAとHABITAが結構力を入れていた印象がある。
個人的には大阪の豊崎長屋のリフォームプロジェクトが面白かった。
大正時代につくられた長屋4棟15戸を耐震補強と住戸改修を加えて
再生し、借家として継続利用しているもの。
新規開発の住宅地や大手のマンションプロジェクトのような
絵に描いた餅的なコミュニティではなく
地に足がついたリアルな「近所付き合い」が目に見えるよう良い。
リフォームであることがうまく活かされた例であろう。


その他省エネの流れから日本家屋が見直される傾向が目立っており
半数近くが和風住宅、あるいは和風の要素を取り込んでいたように思う。
性能、デザインの両面から日本家屋の長所を活かすということは
以前からあったことだが、長期優良住宅やLCC
そして東日本大震災によって一層顕著になったようだ。
住宅に限らず、日本とは何か、日本的なものとは何かということが
商品生産の現場でも大きなテーマになっており
今後ますます、日本的なものをコンセプトにした商品が
増えていくことは間違いない。
会場には震災からの復興を目的にした
「東北茨城デザインプロモーション」というコーナーが設けられていた。

こうして考えると「東北」は被災地というとらえ方だけでなく
「日本的なモノ」「日本的なモノづくり」の発信地として
再度見直す必要があるのかもしれない。
日本デザインセンターは復興支援デザインセンターを設けて
今後3年間東北地域の企業活動を支援していくそうだ。
とにかく数が多く、全てを見ている時間はとれなかったのが残念。
それにしても「グッドデザイン賞」とはいえ
受賞した商品が売れている(または売れる)かどうかは全く別問題だ。
あらゆる分野で商品の寿命が短くなり、開発のスピードが求められる中で
デザインを考え、定着させていくのがいかに大変なことか、あらためて実感した。
差別化のためにはデザインは重要だ。
とはいえ、これだけ大量の商品を目の前にすると
デザインもひたすら消費されるだけなのか、という思いがよぎる。
「グッドデザイン」がただの「グッズデザイン」にならないよう、祈りたい。