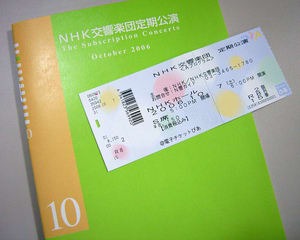久しぶりに神保町を散策する。
この辺の古本屋さんが普通の日曜にも営業していると
行きやすいんだけど。
たまに行くから面白いのかな、とも思う。
折角なので目標設定をする。
書籍:①吉増剛造さんの詩集(80年代~それ以前)
(『青空』『草書で書かれた川』『頭脳の塔』とか・・・)
②自分には全く縁のない豪華でまじめな写真集
(盆栽写真集とか、バクテリアの顕微鏡写真集とか・・・)
③ひし美ゆり子さん(アンヌ)の写真集
レコード:④武満さんのアンソロジー「ミニアチュール」シリーズ 2と4
特に下調べもせずにいったので、どこのお店に何があるのやらも
わからず、通りに沿って順番に覗いていった。
う~ん、古本屋さん独特の、あのほこりくさい空気が
なんともいえず、心地いい!
しかし、つくづく思うのだけれど、あらゆる情報が
ネットを通じて瞬時に世界中に広がっていく現代にあって
これだけの知的財産が埋もれている(?)というのも
実に奇妙な感慨を受ける。
図書館のように体系化されて保存・公開されるのではなく
それぞれがテーマを持つ、独立した小さな「書店」として
密集している。
秋葉原と似て非なるところは
アキバが時代の流れに乗って
急速にスクラップ・アンド・ビルドを始めている一方で
ここは、ひたすら時間を蓄積していることにある。
まるで降り積もるホコリのように。
(パソコンにホコリは大敵だ・・・)
訪問者は事前に何らかの情報を得ていなければ
ただひたすらランダムにその中をさまよい続ける。
ま、それが楽しくもあるのだけれど。
googleが世界中の図書館の本をスキャンして
文字検索できるようにする、と豪語しているが
ぜひ、神保町の古本も仲間に入れてほしいものだ。
なんてつまらないことを考えながら、目標はどうなったかというと・・・
①吉増剛造さん/目標物ナシ(数年前に出た新し目のものは1冊発見)
②まじめな写真集/特にビットの立つものはナシ(無念!)
③ひし美ゆり子/『ひし美ゆり子写真集 YURIKO 1967-1973』発見!
(1万円!)。
※う~ん、先日再販された新装版(一部写真が差し変わってる)を
買っちゃったんだよね~と悩みつつ、見送り(残念!)。
結局、購入したのは
④武満さんのレコード/「ミニアチュール」第4集 1,200円
(さくら通り沿いのササキレコード社にて)
「ミニアチュール」第2集 2,500円
(三省堂書店 自遊時間にて)
※これで念願のシリーズ全5枚がやっと揃った!
想定外でつい・・・
月刊「井川遥」袋入り、特別版 500円
(さくら通りのワゴンセールにて)
※昔、発売日に買っていたのだが、袋も開けずに
井川ファンの友人に譲ってしまっていたので・・・
谷川俊太郎/『定義』 500円
『コカ・コーラ レッスン』 600円
(意味不明なレトロ雑貨店にて。店名忘れた。)
※人に貸したっきり戻ってこなかったので
取り戻すつもりで買ってしまった・・・
ほかに西脇順三郎、瀧口修造など発見するも、予算の都合で
次回以降のお楽しみということに。
それにつけても「ひし美ゆり子」のオリジナル版には
後ろ髪を引かれる・・・
ああ、オヤジの欲望に歯止めはないのか!
この辺の古本屋さんが普通の日曜にも営業していると
行きやすいんだけど。
たまに行くから面白いのかな、とも思う。
折角なので目標設定をする。
書籍:①吉増剛造さんの詩集(80年代~それ以前)
(『青空』『草書で書かれた川』『頭脳の塔』とか・・・)
②自分には全く縁のない豪華でまじめな写真集
(盆栽写真集とか、バクテリアの顕微鏡写真集とか・・・)
③ひし美ゆり子さん(アンヌ)の写真集
レコード:④武満さんのアンソロジー「ミニアチュール」シリーズ 2と4
特に下調べもせずにいったので、どこのお店に何があるのやらも
わからず、通りに沿って順番に覗いていった。
う~ん、古本屋さん独特の、あのほこりくさい空気が
なんともいえず、心地いい!
しかし、つくづく思うのだけれど、あらゆる情報が
ネットを通じて瞬時に世界中に広がっていく現代にあって
これだけの知的財産が埋もれている(?)というのも
実に奇妙な感慨を受ける。
図書館のように体系化されて保存・公開されるのではなく
それぞれがテーマを持つ、独立した小さな「書店」として
密集している。
秋葉原と似て非なるところは
アキバが時代の流れに乗って
急速にスクラップ・アンド・ビルドを始めている一方で
ここは、ひたすら時間を蓄積していることにある。
まるで降り積もるホコリのように。
(パソコンにホコリは大敵だ・・・)
訪問者は事前に何らかの情報を得ていなければ
ただひたすらランダムにその中をさまよい続ける。
ま、それが楽しくもあるのだけれど。
googleが世界中の図書館の本をスキャンして
文字検索できるようにする、と豪語しているが
ぜひ、神保町の古本も仲間に入れてほしいものだ。
なんてつまらないことを考えながら、目標はどうなったかというと・・・
①吉増剛造さん/目標物ナシ(数年前に出た新し目のものは1冊発見)
②まじめな写真集/特にビットの立つものはナシ(無念!)
③ひし美ゆり子/『ひし美ゆり子写真集 YURIKO 1967-1973』発見!
(1万円!)。
※う~ん、先日再販された新装版(一部写真が差し変わってる)を
買っちゃったんだよね~と悩みつつ、見送り(残念!)。
結局、購入したのは
④武満さんのレコード/「ミニアチュール」第4集 1,200円
(さくら通り沿いのササキレコード社にて)
「ミニアチュール」第2集 2,500円
(三省堂書店 自遊時間にて)
※これで念願のシリーズ全5枚がやっと揃った!
想定外でつい・・・
月刊「井川遥」袋入り、特別版 500円
(さくら通りのワゴンセールにて)
※昔、発売日に買っていたのだが、袋も開けずに
井川ファンの友人に譲ってしまっていたので・・・
谷川俊太郎/『定義』 500円
『コカ・コーラ レッスン』 600円
(意味不明なレトロ雑貨店にて。店名忘れた。)
※人に貸したっきり戻ってこなかったので
取り戻すつもりで買ってしまった・・・
ほかに西脇順三郎、瀧口修造など発見するも、予算の都合で
次回以降のお楽しみということに。
それにつけても「ひし美ゆり子」のオリジナル版には
後ろ髪を引かれる・・・
ああ、オヤジの欲望に歯止めはないのか!