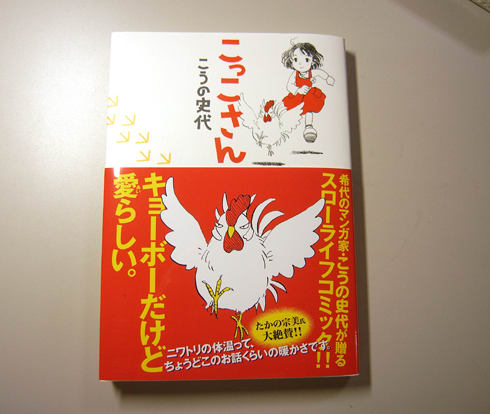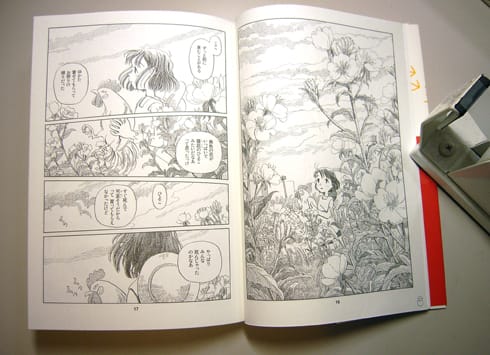上原ひろみ Hiromi BEYOND STANDARD

ジェットコースター・サウンドに磨きがかかって、
まさに音速セッションである。
優れた技術が新しい音楽の可能性を拓くということがあるが
このセッションは、まさにそういう新しさを
ガシガシ感じさせてくれて、実に楽しい。
リズム・メロディ・ハーモニーというのが音楽の3要素といわれているが
最近それに加えて音質というか音色というのか
特にアンサンブルの時の音のアマルガムも
とても重要なのではないかと思っている。
ニュアンスとしては「ハーモニー」に近いのだけれど
絵画の語法でいえば「マチエール」とか「バルル」といわれる
仕上げの重量感、とでもいうのか。
つまり、水彩画のようなさらっとした画質と
ゴッホの絵のような、絵の具の盛り上がりがそのまま
表現の質につながっている、そういう違いのことなんだけど。
例えば、最近ハマっているPerfumeというテクノポップの曲は
殆んど「打ち込み」だから
コンピュータの中で合成された
「ドラムのような音」や「ベースのような音」など
実に様々な音色が飛び交っている。
PC内でつくられる音だから、アイデアさえあれば
あらゆる音やリズムが出てくるわけで
そういう音のミクスチュアは感動的なくらい作りこまれていて
楽しいのである。
しかし、出てくる「音質」は、大雑把な言い方をすれば
ボーカルさえエフェクトがかけられているくらい
全てがデジタルに均一化されているので
いかにいろんな「音」を詰め込んでミックスを重ねていたとしても
非常に平坦で凹凸のない、のっぺりしたものである。
一方で、これも最近なぜか毎日聴いているのが
BEATLESの『REVOLVER』。
ご存知の通り、エレクトリックバンドとしての
普通の(当時はどうだったかは置いといて)ロックチューンから
エリナ・リグビーのような弦楽四重奏、シタールとタブラの入った曲やら
ホルン、ブラスアンサンブルを使った曲、
果ては現実音を入れたり、テープの逆回しを使ったりと
実に多彩で「異質」な音が混在している。
レコーディングの技術やプロデュースの意図にもよるのだろうが
BEATLES独特の、ボーカルと演奏がはっきり分けられた録音で
一つ一つの音がしっかりと生きている。
当然、アナログだから全て現実の楽器音を使っているわけで
打ち込みによる「均一化されたヴァーチャルな音」ではないから
音の数は少なくても、その分存在感がある。
現代的な打ち込みによる音密度に比べると
実にスカスカで、すき間だらけな音なんだけど
曲ごとの表現性というのか訴求力というのは
いつ聴いても圧倒されるというのか、飽きることはない。
色数は少ないけれど
絵の具のチューブをそのまま搾り出して描いているような
荒削りで、ゴツゴツした迫力があるのだと思う。
さて、Hiromiなのである。
1枚目の圧倒的なテクニックによる
スピード感が実に爽快であったわけだが
この『BEYOND STANDARD』の
ギターを加えたカルテットの緊張感と表現性は
まさにこのバンドでしかできない音のアマルガムを創り上げている。
どこまでがスコアでどこまでがアドリブなのかはよく分からないのだけれど
4人のプレーヤーが出す音とリズムの一つ一つが
綿密に計算されて、極彩色に絡み合っていく。
まるで4人の画家が8本の腕にペインティングナイフを持って
1枚のカンバスの上に一斉にガーッと絵の具を塗りこんでいくのを
早送りで見ているようで
気が付いたらゴッホの自画像ができ上がっちゃいました、という感じ。
絵の重量感という意味でも
絵の具の凹凸のある、それもチューブで出すというより
ナイフで盛り込んでいくという「技」を活かしながら
実は丁寧に丁寧に重ね塗りされているという重みがある。
スピーカーを通してパワーに圧倒されるのもいいけれど
ヘッドホンで(大音量で)一つ一つの音のニュアンスを
確かめながら聴いても、実に面白いのだ。
もう一つ言えば、それが人の手によるアナログな演奏であって
聴きながら、乾ききらない絵の具の匂いがぷんぷん漂ってくるような
生な感触も良いのだと思う。
彼女のピアノソロも良いけれど
カルテットのアマルガムの中で自在にピアノが跳ね回っているのも
それはそれで、実の爽快。
Hiromiの求める「音色」「音質」が見事に開花しているのだ。
昔、「芸術は爆発だ」と岡本太郎は言ったけど
まさに音楽で爆発しているのが
このHiromiなのだと思う。
Hiromi 『BEYOND STANDARD』 CD+DVD
※実は借り物だったりする・・・濱君に感謝!