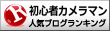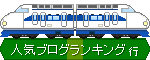今朝信州は気温が8度、昨年は1度でしたから、少し
穏やかな気温、曇り空ですがこれら晴れる予報です
今日は、うるしの日との事です。日本漆工協会が1985
年(昭和60年)に制定したようです。平安時代のこの日
に、文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が、京都・嵐山の
法輪寺に参籠し、満願の日の11月13日に漆の製法を
虚空蔵菩薩から伝授されたとされる伝説からこの日が
制定されたようです。表題の通り私の街信州塩尻市は
木曽漆器とワインの街・・と大きな看板が至る所に・
塩尻市のPR史料によれば、慶長12年(1607年)以前
より奈良井宿では曲物が生産されていたことが確認で
きているが、塗物生産については寛文5年(1665年)が
初見となるようです。約350年前のことだが、それ以前
の伝承には天正10年(1582年)に木曾義昌との戦いに
敗れた武田勝頼が、敗走するさいに本陣としていた木曽
平沢の諏訪神社の朱塗りの社殿に火を放ったという記録
がある。このことから当時奈良井や平沢には350年より
前に既に朱塗りの技術があったとも言われているが、
残念ながらそれを実証する史料は見つかっていない。
木曽漆器は、木曽五木(ヒノキ・サワラ・アスナロ・
コウヤマキ・ネズコ)に代表する木曽の山々の良質な
材を用いて作っていた木製品を丈夫にするために漆を
塗ったことから始まったと言われている。
江戸時代の初めには、ヒノキやサワラなどの薄板を曲
げて山桜の皮で縫い止めて作る奈良井の曲げ物が、全
国屈指の木製品として知られていた。そうした曲げ物
や他の木製品に直接漆を塗り重ねた製品(代表的な物
が木曽春慶塗)を多く製造していたが、明治に奈良井
で錆土という良質な下地素材が発見されたことにより
更に堅牢な平滑面を作れるようになり、庶民の生活用
具としての漆器だけではなく、高級調度品など様々な
製品へ展開していき、産地として発展を遂げてきた。
高度成長期には日本中に作られたホテルや旅館、また
生活が豊かになった一般家庭向けに、座卓やコタツ板
などの大物製品が主流となった。現在では大物が得意
な産地の特性を活かした社寺建造物や神輿・屋台など
の文化財修復も行われており、各工房では生活様式の
変化や多様化により需要が減った大物だけではなく、
小物を作る工房が増えてきています。最近は電子レン
ジや食洗器などの普及により家庭の食卓から漆器製品
が無くなってきましたが、我が家では箸もお椀も皿や
サラダボールも漆器製品が活躍しています。















コメント欄はお休みさせて頂いてます m(_ _)m