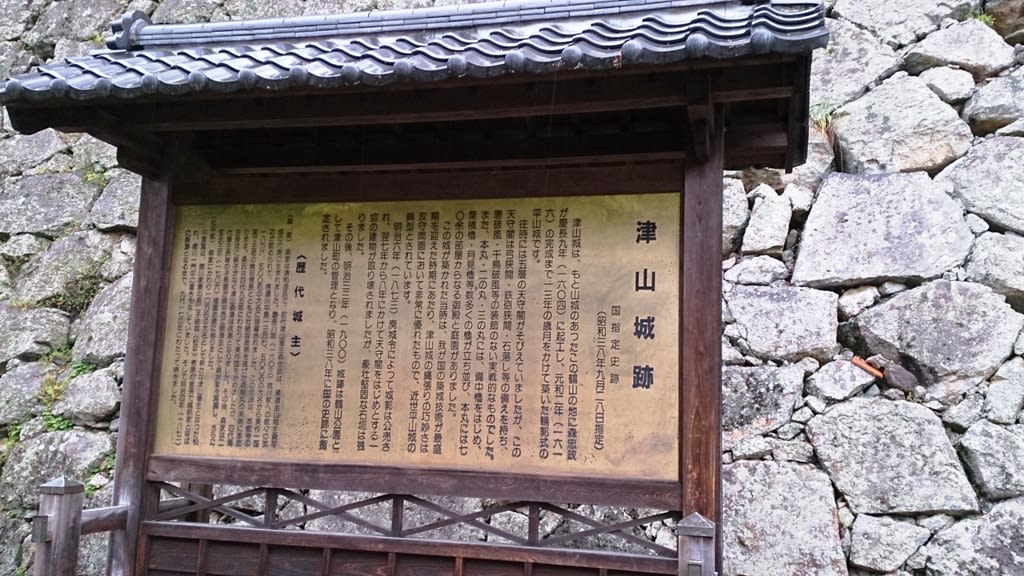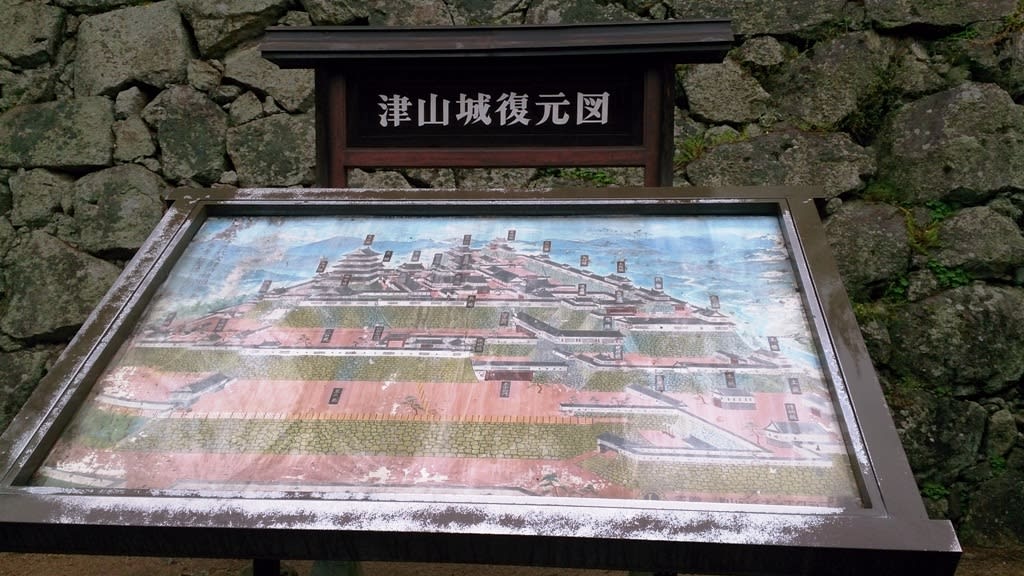【赤穂城】あこうじょう
【別名】加里屋城・苅屋城・仮屋城・蓼城
【構造】平城、海城
【築城者】浅野長直
【築城年代】1648年(慶安元年)~1661年(寛文元年)
【指定史跡】国指定史跡
【場所】赤穂市上仮屋 地図
地図
【スタンプ設置場所】本丸櫓門下・赤穂市立歴史博物館
【城郭検定】出題あり

案内図

赤穂市立歴史博物館の無料駐車場に車を停めて清水門より入城。
門を抜けると案内看板があります。
清水門から近い三の丸方面と武家屋敷から見て回ることにしました。

大石内蔵助邸長屋門

「忠臣蔵」で有名な大石内蔵助の屋敷門。
元禄14年3月の主君刃傷による江戸の悲報を伝える早打ちがたたいたのもこの門である。
大手隅櫓
建物は明治11年に取り壊されたが古写真をもとに昭和30年に復元された。
武家屋敷跡では他に大石神社や近藤源八屋宅跡を訪問。
二の丸門を抜けていよいよ本丸へ。
本丸門(高麗門)

お堀を覗くと・・・鯉ですかね^^;
そっちじゃなくて横矢掛けの枡形門を見ましょうよ。
白壁には沢山の狭間があります。
本丸門(櫓門)

ガイドさん曰く、復元した櫓門の梁は、一番太いものが三千万円したそうです。
本丸御殿跡

正面に天守台、眼下に広がる御殿跡は御殿の間取りを原寸大で表している。
城内は広いので歩き疲れて三の丸の番所で一休み。
赤穂藩、忠臣蔵が色濃く前面に押し出された城跡で平城で横矢が多用されたとにかく平な城郭でした。
平成27年5月3日登城
【別名】加里屋城・苅屋城・仮屋城・蓼城
【構造】平城、海城
【築城者】浅野長直
【築城年代】1648年(慶安元年)~1661年(寛文元年)
【指定史跡】国指定史跡
【場所】赤穂市上仮屋
 地図
地図【スタンプ設置場所】本丸櫓門下・赤穂市立歴史博物館
【城郭検定】出題あり

案内図

赤穂市立歴史博物館の無料駐車場に車を停めて清水門より入城。
門を抜けると案内看板があります。
清水門から近い三の丸方面と武家屋敷から見て回ることにしました。

大石内蔵助邸長屋門

「忠臣蔵」で有名な大石内蔵助の屋敷門。
元禄14年3月の主君刃傷による江戸の悲報を伝える早打ちがたたいたのもこの門である。
大手隅櫓

建物は明治11年に取り壊されたが古写真をもとに昭和30年に復元された。
武家屋敷跡では他に大石神社や近藤源八屋宅跡を訪問。
二の丸門を抜けていよいよ本丸へ。
本丸門(高麗門)

お堀を覗くと・・・鯉ですかね^^;
そっちじゃなくて横矢掛けの枡形門を見ましょうよ。
白壁には沢山の狭間があります。
本丸門(櫓門)

ガイドさん曰く、復元した櫓門の梁は、一番太いものが三千万円したそうです。
本丸御殿跡

正面に天守台、眼下に広がる御殿跡は御殿の間取りを原寸大で表している。
城内は広いので歩き疲れて三の丸の番所で一休み。
赤穂藩、忠臣蔵が色濃く前面に押し出された城跡で平城で横矢が多用されたとにかく平な城郭でした。
平成27年5月3日登城
 | 日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ) |
| 日本城郭協会,福代徹 | |
| 学研プラス |