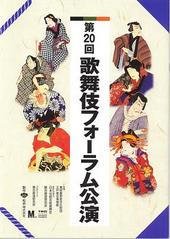以前から行ってみたいと思っていた歌舞伎フォーラム
今回、歌舞伎座へ行くのにあわせて行ってきました。
会場は、両国にある江戸東京博物館の一階ホール。
とても小さな劇場で、歌舞伎を身近に楽しむ事ができました
第一部「歌舞伎の美」
解説は片岡松三郎さん。
お客さんを舞台に上げて、上方の紙屋治兵衛と江戸の助六の衣装をそれぞれ着せての説明。
着物の着方や、歩き方、懐への手の入れ方など、ちょっとした事で、上方、江戸の雰囲気がにじみ出るのには驚きました
お客さんがセリフを言う、ちょっとしたお芝居もあり、楽しませてもらいました。
解説の松三郎さん、終始すまして解説されていましたが、最後はさすが上方役者さん、上方言葉で花道を引っ込まれました
花道と言っても花道はないので、座席と座席の間の通路です。
通路から2つめの席だったので、間近で見る事ができました。
歌舞伎舞踊「お祭り」
江戸の三大祭りの一つ、日枝神社の山王祭を描いた清元の舞踊。賑やかな曲に合わせて、鳶頭の瀧之さんと芸者の京妙さんが踊ります。
第二部「息子」
 あらすじ
あらすじ 
徳川末期の火の番小屋。
火の番の老爺が若い男を火にあたらせ、自分の息子は大坂へ行って真面目に暮らしていると話す。若い男も大坂にて、いかさま博打をして食いつないでいたという。
話すうちに、若い男金次郎は目の前の老爺が実の父親だと察するが、息子を信じきる様を見て、打ち明けられない。
そんな折に、捕吏がきて、お尋ね者を捕まえようと金次郎と激しい立廻り。
金次郎は一瞬の隙を見て逃げ、再び小屋の側へ戻り、一言「ちゃん」と呼んで雪の中をかけ去る。あっけなくもせつない九年ぶりの再会であった。
 感想
感想 
この演目に出演するのは、たったの三人。
しかも、しんしんと降る雪の中に、火の番小屋があるだけの舞台。
とても短い演目ですが、奥の深い人生が描かれた良い作品です。
息子を信じきっている老爺 松三郎さんは、頑固者だけれど、淡々と語る言葉の端々に優しさが出ていて、上手いなぁと思いました。
息子 金次郎の松三郎さんは、息子と打ち明けられないつらさが、ひしひしと伝わってきました。
ちょっとハスキーな松三郎さんの声が、さらに切なさを増し、「ちゃん!」と呼んだ時は胸がしめつけられました
第三部「応挙の幽霊」
 あらすじ
あらすじ 
ある夏の夜。
道具屋の甚三が二枚の幽霊画を安く仕入れ、偽物と知りつつも箱書きをし、応挙のものと信じさせ、呉服屋の若旦那に高く売る。
明日取りに来ると言い残して若旦那が帰った後、喜んだ甚三は幽霊画を拝み、御神酒を一杯供える。
気分良く呑んでいると、なんと掛け軸から幽霊が抜け出てきて「応挙の幽霊ですよ~」と名乗る。この幽霊が、大酒飲みで酒癖が悪く、脅すわ唄うわ踊るわ金をせびるわと大暴れ。
 感想
感想 
京妙さんの幽霊が大爆笑でした。
声は震えているし、両手はずっと胸の前でぶらっと下げているし(幽霊界の掟らしいです(笑))。
怖いと言うより、なんだか可愛らしい

この幽霊が大の酒好きで、ドンドン酔っぱらっていき、呂律も回らなくなり、甚三に絡む所なんて、京妙さんのペースで進んでいき本当に面白かったです。
それに振り回される甚三の松之助さんもオロオロソワソワ、その動き表情が笑いを誘います。
せっかく儲けたのに、それをまさか幽霊にせびられるなんて…
べろんべろんに酔っぱらっても京妙さんは最後までしっかり幽霊をしていました。さすがです
これは落語噺を歌舞伎にしたものです。
落語の応挙の幽霊もぜひ聞いてみたいです。
幕がおり、京妙さんのご挨拶。
すごく息があがっていました。舞台ではそんな素振りは全く見られませんでしたが、やはりハードなんですね。
出演者の紹介があり、第三部に出ていなかった松三郎さんも、「息子」の金次郎の姿で出てきてくれました。
最後は松之助さんで締め。
少人数の小さな舞台でしたが、歌舞伎の魅力を思う存分味わうことができました。
関西でもこういうフォーラムをぜひ開催して欲しいです。

今回、歌舞伎座へ行くのにあわせて行ってきました。
会場は、両国にある江戸東京博物館の一階ホール。
とても小さな劇場で、歌舞伎を身近に楽しむ事ができました

第一部「歌舞伎の美」
解説は片岡松三郎さん。
お客さんを舞台に上げて、上方の紙屋治兵衛と江戸の助六の衣装をそれぞれ着せての説明。
着物の着方や、歩き方、懐への手の入れ方など、ちょっとした事で、上方、江戸の雰囲気がにじみ出るのには驚きました

お客さんがセリフを言う、ちょっとしたお芝居もあり、楽しませてもらいました。
解説の松三郎さん、終始すまして解説されていましたが、最後はさすが上方役者さん、上方言葉で花道を引っ込まれました

花道と言っても花道はないので、座席と座席の間の通路です。
通路から2つめの席だったので、間近で見る事ができました。
歌舞伎舞踊「お祭り」
江戸の三大祭りの一つ、日枝神社の山王祭を描いた清元の舞踊。賑やかな曲に合わせて、鳶頭の瀧之さんと芸者の京妙さんが踊ります。
第二部「息子」
 あらすじ
あらすじ 
徳川末期の火の番小屋。
火の番の老爺が若い男を火にあたらせ、自分の息子は大坂へ行って真面目に暮らしていると話す。若い男も大坂にて、いかさま博打をして食いつないでいたという。
話すうちに、若い男金次郎は目の前の老爺が実の父親だと察するが、息子を信じきる様を見て、打ち明けられない。
そんな折に、捕吏がきて、お尋ね者を捕まえようと金次郎と激しい立廻り。
金次郎は一瞬の隙を見て逃げ、再び小屋の側へ戻り、一言「ちゃん」と呼んで雪の中をかけ去る。あっけなくもせつない九年ぶりの再会であった。
 感想
感想 
この演目に出演するのは、たったの三人。
しかも、しんしんと降る雪の中に、火の番小屋があるだけの舞台。
とても短い演目ですが、奥の深い人生が描かれた良い作品です。
息子を信じきっている老爺 松三郎さんは、頑固者だけれど、淡々と語る言葉の端々に優しさが出ていて、上手いなぁと思いました。
息子 金次郎の松三郎さんは、息子と打ち明けられないつらさが、ひしひしと伝わってきました。
ちょっとハスキーな松三郎さんの声が、さらに切なさを増し、「ちゃん!」と呼んだ時は胸がしめつけられました

第三部「応挙の幽霊」
 あらすじ
あらすじ 
ある夏の夜。
道具屋の甚三が二枚の幽霊画を安く仕入れ、偽物と知りつつも箱書きをし、応挙のものと信じさせ、呉服屋の若旦那に高く売る。
明日取りに来ると言い残して若旦那が帰った後、喜んだ甚三は幽霊画を拝み、御神酒を一杯供える。
気分良く呑んでいると、なんと掛け軸から幽霊が抜け出てきて「応挙の幽霊ですよ~」と名乗る。この幽霊が、大酒飲みで酒癖が悪く、脅すわ唄うわ踊るわ金をせびるわと大暴れ。
 感想
感想 
京妙さんの幽霊が大爆笑でした。
声は震えているし、両手はずっと胸の前でぶらっと下げているし(幽霊界の掟らしいです(笑))。
怖いと言うより、なんだか可愛らしい


この幽霊が大の酒好きで、ドンドン酔っぱらっていき、呂律も回らなくなり、甚三に絡む所なんて、京妙さんのペースで進んでいき本当に面白かったです。
それに振り回される甚三の松之助さんもオロオロソワソワ、その動き表情が笑いを誘います。
せっかく儲けたのに、それをまさか幽霊にせびられるなんて…
べろんべろんに酔っぱらっても京妙さんは最後までしっかり幽霊をしていました。さすがです

これは落語噺を歌舞伎にしたものです。
落語の応挙の幽霊もぜひ聞いてみたいです。
幕がおり、京妙さんのご挨拶。
すごく息があがっていました。舞台ではそんな素振りは全く見られませんでしたが、やはりハードなんですね。
出演者の紹介があり、第三部に出ていなかった松三郎さんも、「息子」の金次郎の姿で出てきてくれました。
最後は松之助さんで締め。
少人数の小さな舞台でしたが、歌舞伎の魅力を思う存分味わうことができました。
関西でもこういうフォーラムをぜひ開催して欲しいです。