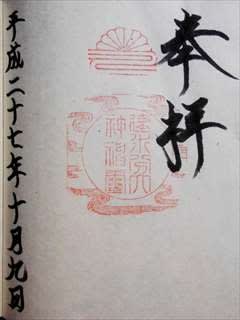江戸時代から昭和初期の町並みが残ることで知られる「富田林寺内町」。富田林市の中心にあり、東西に7本、南北に6本の街路で区画された東西約400メートル、南北約350メートル、面積約13.3ヘクタールの台地上に、近世の町割りをよく残した街並みが広がります。

富田林寺内町は、戦国時代末期の永禄3年(1560)、本願寺一家衆興正寺第16世・証秀が、石川西側の河岸段丘上の荒芝地を百貫文で購入し、一向宗興生正寺別院を中核に開発された宗教自治都市として発展してきました。

興正寺御門跡兼帯所由緒書によれば「周辺4ヶ村(中野・新堂・毛人谷(えびたに)・山中田)の「八人衆」の協力で、芝地の開発、御堂(興正寺別院)の建立、畑・屋敷・町割等を行い、富田林と改めたことに始まるという」と記載されています。

伏見城の城門を移築したと伝わる「興正寺別院山門」は、国の重要文化財指定。

寺内町の核ともなるのが、江戸時代初期17世紀中頃の建造で富田林寺内町の中でももっとも古い建築物とされ、また現存する町家の中でも最古と考えられている「旧杉山家住宅」。

杉山家は代々『杉山長左衛門』と名乗り、富田林寺内町の創設にもかかわった富田林八人衆として町を経営した旧家のひとつとされています。また明治時代に与謝野晶子らと共に活躍した明星派歌人『石上露子』の生家としても知られています。

旧杉山家住宅の向かい側にある「じないまち交流館」。富田林寺内町の歴史と文化を生かしたまちづくりを推進するとともに、地域の賑わいや交流を創出する拠点として開館されました。

いつの時代の看板でしょうか?日章旗の下には「国誉足袋」、隣は見た目にもわかりやすい白足袋と「足袋」の文字。古い看板はそれだけで面白く見飽きません。

「遠隔地取引用革袋」・・正直な話、よく分からない代物です(^^;) とはいえ、ここに展示されているものは、みんなこの町で普通に存在していたものばかりなのです。

じっくり歩くととてもではないけれど見終わるなんて無理な寺内町。今ならそれも有かと思えるのですが、この当時は行きたい場所が多すぎて、無理なスケジュールを組んでいたように思います。

19世紀中期(1854年)の築造の「葛原別邸」。18世紀末に酒屋を始めたと伝えられている葛原家の分家で、画像では見えませんが「三階蔵」で知られています。


18世紀中期の築造とされる「杉田家住宅」、屋号を「樽屋善兵衛」と称し、油屋を営んでいました。現在は「杉田医院」として看板を上げています。

18世紀中期の築造と推定される「木口家住宅」

18世紀中期の築造とされる「橋本家住宅」、屋号を「別井屋」と称し、酒造業を営んでいました。入口には駒つなぎの置石が残されています。

辻角にたてられた「あてまげのみち」。防衛上の観点から、寺内町の街路のほとんどは直行しておらず、角で少しずらされた「あてまげ」によって、まっすぐの見通しが妨げられるようにつくられています。

寺内町の町境は、屋敷裏にめぐらされた「背割り水路」で区切られ、その水路は雨水や生活排水路として今も利用されているそうです。

江戸期、周辺よりも一段高い台地上に作られた寺内町の出入り口に設けられた四坂・・聳えるような石垣沿いに続く坂道が町への入り口です。

訪問日:2008年4月26日