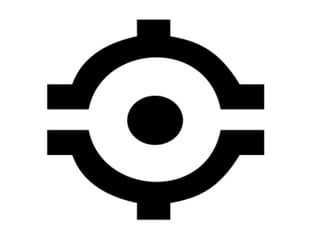「大股で歩いても、小股で歩いても危険」といわれていたことからその地名がついた「大歩危(おおぼけ)・小歩危(こぼけ)」。 2億年の時を経て四国山地を横切る吉野川の激流によって創られた約8kmにわたる渓谷は、まさに見るものを圧倒させる質感と共に、見事な景観を生み出しています。

「大歩危」とは、吉野川西岸の旧山城町西宇地区から高知県大豊町大久保地区の一部までと、その対岸となる旧西祖谷山村の一部を指す総称。剣山国定公園の一画を成しており、2014年には「小歩危」と共に国の天然記念物に指定されました。

西宇地区の一画、「レストラン大歩危峡まんなか」敷地内に建立されているのは、時の逓信(ていしん)大臣『後藤新平』が、明治42年(1909)秋にこの地を訪れた折に詠んだ【岩に題す 天下第一 歩危の秋】。大歩危を代表するとも言われるこの句によって、それまで秘境とされていた「大歩危・小歩危の」景勝が広く国内に認知されるようになったと言われています。

句碑の右前に展示されているのは「県指定天然記念物」の「三名含礫片岩」。ちなみに大歩危の「礫質片岩(れきしつへんがん)」は、含礫片岩として、国の天然記念物に指定されているのですよ。・・あれ?県じゃなくて国??と思われた方、何と!😲!私たちがこれを見る一週間前に国指定に変更されたのです。

いやもうね、どんだけ天然記念物が好きやねん!とついつい突込みがはいるのですが。だってね、日本国が認めるほどの記念物ですよ、やっぱり興味は惹かれるじゃないですか。 で、往々にして「なんちゃ~?ようわからん?」となるのですが、今回はモノが見えて触れる分、分りやすかったし😅

句碑のある「レストラン大歩危峡まんなか」から見る大歩危峡は、紅葉の赤が無くとも十二分に美しく、特に岩肌の白とエメラルドの水とのコントラストは、言葉にし難いほど。ですが・・瑠璃より深い川面を真下に泳ぐ鯉のぼりの爽やかさ、これは子供よりも大人の方が感激します。

自然の姿をあるがままにと言うのは勿論ですが、こうした人の匂いが感じられる装いもまた格段に美しいと思えます。ここから遊覧船に乗って大歩危峡観光ができると言う事で、下には何艘かの船も見えています。


ちなみに、この美しい景観を写真に収める為にはある程度の高さが必要となりますが、大丈夫、こんな展望台まで用意されて、まさに至れり尽くせり。

対岸の緑を縫うように電車が通り過ぎていきます。あんな狭い場所に線路があったことも驚きですが、運よく電車に遭遇できたことも驚き😲

電車も見たからという訳では有りませんが「大歩危駅」まで行ってみる事に。ところが駅のロータリーは予想外の狭さ、車を置くスペースもままなりません。とりあえず電車はまだみたいだし、ロータリーの隅に停車し、駆け足で構内に。

改札口の向こうでは藁沓を履き、蓑を着けた『児啼爺(こなきじじい)』の駅長さんが笑顔で出迎えてくれます。秒を惜しんでの記念写真😄、実に思い出に残るよい記念になりました。

国道から駅に入る為の高架橋にマイクロバスが見えたので速攻で車を出し、次に向ったのは妖怪屋敷と石の博物館が併設された「道の駅・大歩危」。
昨夜はここで車泊させていただきました事、本当にありがたく感謝しています🙏🙏

この「大歩危」ですが、さすがは「児啼爺伝説:発祥地(水木先生・談)」だけあって、妖怪の姿も見覚えのあるものばかり。でもご亭主殿に頼んで参加してもらった顔出しは、誰もその存在に気がついて貰えませんでした😅

岩石・鉱物が展示された石の博物館「ラピス大歩危 」。マスコットキャラクターはラテン語で『石』『宝石』を意味する名前の『ラピスちゃん』。

「大歩危駅」に寄ったのだから「小歩危駅」もと言うことで、急遽の寄り道。道路の隅に作られた結構な数の急な石段を登った先が「小歩危駅」です。

駅からだと、さっき走ってきた道がこんな風に見えます😲。 毎日の足となる最寄の駅がこんな高い位置にあるなんて、ただ、驚きでした。

訪問日:2014年3月24日~25日
------------------------00----------------------
「大歩危駅」の所在地、旧三好郡西祖谷山村(にしいややまそん)は、徳島県の北西部、吉野川の中流域東岸に位置した村です。北は三好郡三加茂町・井川町・池田町、西は三好郡山城町、東は三好郡東祖谷山村、南は長岡郡大豊町に隣接。屋島の戦いに敗れた平家の落人伝説や阿波山岳武士の伝説が残り、切り立った岩肌が広がる吉野川流域「大歩危」や祖谷川の渓谷に架かる「かずら橋で知られています。

明治22年(1889)、町村制の施行により、美馬郡東祖谷山村、美馬郡西祖谷山村が発足。
1950年、東祖谷山村、西祖谷山村が三好郡に編入。
昭和43年(1968)12月28日制定の村章は「「にい」を図案化したものです。」

------------------------00----------------------
「小歩危駅」の所在地、旧三好郡山城町(やましろちょう)は、徳島県の北部最西端、吉野川の中流域西岸に位置した町です。北は三好郡池田町、南には三好郡西祖谷山村、西は愛媛県四国中央市、南は高知県長岡郡大豊町に隣接。高知県いの町を水源とする吉野川が町東端を南北に貫き、愛媛県新居浜市を水源とする銅山川が町北部を東西に貫いて、吉野川に合流。三傍示山が町南西部と愛媛県四国中央市と高知県長岡郡大豊町に跨り、山間へき地で平坦な個所が極めて少なく、総面積に占める森林面積の割合は 85% にものぼります。「町の木:杉」「町の花:アンズ」「町の鳥:メジロ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、三好郡山城谷村・三名村が発足。
1956年、山城谷村と三名村が合併、町制を施行し改称して、三好郡山城町が発足。
昭和41年(1966)10月1日制定の町章は「頭文字の「山」を図案化したものです。」

訪問日:2014年3月25日
------------------------00----------------------
比較的快適に走れていた県道32号線から、国道319号線に入り、高知自動車道新宮ICに向かったのですが・・・まさかこんな酷道とは😱。
見通しは悪いわ、一車線だわ、たまにハイスピードで地元車らしい対向車は来るわ😭 国道だからと油断した!次回は絶対に遠回りする!!

合併した旧自治体は別にして、「上勝町」「那賀町」「神山町」「石井町」「佐那河内村」が未訪問。これらの地を再度訪れる事が出来るかどうかは神のみぞ知るですが・・多分無理だろうな。
徳島県のご当地マンホールは、2014年3月25日の三好市をもって終了。明日からは愛媛県のマンホール・神社仏閣・名所に旧跡&迷所の紹介です。