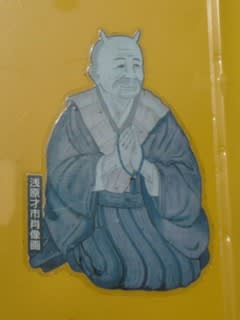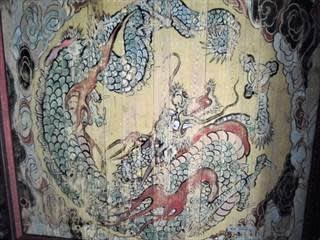戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎え、日本最大の銀山として世界に知られた「石見銀山」。「大森銀山」「佐摩銀山」とも呼ばれ、その最盛期には、世界の銀の三分の一を産出したと言います。

銀山川沿いの通りには、当時の面影を残す武家屋敷や代官所跡、豪商の住宅などが残されており、昭和62年に重要伝統的建造物群保存地区( 鉱山町)として選定。この美しい町を歩いてみたく、2011年&2013年の二度に渡っての来訪です、

「大森代官所前」の駐車場、最初に目にしたのは高さ2mの岩盤の上にある「西南之役戦死者紀念碑」。紀念碑は当時の島根県知事籠手田安定の提唱によって明治十年に建立。

きっと明るい時間帯なら沢山の人で賑わう筈の「食事処おおもり会館」もひっそりと静まり返り、「天領のうた」の碑だけが私たちに愛想を振りまいてくれます。

最初の訪問は、もうすぐ日が暮れようという時間。通りには観光客の姿も無く、家々も表戸を閉ざしています。 人気のない通りは、迫り来る夕闇に自ら溶け込むようにひっそりと、ただ優しく、ただ静か。それはそれで風情がありますが、街歩きを楽しむにはあまりにも不適切な時間帯だったと反省(-_-;)

二度目に再びこの地を訪ねたのは、前の訪問で行けなかった幾つかの場所に行く為もありましたが、何よりも人の気配のする町の空気を味わいたかったから・・・いくら人混みが苦手と言っても、モノには限度と言うものが有ります(-_-;)

大森の町並みの中で、いつも多くの観光客の撮影スポットになっている橋の写真、二枚並べてみました。 一枚はもうすぐ夕闇に包まれる直前の僅かな日差しの下。

もう一枚は、真昼の陽光の下。橋の下がこんな石造りのアーチになっていたこと、二度目で初めて知りました (゚o゚*)

微妙なカーブを描いて伸びる道の両脇にたたずむ家々、その佇まいは2年の歳月を経ても変わりません。 人が多すぎるのは苦手ですが、それでも賑やかに活気付く観光地の風景はやっぱり良い!・・と言いつつ、何故か人気の少ない場所を選んでいる私たち、こんなに素敵な町並みなのに・・人の姿がありません(笑)

二年の歳月を飛び越え、ごちゃ混ぜの画像で紹介する大森の町歩き。白漆喰の建物は「旧大森区裁判所」。現在は「町並み交流センター」として活用されています。

「大森代官所跡」には文化12年(1815)に再建された門長屋があり、内側には門番詰所や仮牢などが残されています。19時前にも関わらず門が開いていたので、門の内側と建物の外観を見ることが出来ました。


古い道標・・文字が読み取れない(-_-;)

敷地中央の建物は明治35年に建てられた「旧邇摩郡役所」。今は「石見銀山資料館」として、鉱山道具や、鉱山に関する古文書、奉行や代官の遺品などが展示されているそうです。

我が家の画像には珍しく(笑)、観光客の姿がある重要文化財「熊谷家住宅」。 この大森の地において鉱山業の他、酒造業、金融業、代官所の御用商人などを務めた熊谷家。その広大な建物は、石見銀山御料における有力商人の、生活の変遷を如実に伝えています。

街歩きの途中で、かなり珍しい建物を発見。今では博物館くらいでしかお目にかかれない理容室の風景が整然と残された店内。何とこちらのお店、現役の理容室なんですよ。

お店の入り口横に設置された碑には「理容遺産認定第一号-四 石見銀山理容館 アラタ 全国理容連合会」と刻まれています。

道路上に設置されたちょっと渋い観光マップは「代官所跡」から「龍源寺間歩」までのコースと、現在地を示しています。 町歩きの観光ポイントごとに姿を現し、今どこにいるのか、目指す場所は何処なのかを教えてくれます。

訪問日:2011年5月15日&2013年5月23日