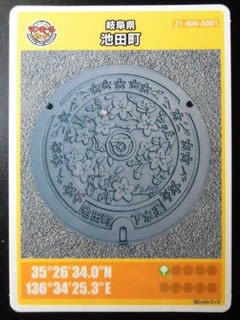神戸町下宮に鎮座される「下宮日吉神社」。御祭神は『大山咋神、大貴己神』。

境内の入り口で参拝者を出迎えてくれる三猿。「見ざる・言わざる・聞かざる」

「創建は弘仁8年(817)、伝教大師の東国巡錫を機に、この地を納めていた『安八太夫』の願いにより、「比叡坂本日吉大社」の摂社として勧請されたのが始まりです。」境内由緒より

拝殿前より神域を守護されるのは、西保城主『不破河内守光治』が寄進した、笏谷石製の狛犬さん一対。室町時代末期の石造狛犬の遺構として貴重な事から、昭和33年に岐阜県文化財に指定されています

しっかりとガラス張りの覆い屋の中にいるので、画像では詳細な姿を紹介することは出来ません。が、大切な狛犬さんを守る為であれば致し方ないこと、実物を見られるだけでも良しとしましょう。

こちらは大正7年(1918)2月建立の浪花狛犬さん一対。阿形さんの手の下では、可愛い(?)仔狛が、なぜか逆立ちをしているのがユーモラス。>


日吉さんと言えば、何と言っても「魔除けの神猿(まさる)」は、無くてはならない存在。こちらは、いかにも神様のお使い風な「神猿」と、山から下りてきたばかり風の「お猿さん」のコンビ。

ちなみに神戸町神戸には、もう一社「日吉神社上宮」が鎮座されておりますが、未参拝。そちらでは国重文の三重塔や、狛犬さん(レプリカ)が拝見できたとか・・なんで帰宅して資料を探している時になって、そんな事実が判明するのか・・😭 神戸町町役場内に展示されていたレプリカの狛犬さん。たとえレプリカのレプリカでも見られたんだから良しとしなければ。

参拝日:2018年10月11日