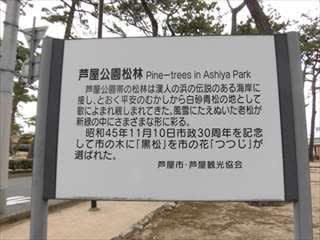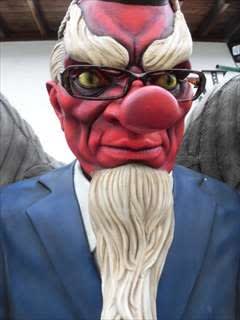大阪府豊中市、池田市、兵庫県伊丹市にまたがる関西三空港のひとつ「大阪国際空港」。乗るのは絶対に「ご免蒙る!!」私ですが、地上で見る分には全然、余裕😄

実際、この年になるまで、飛行機には一度も乗ったことがありません。独身だった頃に一度だけ、家族全員になだめすかされて琵琶湖の遊覧飛行に乗った事がありますが、唯々恐怖で震えた30分でした。以来、飛行機には乗りたくない!!海外への旧婚旅行も、飛行機に乗りたくないという理由で拒否ったほど、筋金入りの飛行機嫌い😣

ただし、見るのは本当に好き!。地上に降りた飛行機も、頭上高く飛ぶ飛行機も、見つけると子供のように喜びます😄 ましてこんなに間近でなんて、嘘みたい!

とまぁ、いろいろと御託を並べましたが、本日は離陸する飛行機が撮影できると噂の「猪名川の土手」ではしゃぎまくり。それでも足りずに、俗に飛行機マニアご用達と噂される「伊丹スカイパーク」にやって来ました。目的?もちろん、飛行機を、見・る・た・め! 滑走路がこんなに側にある事にも感激。

目前で、今まさに機首を上げた瞬間

飛び立つ飛行機・着陸態勢に入った飛行機、いやもう、感動😄


飛行機を見ている間、何度も往復するタンクローリー。多分、着陸のたびごとに燃料補給をしているのだろう・・それも有る意味・・すごい😲

猪名川の土手の一画、飛び立つ飛行機をひたすら見ていた私、まさかその瞬間を写真に残せるなんて想像もしていませんでした。何といっても次から次へと頭上に現われるのですから、下手な鉄砲も何とやら😅


実際にはもっと近くて大きく見えるのですが、シャッターを切った瞬間にはもう遥か空の向こう。ものすごく運が良ければこれくらいの距離で見えますが、鮮明ではありません😅

興奮冷めやらぬままに伊丹スカイパークに移動して、離着陸のたび毎に心の中で歓声を上げて、しっかり楽しみまくった一日でした。

気が付けば辺りはうっすらとオレンジ色、引き上げの予定時間は余裕でオーバー。バイクタンデムで我が家までは、渋滞が酷くて大変なのです😣 名残は惜しいけれど、そろそろ引き上げ時。

興奮冷めやらぬ私にご亭主殿が言いました。「飛行機に乗って北海道とか行こうか?」 突然の申し出に一瞬戸惑ってしまいましたが、もちろん、きっぱり!!はっきり!お断りしました😄
訪問日:2006年10日28日