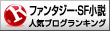時間研究所 水本爽涼

第16回
有象無象の言の葉に、左へ右へと揺れ動く、水面に浮かぶ枯葉が三枚、それが私達なのだ。予測を超越する何か得体の知れない時空の流れに一喜一憂する私達…、私達とは言わずと知れた、塩山、悟君、それに、この私である。世間一般の人間から見れば、とても常人とは思えない私達の研究である。何の利益もない無意味な研究…得たものといえば、三人の友人関係が構築できたぐらいだ。私は塩山の話に耳を傾けながら漠然とそう巡っていた。
「時間が流れる感覚を例えるなら、一つの方法として数値的に模索するのが適当でしょう。例えば、二十歳の若者と六十歳の老齢の男がいたとしますと、この二人が感覚で捉える一日の長さは、若者の方が20分の1×365分の1×10,000≒1.37で、初老の男の場合は、60分の1×365分の1×10,000≒0.46ということになります。10,000を乗じたのには別に意味はなく、小数点以下は四捨五入です。で、数値的に長さの感覚を捉えると、若者は1.37、老齢の男は0.46と一日を捉えている勘定になります。私達が子供の頃に比べ、歳月を短く思う所以(ゆえん)でしょう。しかし、もっともらしいこの説よりも、最近は経験すると短く感じるとの説が主流になりつつあります」
T大理学部卒の塩山は数式まで披瀝(ひれき)して熱弁をふるった。これには流石(さすが)に参った。私が、いつぞや考えていたことを、彼もまた考えていたのか…と思った。悟君などは短絡思考で、「そういや最近、一年が短こう思いまんな」と気楽に言う。こういう感覚的なことは、単純に考えた方が深く考えるよりいいのかも知れない、と私は真摯(しんし)に思った。塩山の数値的表現は、それはそれで強(あなが)ち間違ってはいないのだが…。
その後、暫(しばら)くの間は無意味な雑談をして、次回の会合の方針を決めて散会となった。方針としては、個別観察ではなく、三人の協同観察を試みようという新しい図式である。これは、私が提案し、二人とも異存がないということで了承されたのだが、活動の大きな方針変更であった。
「人生って、いったいなんなんでっしゃろなあ…」
漠然と言った別れ際の悟君の言葉が、部屋に一人残された私の心に甦(よみがえ)る。
私達が追跡しているゴフンという時間、これが描く軌跡の変化は、よく考えると人生のほんの僅(わず)かな断片なのである。この断片のゴフンの積み重ねが一つの人生模様を創作するのだ。その一片は、恐らく天文学的数値となるだろう。数値的発想は塩山の分野だから、ここはひとつ彼に研究して貰えればと考え、次回の会合で依頼することにした。忘れぬよう、観察帳の余白にメモ書きしつつ、ほっと一息入れて床(とこ)に着いた。疾うに深夜の一時は過ぎている。今ではもう当り前になった炬燵(こたつ)の寝床へ毛布を一枚、どこか少し惨めっぽいが、これがどうして、慣れてくると大層、心地いい。臥して天井を見上げると、つまらない想念に苛(さいな)まれる。何のメリットもない研究を愚直なまでに続けている私達だが、いったいこの先どうなることやら…。私は成果を確信して瞼(まぶた)を閉ざした。
頑(かたく)なに研究する姿勢、これは各種多様な発明研究には欠かせないものだが、私達のそれは、そんな大仰なものではない。だが、ある意味では人間行動に秘められた大発見となる可能性もあるのだ。…、と、一応は大義名分を唱えておかないと、私達自身が馬鹿男の集合のようにも思え、とても研究を続けていく気にはなれない。
桜の満開が今年も各地で賑わいを見せている四月初旬、私と悟君、塩山の三人は、久しぶりに連れだって桜並木が延々と続く堤防の小道を歩いていた。
町を丁度、真っ二つに分けるかのように流れるこの川の河川敷(かせんじ)きには、私達が生まれる遥か昔に植えられたと思える見事な桜並木が存在する。春の麗らかさも手伝ってか、すっかり気分よくした三人は、長閑(のどか)に天を仰ぎ草絨毯(じゅうたん)に寝転がっている。陽光に暖かいそよ風が小気味いい。
悟君が、なにやらブツクサ言っている。瞼(まぶた)を閉じ、心地よさでウトウトとしていた私は、隣の小さな雑音に、「なんだい?」と問いかけた。
「あっ、寝たはりましたんやな、すんまへん。いや、どおってことでもないんでっけど、なんか的(まと)を射るような観察モンがないかと思いましてな。ついボソボソ言ってまいました。空の雲見とると、正夫はんは、どない思わはるか知れまへんけど、形がどんどん変わっていきよる。あれでも観察したろかと…。ちょいと、やけっぱちでっけどな、どないでっしゃろか?」
「あ~あ、君の発想には呆れるばかりだ…」
そう私が悟君に返すと、それまで沈黙していた塩山が、ついに口を開いた。そういえば私達三人は、さきほどから、もう二十分以上もドッペリと草の上に寝そべっていた。塩山も春風に誘われウトウトしていたのだろう。それが、悟君の雑音で目覚めたというのは、私と同じようである。
「よし、これからあの山の上空を観察しようじゃないか。あの一角の雲と空が、どういう変化を起こすかだ。とにかくゴフンという時間でだ。俺達はこのままじっと寝そべって、動かない状態でいよう」
私は退屈紛(まぎ)れに、そう言った。明らかに研究する意図の時間観察とは趣旨が違うのだが…。
ゴフン後、私達は各々の違った感性で、観察対象となった空域ゾーンの一角に対しての意見を述べ合った。
「あの巻雲(ケンウン)は消えなかったなぁ…。ただ、綿雲(わたぐも)の方は形をどんどん変えて今はもうない。ほとんど青空になってしまった。ゴフンは結構、長いねぇ」と、私がまず発起した。
「そうでっか? 僕は巻雲っちゅうのは分かりまへんでした。それに綿雲については、形が大福餅に見えていたのが、終いにはラーメンかウドンのように伸びてもて、消えよりましたな。ゴフンあると、鉢は空にできまっせ」
悟君らしい食品に見立てての観察である。
「私は下の山と対峙して見ていました。最初はいい塩梅(あんばい)で、雲と山が一つの絵画になってましたね。最後の方は、雲が消えてしまいましたから、景観が台無しになりました」
これは塩山らしい感性だ…、と私は思った。
続