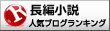パターン・・思考・行動・文などの型や様式を意味し、日常で普通に使われる言葉だ。もはや日本語化していて、お決まりのパターン・・などという形でよく使われる。いいパターンは安定しているから変化が少なく、反して変えよう! とする力に強く、大いに助かる。ただ、変化しないから、癖(くせ)、生活習慣、慣習などといった悪い繰り返しがパターン化したときは、助かるものも助からない。いわば溶かそうとする水に対して、凍らせようとする氷(こおり)のような存在なのである。とすれば、逆のパターンどおしが鬩(せめぎ)ぎあえばどうなるか? これを考えてみるのも面白い。^^
とある家の日曜である。朝からご主人がお決まりのパターン化された深刻[シリアス]なテレビ番組を、お決まりのパターン化された食事を食べながら渋面(しぶづら)で観ている。
「ワンパターンで変わり映(ば)えしないわねっ!」
「そこがいいんじゃないかっ!」
主人も、妻に反発して言い返し、どうしてどうして負けてはいない。
「この前、おなたがいないときに観た△○テレビのホニャララ、面白かったわよっ!」
「ホニャララ? 何だい、それは?」
「だからホニャララっていう訳が分からない番組よ」
「訳が分からない番組? …それが面白かったのか?」
「ええ、面白かったのよ」
「そうか…。ちょっと観てみるか…」
そう言いながら主人は徐(おもむろ)にテレビのリモコンを手にし、映ったホニャララをしばらく観ていた。そして突然、大声を発した。
「ほほぉ~~!! なかなか面白いじゃないかっ!」
主人のパターンは、いとも簡単に妻に溶かされ、ビチャビチャの水に変化してしまった。それからというもの、主人はそのホニャララという番組を観るのが病みつきになったと聞く。ビチャビチャの水が凍結し、また新しい氷となってパターン化した訳だ。妻は主人が機嫌がよくなり、大いに助かるそうだ。都合の悪いパターンは変えれば大いに助かる・・というお話である。^^
完
物事に変化が生じるには動機が存在する。動機がなければ物事は起こらず、何の変化もない。この動機は直接、目に見えない心の動きである。尾籠(びろう)な話ながら、生理現象でプゥ~~! っと、おならを漏(も)らしたとしよう。^^ 音がすればまだ分かるが、嫌(いや)な臭(にお)いだけなら、誰が漏らしたのか分からない。もちろん、見えないからだが、この見えない動機こそが一番の曲者(くせもの)だ。通り魔事件とかいう説明のつかない事件が起こるが、行為者というより犯人は動機なのだから、人には捕らえようもなく、実は厄介(やっかい)なのだ。一応、犯行に及んだ者を、捕らえたっ! くらいの結果に終始し、真犯人である動機は巧妙に逃れているのである。^^ まあ、一目惚(ひとめぼ)れの動機が何なのか? までは分からないようなものだろう。^^
とある家庭内での話である。
「戸棚(とだな)に入れておいた昨日(きのう)の月見団子、一つ足りないぞっ! お前が食ったのかっ!」
「知らないわよっ! お団子が一人で歩いて散歩にでも行ったんでしょ!」
「そんな馬鹿な話があるかっ!」
するとそこへ、離れからご隠居が現れた。
「団子? ああ、それなら儂(わし)が食った。腹が減ってたんでな…」
「なんだ! 父さんでしたか。ははは…」
息子は青菜(あおな)に塩で、それまでの威厳(いげん)はどこへやら、萎(な)えて愛想笑いした。
「小さいわね…」
妻は、たった一つくらいで…という気分で呟(つぶや)いた。
「すまんなっ!」
「いいえっ! まだ、こんなにありますから…」
いい動機でコトが進行する場合は大いに助かるが、悪い動機は、不意に襲ってきて助からなくなるから始末(しまつ)が悪い。^^
完
何をもって強い弱いと言えるのか? を考えてみるのも面白い。お金持ちは貧乏な人より強いのか? また、多勢(たぜい)は小人数(こにんずう)より強いのか? はたまた、若者は老人より精力が強いのか? などなど、強い弱い・・という定義づけは実に曖昧(あいまい)なのである。確かにお金持ちは金に物を言わせていろいろ自由に出来るから強いが、自由に出来るあまり、勇み足をして不正使用で墓穴(ぼけつ)を掘り、助からない場合だってある。強くても結果は弱かった訳だ。また、大軍が少数の軍勢に敗れた桶狭間の戦いのようなこともあり、強い勢力だから助かるとは限らないのである。同じように、若者が弱く、老人が精力絶倫で女性を助ける強い場合だってある。^^
秋の夜長(よなが)、テレビがガナらなくてもいいのにガナっている。とある夫婦の会話である。
『台風13号は勢力を維持し、今夜半、○○半島を暴風域に巻き込みながら北上する可能性がありますっ! 中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速35メートル…弱い! 実に弱いっ!』
「お父さん、弱いそうよ…」
「そうかっ!? 強いと思ってたが、そうでもないか…」
「あなたと同じっ!」
「今、何か言ったか?」
「何も言ってないわよっ!」
夫は早々と家の補強をやめ、一杯飲むと床(とこ)についた。
「やっぱり弱いじゃない…」
「んっ?」
「なにもない。おやすみ…」
「ああ…」
次の朝、夫が窓を開けると、眼下(がんか)数m下の家まで床下(ゆかした)浸水していた。
「弱くなかったんだ…」
「あなたは弱かったけどね…」
「んっ?」
このように、強い弱いの判別は実に難しく、助かる根拠(こんきょ)とはならないのである。^^
完
進む方向が逸(そ)れる・・ということがある。墨壷(すみつぼ)で線が引かれた木材の上を電鋸(でんのこ)で切っていたのはいいが、うっかり話をしていたばかりに逸れ、とんでもない方向に切ってしまった場合だ。こんな場合は大いに困る。逆に、上陸が心配された台風が逸れ、まったく違った方向へ行ってしまった場合は大いに助かる。いや、むしろ、やれやれ…と安息(あんそく)の息を誰しも漏らすことだろう。^^ このように、逸れると、いい場合、悪い場合の二通(ふたとお)りがある。
連休でとある温泉へ向かった家族のお話である。
「いえ、ここは違います。その温泉はこの山向こうですね」
「ええっ!! この地図にはそう書いてますがっ!」
「ああ、地図ですか。地図はそうでしょうが、現実は違います。ドラマと実話の違いですかな、ははは…」
「と申しますと、ここは?」
「ええ、ここも温泉ですが…」
「温泉ですか? よかった…」
「いやいや、そうじゃないんで。温泉という地名の温泉ですから、湯には浸(つ)かれません…」
「湯に浸かれない温泉…ですか?」
「はい! 残念ながら…。よく道に逸れた方が寄られるんですよ。しかし、私らにはどうも出来ゃ~しませんから…」
「はあ、そらそうです。有難うございました…」
「小一時間です…」
「どうも…」
家族は温泉ではない本当の温泉へと向かった。
勘違いで逸れることもある訳だが、こんな笑えるような軽い話の場合は助かる。^^
完
世の中は電気、電話、電池、電波、電子・・などの見えない物が飛び交う高度機械文明の時代となり、どんどん、進化している。だが、冷静に考えれば、果たして、どうなんだろう? と首を傾(かし)げたくなることも、ままある。例(たと)えば、歩いて二、三分の距離にあるうどん屋へ店屋物(てんやもの)の天麩羅(てんぷら)うどんを電話で注文したとしよう。歩いて往復したとしても、その距離は僅(わず)か五分ばかりなのである。確かに早いことは早いし便利だ。しかし、足は使わないから退化して弱ることになる。そうして、どんどん弱り、^^ やがては使っていた人がこの世から消える憂(う)き目となる。とっ! どうなるかっ!!? 分かりきったことだ。使われていた見えない物は使う人がいなくなって使われなくなるから、ご主人を失って失業をする。そうしてやがては、ゴミとなって捨てられる運命を辿(たど)る。ゴミとなって捨てられるとは、人の場合と同じでこの世から消え去ることを意味する。すなわち、進化ではなく、このまま高度機械文明の時代が進めば、文明は退化することになる訳だ。だから、人が助かるためには、人がついていける程度に機械文明を進めよう! という結論に立ち至る。^^
残暑が厳(きび)しい中、涼しい木陰(こかげ)のベンチに座り、二人のご隠居が語り合っている。
「まだ、暑いですなっ!」
「はいっ! 朝夕は少し涼しくなりましたが…」
「今年の夏もクーラーで、なんとか凌(しの)ぎましたぞっ!」
「私もです。暑かったですからな…」
「ええええ、そらもう…。クーラーなしじゃ、あの世逝きですわっ、ははは・・・」
「しかし、クーラーを使うとクールビズに反するようですな」
「はい。しかし、命には代えられません」
「クーラーを使うと温暖化で暑くなり、またクーラーを使いますか…」
「ちっとも進化してないですなぁ~」
「退化です…」
「この林も消えるようですぞ。工場が建つとか…」
「人も自然も助かる道はないもんですかなっ!」
「まだまだ暑くなりそうですなっ!」
「はい…」
文明の進化は、必ずしも人が助かることにはならないようだ。^^
完
物事が順調に進行しているときは何の問題もないが、突然、障害(しょうがい)や妨害(ぼうがい)で進行が止まったとき、瞬間、『さて、どうするっ!』と、戸惑(とまど)うことになる。こんなとき、冷静な判断が出来たり、他人の助けがあれば助かる。人は孤立無援(こりつむえん)には弱いのだ。いや、私は弱くないっ! と強がられる方も、実は相当に弱いのである。^^ 『さて、どうするっ!』と思ったとき、次の打開策が閃(ひらめ)く、思い浮かぶ、頭に描かれる・・などすれば、助かる方向へと進んでいくことになる。ダメな人は、まあ残念ながら、諦(あきら)めて欲しい。^^
現在、私達が暮らしている社会の進行は、目に見えない判断の連続だ。成功している人々は、さて、どうするっ! の一瞬、一瞬を上手(うま)く判断して躱(かわ)しながら生きているのだ。躱せない人は、…まあ、それまでとなる。^^
とある学校で試験が行われている。学生が机上(きじょう)の試験用紙を前にして難問に挑(いど)んでいる最中だ。試験官の教師は、会場の一段高い机の椅子にドッカリと構(かま)えて座り、異常がないか…と、見下ろしている。ところが、である。その教師が、こともあろうに、俄(にわ)かに便意を催(もよお)した。最初のうちは、なんとか耐えられたが、その便意は益々(ますます)強まり、とうとう耐えられない状況にまで到達した。さて、どうするっ! である。教師は生徒側から教壇机で前が見えないのを幸いに、ズボンと下着をゆっくりと下ろし始めた。そして、答案用紙の余った紙を徐(おもむろ)に、それとなく、目立たないように椅子の下へと置き、コトを済ませたのである。そして、何もなかったようにその紙を徐に、それとなく、目立たないように丸め、ズボンと下着を上げた。拭(ふ)かず終(じま)いである。そのときチャイムが静かに鳴り、試験の終了を告げた。
「やめぇ~~!!」
教師は偉(えら)ぶった声で、何事もなかったように生徒に叫(さけ)んだ。
「クラス委員は用紙を集め、職員室へ持ってくるようにっ!!」
教師は、なおも落ち着き払(はら)った声でそう告げると、怯(ひる)むことなく丸めた紙を徐に、それとなく、目立たないように隠し持ち、教室から消え去った。
「おいっ! 何か臭(にお)わねえかっ!」
「そういや…」
「クッセェ~~!! 妙だなぁ…」
学生達の、その後の会話である。
さて、どうするっ! とコトが逼迫(ひっぱく)したとき、冷静な判断をして慌(あわ)てなければ助かる・・という一例のお話だ。^^
※ 答案用紙の残り紙がなかった場合は、下着を使うつもりだった…ということです。^^
完
根回し・・世間で非常によく使われる言葉である。
『なにとぞ、よしなに…』
何げなく出された菓子鉢。その菓子鉢の中を、何げなくチラ見する代官。上げ底の菓子の下には金25両の包み金が並ぶ。
『! フフフ…◎◎屋、そちもなかなかの悪(ワル)よのう』
『そう申されますお代官様も…』
『こやつ、言いよるわっ! フッフッフッ…』
『フフフ…』
などという会話が交わされたであろう時代から現代に至るまで、根回しの必要性がなくなった試(ため)しはない。^^ もちろん、いい意味の根回しもある訳で、事前工作で物事を成功へと導(みちび)き、大いに助かる行為ともなる。
とある中学校の体育館である。
「監督! 僕、どうなんですかっ!?」
「お前なぁ~。…お前は補欠とレギュラーの際どいとこだっ!」
「…ってことは、出られる可能性も?」
「ああ、まあなっ! ははは…なくはないっ!」
「先生、これ、うちの店の特上品の試供品ですっ! どうぞ…」
「ははは…根回しかっ? 試供品ならいいか…。いや、悪いなっ! まっ! 考えておこう!」
部員は、これで出られるっ!…と、監督に一礼すると体育館を後(あと)にした。
大会当日、その生徒は今か今かと出番を待っていたが、残念ながらついに試合には出られなかった。
このように、根回しをしたからといって、必ずしも助かる結果にはならない・・ということになる。^^
完
元(もと)とは元々あった物(もの)や事(こと)である。物は形(かたち)があって分かりやすいが、事にはその形がなく、漠然(ばくぜん)とした出来事だから忘れられやすい。では、その元が何をもって元とするのか? が問題となる。分かりやすく言えば、その元々あった物や事の元は何なのか? ということだ。平成が元号(げんごう)なら、次の元号は何なの? という話ではない。^^
二人の老人が様変(さまが)わりした工事後の町を眺(なが)めながら小高い丘の叢(くさむら)へ座り、話し合っている。
「綺麗になりましたなぁ~!」
「はあ、まあ…」
「浮かぬ顔をされておられますが、なんぞ訳でも?」
「確かに綺麗になりました。綺麗にはなりましたが、どこか元あった風情(ふぜい)が消えましたな。これでは助かるものも助かりませんっ!」
「はあ、それはまあ、そうですが…。それは時の流れ・・でしょう」
「いやぁ~、それはどうですかな。元は元々あった風情ですから、時が流れようと戻(もど)ろうと、変わらんものだと私ゃ思っとりますが…」
「元々ですか?」
「はいっ! 元々あった風情です」
「では、建てかえ前の町に建っていた建物の前に建っていた建物の風情は元ではないと?」
「… いやいや、そりゃ、元の風情でしょう」
「ということは、建てかえ前の町の風情は元の風情ではない・・ということになりますが…」
「ははは…、そうなりますかな」
「はいっ! そうなります」
「ははは…考えてみりゃ、元なんてものは、いい加減なものですなっ!」
「ははは…深く考えるほどのことでもないですな」
「ははは…そのようですな」
二人の老人は話し合うのが馬鹿馬鹿しくなったのか、立ち去った。
元とは何なのか? などと深く考えず、軽く考えた方が助かる訳だ。^^
完
生活する上で雑念が湧(わ)いて悩まされることがよくある。人はそれを煩悩(ぼんのう)と呼ぶ。まあ、煩悩が湧くから人生が楽しい訳で、煩悩が湧かないお坊さんのような人ばかりに世の中がなれば、これはもう、味も素(そ)っ気(け)もない世の中になってしまい、面白くも何ともなくなる。^^
とある繁華街の肉料理専門店の店前である。美味(うま)そうだろっ! と、食欲をそそるようなショーウインドウの数々の品書き写真が並ぶ。そのウインドウを見ながら二人のサラリーマンが立ち止まり、品定めをしている。
「サーロイン・・150g ¥3,000。…これにしますかっ!?」
「いやいや、それよかテンダーロイン・・100g ¥2,800の方が安くて美味そうだぜっ!」
美味しい物を安く食べたいっ! という雑念が湧いたのか、先輩風の男が惑(まど)わす。
「はあ、そういえば…。では、これで…」
「いやいやいや、ちょっと待てっ! 200g ¥4,000のサーロインの量が多くて美味そうだな…」
「はあ…」
後輩風の男は、『どれだって、いいじゃないかっ! こちとらっ、腹が減ってんだっ!!』と怒れる気持をグッ! と抑えて沈黙した。
「いやいやいやいや、額からすりゃ、150g ¥4,200のテンダーロインの方がいいか…」
先輩風の男の食に拘る雑念は続く。そのときである。店主が店の中から出てきて、OFFと書かれた表札を入口ドアにかけた。
「すみません、お客さん。閉店時間なもんで…」
二人のサラリーマンは、後ろ髪を引かれる思いで店前から立ち去った。
雑念が多いと、思っていることがダメになる場合が多いから、抱かない方がいいようだ。^^
生活する上で雑念が湧(わ)いて悩まされることがよくある。人はそれを煩悩(ぼんのう)と呼ぶ。まあ。、煩悩が湧くから人生が楽しい訳で、煩悩が湧かないお坊さんのような人ばかりに世の中がなれば、これはもう、味も素(そ)っ気(け)もない世の中になってしまい、面白くも何ともなくなる。^^
とある繁華街の肉料理専門店の店前である。美味(うま)そうだろっ! と、食欲をそそるようなショーウインドウの数々の品書き写真が並ぶ。そのウインドウを見ながら二人のサラリーマンが立ち止まり、品定めをしている。
「サーロイン・・150g ¥3,000。…これにしますかっ!?」
「いやいや、それよかテンダーロイン・・100g ¥2,800の方が安くて美味そうだぜっ!」
美味しい物を安く食べたいっ! という雑念が湧いたのか、先輩風の男が惑(まど)わす。
「はあ、そういえば…。では、これで…」
「いやいやいや、ちょっと待てっ! 200g ¥4,000のサーロインの量が多くて美味そうだな…」
「はあ…」
後輩風の男は、『どれだって、いいじゃないかっ! こちとらっ、腹が減ってんだっ!!』と怒れる気持をグッ! と抑えて沈黙した。
「いやいやいやいや、額からすりゃ、150g ¥4,200のテンダーロインの方がいいか…」
先輩風の男の食に拘る雑念は続く。そのときである。店主が店の中から出てきて、OFFと書かれた表札を入口ドアにかけた。
「すみません、お客さん。閉店時間なもんで…」
二人のサラリーマンは、後ろ髪を引かれる思いで店前から立ち去った。
雑念が多いと、思っていることがダメになる場合が多いから、抱かない方がいいようだ。^^
完
事故で人が助かるときとダメなときの違いを考えてみよう。助かる場合は必然的に、誰かによって、あるいは目に見えない何らかの力によって命が救われる・・ということを指す。ダメな場合はその逆である。孰(いず)れにせよ、事故に遭(あ)って助かる方がいいに決まっている。事故といっても、他人による場合と自分自身による場合とがある。^^
真夏の、とある海水浴場である。多くの海水浴客で浜辺は大いに賑(にぎ)わっている。そんな中、夫婦と三人の子供の五人家族がビーチパラソルの下で寛(くつろ)いでいる。
「去年、ここで水難事故があったんだ。皆、気をつけるようにな」
「はいっ!」
「はぁ~~いっ!」
「ふ~ん…」
上の長男、長女は素直な返事をしたが、下の五才になる次女は生返事(なまへんじ)を返した。
「もおっ! あなたが一番、危ないんだからっ!!」
母親はすぐに次女を叱(しか)りつけた。
その一時間後、心配していた事故が起きた。がしかし! どういう訳か、その事故は事故というまでには至らないただの事故で、事故ではなかった。詳(くわ)しく解説すれば、水難事故というまでには至らないただの迷子になった事故で、両親の心配は同じだったが、助かる確率が全(まった)く、違っていたのだ。
「私が溺(おぼ)れたのっ? ふ~~~ん??」
発見されたあとの次女のひと言である。
迷子事故は、ほぼ100%に近い確率で助かるが、水難事故だと逆に非常に危険な確率が出る。事故といっても種々雑多(しゅじゅざった)で、様々(さまざま)な違いを見せるのである。^^
完