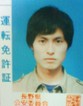2/1(土)、NSG美術館で「渡邉桜子作品展」を見に行ってきました。
現在、NSG美術館では、「粛粲寶(しゅくさんぽう)の鳥展」の開催期間に、「渡邉桜子作品展」「近藤武弘小品展」「楽美会展」の3つの展示を、短期間で順番に同時開催しています。
そのことをたまたま知り、「渡邉桜子作品展」の終了直前に見に行くことができました。
そもそも渡邉桜子さんはここ、NSG美術館のスタッフの方だそうです。
しかし、若い頃から美術に親しんでいたそうで、初めてこういった展示に挑戦してみたということです。




まず、メインとなる作品は、色を塗った小さなキャンバスの上に、蓮と透明なケース、そして商品のパックみたいなものを組み合わせた作品。
家に蓮がたくさんあったから思いついたそうですが、そもそも蓮以外の材料は言ってしまえばゴミのリサイクル、有り余っているものや本来なら捨てるものをこうして作品として生まれ変わらせるアイディアは楽しいなと思いました。

中学や高校の美術部で描いたという風景画や静物画も展示。
まさに基本に忠実ないい絵だなあと思うのですが、「自分は生意気だった」みたいな当時を振り返る文章も面白く、そもそもこういう昔の作品もちゃんと保存しておいて、それが今の自分の創作の糧になっているところが素敵だと思いました。




毎年年賀状用に作るという干支のイラストや紙粘土細工、エジプトのミイラ作りで臓器を入れるカノポスという壺をシャンプーの容器で再現したもの、粛粲寶も描いていた中国の伝説の妖獣・白澤の粘土細工なども展示。
どれも遊び心が溢れている上に、凄まじい存在感を放っている!

シーチキンフレークの缶詰とマグロが一体化したROOTSという作品も。
遊び心と微妙な毒を感じる…君はそれで幸せなのかい?

最後は、修学旅行で見た三十三間堂に影響を受けて作ったという、粘土細工の首を付けた三十三体の人形たち。
三十三体、みんな顔が違うし、とにかく遊び心のアイディアが溢れまくっていました。
全体的に、遊び心満載で、こんなに自由に作品を作れたら楽しいだろうなあという気持ちが伝わってきました。
自分も何か作りたくなるような展示でしたね。