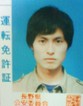7/11(日)、T・ジョイ新潟万代で「アメリカン・ユートピア」を観てきました。
予告編はこちら。
世の中には、観る前から世間の評価が高すぎてハードルが上がりまくってしまう映画というものがあります。
本作「アメリカン・ユートピア」は、僕がこの映画の情報を知る前から、知り合いやSNSの映画好きから、映画製作の仕事をしている知り合いまで、とにかく周りから「今年ベスト!」「とにかく観ろ!」など大絶賛の声が聞こえてきていました。
「アメリカン・ユートピア」は、元トーキング・ヘッズのデビッド・バーンが新たなバンドメンバーと行ったライブを、「ブラック・クランズマン」などのスパイク・リー監督が映画化。
トーキング・ヘッズといえば、かつて松本爆音映画祭でライブ映画「ストップ・メイキング・センス」がめちゃくちゃ良かったので、僕のハードルも上がってしまうわけです。
こうして、ハードルを上げに上げて観に行ったわけですが、正直初めて観た時の率直な感想は「なんだか分からない」。
正直、自分には理解しがたい音楽のライブを見させられて、映画の中の観客も映画館の観客も盛り上がっているのに、自分はどんどん取り残される思いに…
そんな感じでまったくぴんとこなかった僕は、なんとこの映画の9割くらいを寝てしまったのです!
ただでさえ少ない金の中から映画代を頑張って出している人間なのに、なんと勿体ないことを!
言い訳を言うと、繰り返しになりますが、僕は「ストップ・メイキング・センス」のトーキング・ヘッズのロックなライブはめちゃくちゃ好きでしたよ。
ただ、「アメリカン・ユートピア」はちょっと難解というか…
まあ、どんなにいい音楽だとしても個人の趣味や好き嫌いってのはあるから、僕にはハマらないものもあるんだろうな…
どんなに周りが絶賛しても、僕は自分の感想を堂々と言う!面白くなかった!
…なんてことを思って自分の気持ちを整理したものの、次第に「これでいいのだろうか」という気持ちになってくる俺。
というのも、これは僕の基本的な考えなのですが、世の中のエンターテインメントは結局好き嫌いが別れる世界なのかなとは思うものの、とはいえ本当に素晴らしい作品には個人の好き嫌いを超越した芸術的価値があるのではないか?
というか、映画の9割を寝ていた僕はそもそもこの映画の面白さをちゃんと理解するどころか観てすらいないではないか!
もし本当に批判するのであればちゃんと観てから批判しなければいけないではないか!
ただまあ、本当に合わなかったから寝てしまったのではないか?という疑問もありつつも、やっぱりもう一度観ておこう!
というわけで、翌日再び同じ映画を観に行ったのですが(たまに僕は寝るとこういうことがあってお金を無駄にしてしまう)…
2回目を観たら、ちゃんと面白かった!
というわけで、ここまでは長い前置きで、ここからがちゃんとした感想です!
映画が始まると、デビット・バーンがステージの真ん中に一人で登場して、脳の模型を持ちながら謎の脳の歌を歌う…
…一度目に観た時はここで付いて行けなくなって寝てしまったわけですが、今度は頑張って観るぞ…!!
観ていると、2人のダンサーが登場してデビット・バーンの歌に合わせてダンスを始めたり、バンドメンバーが1人また1人とそれぞれの楽器を持って登場し、最終的に9人の楽器隊、合計12人がステージに登場します。
そして、2時間約のライブ中に次から次へと曲を披露するのですが、合間にデビット・バーンのMCはまるでスタンダップ・コメディアンのようです。
映画を観ながら、一つのことに気付きました。
曲の内容も、MCの内容も、一貫して「人間」のことを表現しているということ。
曲の歌詞の内容は、人間の脳から始まり、人との付き合い、家や暮らしのこと、そしてメディアや社会について歌っているのです。
そして、デビット・バーンのスタンダップコメディのようなMCは、社会風刺で笑わせたり、かと思えば直球で選挙の投票率を上げよう!というメッセージも発信します。
もう一つ発見したのは、ステージ上には周囲が何本もの細長い紐状の暖簾みたいなもので囲まれていること以外、照明以外に何もない非常にシンプルなステージだということ。
その周りの暖簾みたいなものも、最初にデビット・バーンが一人で登場する時に上に上がっていってライブの始まりを印象的に表現したかと思えば、その暖簾を使ったバンドメンバーの出はけや、時にはそののれんの向こう側からバンドメンバーが楽器だけを出してくるなど、シンプルなセットを最大限遊んでいると感じました。
また、何も置かれていないステージに変化を付けているのが照明。
スポットライトの位置の変化に合わせて出演者も移動、真っ暗な中でスポットライトの下にデビット・バーンが一人で歌ったかと思えば明転してバンドメンバーが一気に登場してくる、ストロボのように暗転と明転を繰り返して躍動感を表現、客席側からステージを照らして出演者の陰を大きく映して動きを盛り上げる、などなど、照明だけでここまで色んな表現方法があるのかと思いました。
そもそも普通のライブってステージ上に色々な楽器が置いてあって配線で繋いでいることが多いのですが、このライブの場合は楽器隊は基本的に一人が一種類の楽器だけを体にくくりつけていて、しかも全部無線。
この状況を最大限生かして、ステージ上でまるで演劇やダンス公演のように全員が自由自在に動き回り、時に踊ったり、輪になってぐるぐる回ったり、動きを綺麗に合わせたり、とにかくこの12人の動きによってステージを盛り上げる。
中でも何回か、曲がふと途切れた時に全員の動きがぴったり止まって、そして全員が同時に曲と共に再び動き出す場面を観た時は、どれだけ息が合ったバンドなんだろうと思いました。
そんな感じで、曲によって「動」と「静」を巧みに使い分けるわけです。
そして、衣装は全員が揃いのカッコいいスーツで決めているのですが、よく見ると全員裸足なんですよね。
これはただカッコつけるだけではなく、人間らしい自由さを表現しているのかなと思いました。
そして何より、曲もロック調のものからダンスナンバー、スローなバラードなどなど、とにかくバリエーションが豊か。
個人的に、僕の好きなYMOやムーンライダーズを思わせる曲もあり、もしかしたら世界的なミュージシャンであるデビット・バーンの影響が日本にもかなりあるのではないかと思わされました。
そんなことを思って見ていたら、終盤でデビット・バーンが僕が感じていたことのまさに答えとなる話をしていました。
それは、デビット・バーンはこの世のあらゆるものの中で「人間」が一番面白いと思っているということ。
ステージ上から装飾や装置などの人間以外のものを極力排して、人間だけでどこまで面白いことができるのか、その表現力の可能性に挑戦していたということ。
そして、人間の芸術的価値を表現すると同時に、人間が平和に生きていけるために大切な社会課題や選挙の呼びかけなどを訴えていたということ。
また、今回のライブの出演者は、国籍も人種も、おそらくセクシャリティなども本当に多様な人達が勢揃いしていて、共に一つのステージを作ってたこと。
音楽やパフォーマンス以前に、出演者そのものが多様性の素晴らしさというメッセージを発していたと思いました。
しかも、クライマックスでは、Black Lives Matterの運動の中で歌われた、殺害された黒人の人達の名前を歌詞の中で呼びながら彼らへの追悼と、人種差別反対を訴えたジャネール・モネイの「Hell You Talmbout」をカバー。
こちら、ジャネール・モネイにどうしても歌わせてくれと直接連絡したそうですが、その歌をこのバンドメンバーで歌うことで、人種差別反対を訴えるのに国籍も人種も関係ないというメッセージだと感じました。
考えてみれば、この映画のスパイク・リー監督は「ブラック・クランズマン」で黒人差別問題を扱っていた方なんですよね。
劇映画でも音楽映画でも、人種差別という一貫したテーマを感じます。
ところで、デビット・バーンはライブの冒頭で謎の脳の模型を持ちながら歌ったあとで、「人間の脳は子供時代にはあった回路が大人になるにつれてなくなってしまう」みたいな謎の話をしていたのですが、ライブの最後のMCで「あの時失った回路を取り戻そう!」と言い出したではないか!
これはつまり、人間が失ったものを取り戻して平和な社会を目指そうという今回のライブのテーマとも通じるもので、まさかの伏線回収!あの謎のMCにもちゃんと意味があった!
そしてライブの最後には、あのステージの周囲を囲んでいた暖簾みたいなものもなくなり、楽器さえも持たずに全員の歌声だけという、本当に色々なものを究極まで削ぎ落して最後に残った「人間」の一番根底にある音楽という表現を見せてくれました。
かと思えば、アンコールでは全員がステージから飛び出して客席を練り歩きながら歌い続けるという、出演者と観客という境界さえもなくなって、同じ音楽を共に楽しむという感動的なラストでした。
そんなわけで、一度目は寝ちゃって全然面白さが分からなかったものの、寝ないでちゃんと観たらちゃんと面白かったし感動できる映画でした!
やっぱりこうやって、どんな作品も勝手に拒絶しないでちゃんと理解しようと頑張ってその良さを味わうのって大事ですね…
というわけで、できるだけこれからは映画館で寝ないようにしたい…
そんな自分の課題も分かったところで、得るものが多い映画体験でした!