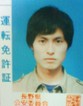2/7(金)、りゅーとぴあで「Choreographers 2024」を観に行ってきました。
コンテンポラリーダンス新進振付家育成事業2024の公演ということで、札幌と新潟で違う演目を上演するそうです。
上演前に、朝日新聞で芸術を扱っている方と舞踊評論家の方を招いてのトークがあったのですが、そのテーマが「メディアとしてみる、コンテンポラリーダンス」。
どういうことかと思ったら、メディアとは現実に起こったことを報じるものだが、コンテンポラリーダンスはまだ言語化されていない現実や人間の感情を表現するものだからある意味メディアではないかということ。
そもそも西洋では伝統的な劇場文化、そしtバレエなどのダンス文化があり、その上にコンテンポラリーダンスが発展したという歴史があるが、日本では明治以降にダンス文化が入ってきたので、コンテンポラリーダンスの文化は未だに根付いていないのではないかとのこと。
特に、観客が未知の芸術に触れて自分の頭で考えるような文化が未発達で、あらかじめ宣伝で提示された内容の作品で気持ちを満たすだけだったり、作者の意図を絶対的に信じて疑わない観客を育ててしまったのではないか…という話には、正直こういう人達の話は難しくて分からないことがよくある自分も、「分かるぞ!」と思ってしまいました。
その後、いよいよ本番。
全部で3つの演目が順番に上演されていきました。
大森瑶子「Tuonelan」
無音の舞台で1人の女性が踊っている。
まるで自然や動物の動きを再現しているようだ。
そこに別の女性が現れたと思ったらすぐに消えていく。
まるで突然踊っている人を見てびっくりしたみたいでちょっと面白い。
すると、突然オーケストラの音楽鳴り響くと、最初の女性が1人で指揮者のように直立したまま両手を振り回す。
その周りを4人の女性がぐるぐる回りながら踊りだし、まるで優雅な動物のようだ。
しばらく経つと、今度は電子音楽が流れ出し、5人の女性の踊りはまるでゲームの登場人物やロボットのようになっていく。
途中でYUIの「CHE.R.RY」が流れ出したり、5人が舞台から消えたり、再び現れたりを繰り返しながら、ばらばらだった踊りが次第に連動していく。
すると、ロボットのようだった踊りの中に。次第に前半の動物のような踊りが再び登場する。
これは、最初は自然の中で音楽を奏でていた人間が、オーケストラからの電子音楽という変遷を経て、最後は再び基本に立ち返る…みたいな音楽と踊りの壮大な歴史を表現しているのか?
…と思ってあとでパンフレットを見たら、この踊りは死の国と現世の境を流れる黒い川の白鳥という、想像以上に深い世界を表現していた!
言われてみればあの優雅な動物みたいな踊りとか、ばらばらのようで連動している踊りは、確かに白鳥のようでした。
砂連尾理+寺田みさこ「男時女時」
舞台上に男性と女性が登場し、二人とも何かを探すようにばらばらに踊り始める。
しかし、次第に2人の距離が近付き、2人の踊りが影響し合っていく。
一度、男性が舞台からいなくなったと思ったら、急に女性が服をめくって顔に被るというふざけたような行動を始め、その周りを「マンボNo.5」に合わせて男性が跳ね回る。
今度は女性がいなくなり、男性が舞台の真ん中で座り込んだと思ったら、今度は女性が舞台の奥にあるピンポン玉の山を舞台上にぶちまけ始める!
そしてピンポン玉だらけになった舞台の上で、2人がピンポン玉をまき散らしながら社交ダンスみたいに踊り始めたり、男性がピンポン玉を頑張って拾い集めて女性のスカート上に集めたりする。
二人が体を重ねる場面は妙に妖艶だ…と思えば、オーケストラの音楽に合わせて、二人が激しくぐるぐる回りだす。
全体的に、2人がばらばらに踊る場面と、一緒に踊る場面を繰り返すような舞台でした。、
男女2人だし、タイトルも「男時女時」だし、男女の近付いたり離れたりする心境や人間関係を表現していたのか…?
パンフレットによると、「男時女時」とは世阿弥の「風姿花伝」に出てくる言葉で、「時間の流れには良い時と悪い時があり、それぞれ口語にやってきては移り変わりするものである」という意味だそう。
全体的に静と動を繰り返すような舞台だったので、男女の物語によって移り変わる世界を表現したのかもしれません。
池ヶ谷奏「湊に眠る者たち」
1人目の女性が地図みたいな紙を持って、何かを探すように歩き回ると、ふと動きが止まる。
すると2人目の女性が現れて紙を持って歩き回り、また動きが止まると。今度は3人目の女性が現れる。
これがどんどん繰り返され、最後は7人で紙を見ながら動きが止まる…
すると、突然7人が同時に「あー、ここだー」みたいなことを言い出し、舞台の奥に7人が並ぶ。
そして、7人で踊りが始まるのだが、1人ずつ舞台から消えていき、最後に1人が残った時、天井から紐が下がってくる。
その紐に地図のような紙を括り付けると、紐は天井まで上っていく。
すると、また1人ずつ舞台に現れては、床から何かをかき集めるような動きを順番にしていく。
そして、全員が舞台の真ん中に集まり、人間の山みたいになっていく…
…と思ったら、急に和太鼓の音が流れ出し、舞台の真ん中では相撲のような動き、その周りでは祭りのような動きで全員が激しく踊り出す!
盛り上がったところで、再び天井から地図のような紙が下りてきて、6人が踊る舞台を1人が地図を持ちながら歩いていく…
パンフレットによると、この踊りは全員で古町の下町地区を探検して作ったそうです。
そう考えると、最初の動きは地図を持って町を探検していたんだなあと思ったし、後半は古町のお祭りや、曙公園の土俵を表現していたのかなあと思いました。
はい、僕はこんな感じで3つの舞台を楽しみました。
ちなみにこの日は会場を出ると積雪60cmの大雪の中を帰るハメになったので、そのことで頭がいっぱいになってしまいましたが、なんとか思い出して感想を書きました。
コンテンポラリーダンスは台詞がないからこそ、人間の踊りから自由に想像力が広がっていく面白さがあるなあと思いました。
というか、コンテンポラリーダンスの作り手、踊り手の人達は、一体どういう発想でここまで豊かな世界を表現できる踊りを生み出せるのか…
考えてみれば人は誰でも踊ることはできるのに、その誰でもできそうな踊りという行為で、ここまで豊かな世界を表現する身体能力と豊かなアイディアには本当に脱帽です。
いやー、たまにはこういう本物の芸術に触れる体験って大事ですね!