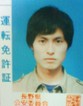東日本大震災から10年の今年、震災時のツイートのデータをまとめて当時を知るという技術をテレビで見ました。
少し前まで、たかがTwitterで政治や社会問題などに対して意見をつぶやいたところで何の意味があるんだ…という気持ちがどこかにあったのですが、その番組を見て、たとえツイートでもリアルタイムでつぶやいた言葉が歴史の記録になるんだなと思いました。
それで、やっぱりその時にしかつぶやけない言葉ってあると思うので、最近は意識して世の中に対して思った気持ちを積極的につぶやくようにしています。
特に、新型コロナウイルス禍に突入した去年からは、その時代の自分を記録するという意味で、Twitterやブログを今まで以上に積極的に使うようになりました。
そして今は、様々な問題や賛否両論を抱えたまま始まった東京オリンピックに対して、思うことを意識的につぶやくようにしています。
というわけで、あまり政治のことは書かないブログですが、せっかくなので忘れないうちにここ最近の気持ちをまとめておこうと思います。
ちなみに、僕が政治のことを考えるようになった経緯や、東京オリンピックに対する気持ちは、こちらの記事にまとめてあるので、もしよかったら見てみてください。
「政治について考えることと、自分自身と向き合うこと。」
軽く説明すると、僕は東京オリンピックが決定した直後から、「復興五輪」と言いながら、当時の安倍首相の「アンダーコントロール」という虚偽スピーチのように、被災地の復興よりも東京オリンピックを優先させるような政府の方針には疑問しかありませんでした。
しかし、2016年のリオオリンピックの閉会式で安倍首相がマリオの格好をして登場するセレモニー(僕の好きな椎名林檎さんやMIKIKOさんや中田ヤスタカさんも関わっていた)も素直に喜べない複雑な気持ちがあり、しかし日本のメディアもTwitterも結局盛り上がってしまったことに対する疑問もありました。
また、アスリートファーストと言いながらも、猛暑の開催時期や、トライアスロン会場の東京湾の水質汚染など、とてもアスリートを大事にしているとは思えないやり方にも疑問がありました。
それ以外にも、五輪を強行しようとする日本の方針にはずっと疑問があった中、コロナ禍が始まり、感染拡大を防ぐために中止するべきだという気持ちになりました(こういう人は多いのかなと思います)。
そんな感じで、東京五輪は招致の段階から現在にまで問題がありすぎだと思いますが、ただ考えてみればアスリートの人達も、別に東京五輪だからというより2020年に(結果的に2021年だったけど)オリンピックがあるなら開催地がどこだろうが出たかっただろうし、たまたま今回出たのがこんなオリンピックで気の毒だなという気持ちがあるので、アスリートの人達を責めたくはありません。
また、純粋にスポーツを応援している人達だって今回の東京五輪に反対したり疑問を持ってる人達は多いだろうし、僕は東京五輪には反対ではあるけれど、それはさておきスポーツファンの人達は本当につらいだろうし、気の毒だと思っています。
そんな中、東京五輪が始まるまでの一週間ほどで、開会式・閉会式の人事を巡る辞任・解任が相次ぐという出来事が起こりました。
せっかくなので、開会式までの、7/20(火)~23(金)の4日間に新潟日報の一面に載っていたオリンピック関連の記事を、一通り紹介しておきます。




7/15(水)、開会式、閉会式に関わる新たなアーティスト達が報じられましたが、その中の一人、コーネリアスの小山田圭吾さんが、20年ほど前にロッキンオンジャパン、クイックジャパンでのインタビューの中で、いじめ自慢ともとれる発言をしていたことがSNSを中心に指摘され、批判が集まり炎上するという出来事がありました。
小山田圭吾さんのこの記事は、知っている人達の中では有名で過去にも問題視されていたということですが、東京五輪によって今まで以上に注目を集めたことで初めて知った人達からも批判された、ということのようです。
(実際僕も、小山田圭吾さんに関しては、小沢健二さんとやっていたフリッパーズ・ギターの「恋とマシンガン」を知っている程度の人間で、このインタビューもこの機会に初めて知りました。)
(とは言え、昨年読んだ「ポスト・サブカル焼け跡派」という日本の音楽を中心としたサブカルチャーを評論している本の中で、フリッパーズ・ギターの小沢健二と小山田圭吾の違い、みたいな文章を読んでいたので、なんとなく腑に落ちる部分もありました。いい本なのでおすすめです!)
これに対して、過去に障害者をいじめ、それをインタビューで自慢していた人間がオリンピックやパラリンピックに関わることを批判する人、そういう少し調べれば分かるようなスキャンダルのある人間を安易に起用するオリンピック委員会を批判する人、そういう記事を掲載した雑誌の方にこそ責任があると批判する人、1990年代当時の人権意識の低さや悪趣味サブカルブームがあった時代背景を考慮して批判するべきだという人、ファンであるからこそショックを受ける人、もともと東京五輪に反対だった気持ちをさらに強める人、炎上が小山田圭吾さんへの過剰なバッシングなのではないかと指摘する人、昔のスキャンダルを今更蒸し返すことに疑問を持つ人…等々、様々な意見が飛び交う、まさに炎上となってしまいました。
こういう色々な意見を見ながら、僕自身はどういう風にこの問題を受け止めるべきか…と考えたのですが、小山田圭吾さんがオリンピックに関わることの是非や、オリンピックのあるべき姿、また当時の記事の検証などは僕なんかよりも適任の専門家の方々がいると思ったので、僕はそういう方向ではなく、これを機に今回の一件だけに限らず、「いじめ」という普遍的な問題について、あらためて自分の頭で考えるきっかけにしたいと思いました。
さて、あの雑誌の内容を信用するならば(と言っても、僕自身は全文読んだわけではなく、ネットニュースに書かれていた部分しか読んでいないのですが)、あそこで語られているのは紛れもなく「いじめ」「いじめ自慢」であり、それはどちらも決して許されない最低の行為であること、それは大前提としてはっきり書いておきます。
時代的な背景もあったとは言え、いじめはいじめであり、誰かを傷つけた過去はどれだけ謝罪、反省したところでなかったことには一生できない重い問題だとも思います。
実際この問題が炎上した翌日にはコーネリアスから公式に謝罪文が出されました。
それに対しては、時間が経ったとはいえ、たとえ形式的にだとしても謝罪文が出されたことは意味があることなのではないか(というか、海外のニュースにまで取り上げられてしまうほど大きな問題になった以上はああするしかないのではないか)、という気持ちと、それでもやっぱり、いじめ被害者の方に謝罪ができていない以上は何も解決していないのではないか、という気持ちが両方ありました。
内容が内容だけに、そしてそれがオリンピックという大きな場で明るみになってしまった以上、批判があって当然だとは誰もが思ったとは思いますが、さすがにここまで袋叩きにしたらそれもかえって小山田圭吾さんに対する新たないじめなのではないかという意見や、キャンセルカルチャーという言葉もネット上では散見されました。
その一方で、いじめとはそのくらい重い問題なのだから決して許されない、という意見も数多く見られました。
僕の気持ちとしては、僕自身いじめられた過去があり、10年、20年も前の出来事なのに思い出して腹が立つこともあるので、そのくらい根深い問題だということは理解できるし、それで小山田圭吾さんを批判している人達の気持ちは理解できました。
しかし、だからと言って、小山田圭吾さんの過去を過剰に蒸し返して批判し続けることには、それはそれで抵抗がありました。
どういうことかというと、確かに僕はいじめれていた人間ですが、同時に無自覚に誰かを傷付けていたことも確実にあるわけで、果たして自分は小山田圭吾さんを批判できるような人間なのだろうか…という気持ちがかなり強くあったのです。
まあ、小山田圭吾さんが語ったいじめくらいひどい行為をしたことはさすがにありませんが、それでも自分の中にも確実に存在する加害性に向き合う行為は、いじめられたトラウマ以上に、僕の中では恐怖を感じるものでした。
完全に清廉潔白な聖人なんていないわけで、おそらく誰もが誰かを傷付けた過去があり、では、そういう過去の過ちと人間はどう向き合えばいいのか、いつまで向き合い続ければいいのか、そう考えると簡単に答えの出ない問題だと思ってしまいました。
僕が過去に傷付けてしまった人は今でも僕のことを恨んでいるのかもしれない、そうなった以上、僕はいつまでこの問題を考え続ければいいのか、どれだけ反省、謝罪し続ければいいのか。
もしかしたらどんなに謝っても向こうは決して自分を許さないかもしれない、それでも自分は自分の人生を精一杯これからも生きていくしかない、その一方で自分が誰かを助けたり感謝されたりすることもあるという、人間は簡単に善悪では分けられない、複雑な存在なんだな、ということです。
誰かをいじめていた過去を忘れて、いじめられていた側がいつまでも恨んでいることも知らずに、幸せな人生を送っている人達なんて大勢いるわけで、でもその人達にだって幸せになる権利はあるはずだし、その幸せは誰にも奪えないという、いじめ問題は長い目で考えると本当に何が正解なのか分からなくなってしまう、本当に複雑な問題だと思ったのです。
そう考えると、いじめ問題は誰だって被害者にも加害者にもなりうる、誰もが当事者である本当に大きな問題だと思うし、もしかしたら人類が生きている以上、永遠に解決しない難しい問題かもしれません。
そしてこの問題は、オリンピックが始まろうが終わろうが、成功しようが失敗しようが、小山田圭吾さんが今後どうなろうが、ずっと続いていく問題なので、せめてこの機会にいじめ問題について真剣に考えてくれる人が一人でも増えてくれればいい、そのことでいじめに苦しむ人が一人でも多く減ればいい、と思いました。
でも、インターネットの炎上騒ぎって結局流行みたいなところがあるから、一時的に小山田圭吾さん一人だけを蒸し返しても何も変わらないのではないか、炎上して時間が経ったらみんな忘れてしまうというお馴染みのパターンになってしまうのではないか、小山田圭吾さんを批判していた人達の中で今後もいじめ問題を考え続けてくれる人が何人いるだろうか、などと考えてしまいました。
なので、せめて自分は、これ以上人を傷付けてしまわないように気を付けよう、やってしまったら謝ろう、発言には気を付けよう、今は笑えると思っていることも将来価値観が更新されれば問題になることもあるから気を付けよう、という方向で考えることにして、小山田圭吾さん一人を過剰に批判するのはやめました。
今はオリンピックのことがあるから騒がれているいじめ問題ですが、オリンピックが終わったあともずっと続いていく大きな問題だと思うので、僕はオリンピックよりもそっちを考えたいなと思ったからです。
そして個人的に僕は今回のオリンピック開催には反対ではありつつもオリンピック自体には大して興味がないし、小山田圭吾さんに対してもあまり興味がないのです(だって他人だし)。
ちなみに、僕はいつもわりとこういうスタンスで、少し前にナインティ・ナインの岡村隆史さん風俗嬢に関する女性蔑視的な発言で炎上した時も、無自覚な女性差別がなくなればいいなとは思いましたが、岡村隆史さんには別に怒らなかったし、彼が反省したかどうかとかは大して興味もありませんでした(だって他人だし)。
誰かが問題を起こして炎上した時は、その人を批判するよりも、自分自身の身に置き換えて、反省したり気を付けよう、という方向で考えるという、要するに「人の振り見て我が振り直せ」のスタンスです、僕は。
小山田圭吾さんが辞任した直後に、今度は小林賢太郎さんが解任になった時も、同じようなことを思いました。
一応書いておくと、小林賢太郎さんの場合は、本当にまだ無名の若手芸人だった時代の問題発言であること、それをとあるメディアがこのタイミングで掘り返して炎上させたこと、それを陰謀論者っぽい人が防衛副大臣に伝え、服防衛大臣が組織委員会の中で話し合うより前にユダヤ人の団体にリークし、いきなり解任になってしまったこと、等々、色々な問題がありすぎるので、小山田圭吾さんの時の問題とは違うとは思いつつも、それでもまあ、そっちの方は僕なんかよりも適任な方が検証してくれると思うので、僕はあくまで自分の意見を書いていきます。
個人的に、今回問題になった、小林賢太郎さんがラーメンズ時代にやったコントに登場した「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」は知りませんでしたが、個人的にNHKの「爆笑オンエアバトル」が好きでラーメンズも見ていた人間なので、例えば当時やっていた他のコントに出てきた「ホモ」や「不法滞在っぽい外国人」を使ったネタも、今の倫理観ではアウトだよなと思ったりしました。
今では普通に「あり得ない」と思うことも10年前は自分も特に疑問も持たずにネタにしていたこともあるし、小山田圭吾さんが批判された時はその背景にあった90年代の悪趣味サブカルブームが話題となりましたが、どの時代にもこういう無自覚な差別的な表現はあるし、時代の変化とともに間違いに気付き、価値観が更新されることを受け入れていきたいと思いました。
また、小林賢太郎さんが解任された時のコメントにあった、「思うように人を笑わせられなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた」という一文が、演劇をやっていた時代の自分に身に覚えがありすぎて、他人事とは思えなかったんですよね。
演劇以外でも、僕が10年前にやっていたニコニコ生放送の中でも、ただ目立ちたいがために何も考えずに差別的な発言を安易にしていた時期もありますし、もし当時の記録を残している人がいたとしたら、そして僕が何かの間違いでオリンピック関係者になったとしたら、まず間違いなく炎上するでしょうね。
個人的に、小林賢太郎さんは、日本のお笑い芸人が陥りがちなパワハラ的なネタには決して進まず(というか、途中で考えをあらためたのかなと)、笑いと舞台表現の新たな可能性を切り開いた人格者だと思っています。
そんな人でも(当時はまだ若かったとはいえ)間違うことはあるということ、それが時代の変化とともに問題視されることもあるということ、そういう方向でこの問題を重く受け止めることにしました。
まあ、これ以外にも女性蔑視発言が問題になって東京組織委員会を辞任した森喜朗さんを名誉最高顧問にという案が浮上した問題とか、オリンピックの開会式で過去に差別発言が問題視されたすぎやまこういちさん(個人的に、少なくとも小林賢太郎さんなんかよりずっと差別意識の強い方だと思ってる)の作曲したゲーム音楽を使うことは問題ではないのかとか、そもそもおそらく物凄く不本意な形で東京五輪のセレモニーから外されたMIKIKOさんや椎名林檎さんはどうなのかとか(個人的に気の毒な気持ちと、こんな五輪に関わってほしくなかったという気持ちが両方あり、自分の中では複雑です)、色々言いたいことはありますが、ここまででだいぶ長々と書いてしまったので、そろそろまとめに入りたいと思います。
東京五輪、開催前には様々な問題が浮上し批判も多くあったにもかかわらず、いざ開会式が開催され競技が始まったら、それまであった批判意見よりも盛り上げようというモードになってしまうメディアや、それに流されてしまう人達への疑問はあるものの(個人的にゲームの音楽が使われれば盛り上がってしまう人達はチョロすぎると思ってる)、僕としては「始まったからには楽しもう」という気持ちにはなれません。
寧ろ、本来中止にするべきだった(と、少なくとも僕は思っている)東京五輪が開催されてしまった以上、この機会に日本の政治や社会全体の、パワハラや人権意識の低さやアスリートやアーティストへの不配慮やメディアのジャーナリズム軽視やコロナ対策の不十分さなどの問題点が、世界が日本に注目されているこの機会にどんどん海外のメディアに取り上げられ、日本が本来受けるべき批判を受け、それで日本がいい方向に変わっていくきっかけになればいいなと思います。
それにしても、コロナ禍でオリンピックに限らず色んなものの今まで隠されていた問題点が露見したと思っていますが、逆にコロナ禍がなかったら実際はここまで問題だらけでしかないオリンピックにみんな騙されて盛り上がっていたのかと思うとそれはそれで恐ろしいと思うので、そういう日本社会というか国民性?の危険な部分にも、もうちょっと一人一人が目を向けるきっかけにもなればいいかな、なんてことも思いました。
ところで先程、オリンピックが始まったらみんないじめ問題なんて忘れてしまうのではないか…なんて書きましたが、そうではない人達がいました!
それは、プロインタビュアーの吉田豪さんと、ニュースサイトTabloの編集長の久田将義さんが、「噂のワイドショー」というネット配信番組で、オリンピックの小山田圭吾さんの問題を扱っていたのですが、なんと、その配信をオリンピックの開会式の真裏でやっていたのです!
こちらの動画です。
この中で、開始37分くらいで登場する、吉田豪さんの「いじめの問題でややこしいのは、いじめられた側はプライドがあるからいじめられたって認めたくないし言いたくない、いじめた側はいじめた過去を忘れる。だからいじめのデータを集めるのは難しい」という言葉が的確だと思いました。
そんな吉田豪さんの話を聞いて思い出した、自分がいじめられた時の体験があったので、最後にそれを書いて終わろうと思います。
僕は中学1年生の時にいじめられていたのですが、ある日、僕がキレて教務室(新潟方言)に乗り込んで担任に直訴していじめの実態を訴え、担任に学級会を開いてもらい、クラス全員の前で自分がいじめられていた事実を一人でひたすら話したら、いじめられなくなった、という体験がありました。
これ、吉田豪さんが言うところの「いじめられていた人間はその事実を認めたがらない」の真逆の行為だったと思うのですが、こうやっていじめの実態を「公然の事実」にしてしまったことって、今思うとすごく効果があったと思うんですよ。
いじめって狭くて閉鎖的な人間関係の中だから成立するところがあって、いじめを公然の事実にしてしまうと、それまでいじめていた奴らに対して批判的な目が集まり、彼らがカッコ悪いみたいな「空気」が周りにできてしまい、いじめが成立しなくなるんですよね。
いじめって、「こいつはいじめていい」みたいな「空気」で成立するところがあり、いじめっ子って「空気」を異様に気にするから、逆に空気を変えて、空気を味方に付けてしまうと、いじめがなくなることもあるんだなという。
それに、これは自分が「空気が読めない」人間だったからこそできたことなのかな、なんてことも思ったりしました。
というのも、「担任を味方につける」「学級会でクラス全員の前で話す」っていうのは、「いい子ちゃん」みたいで逆にカッコ悪いみたいな「空気」があったんですよ。
でも、いじめから逃げる時に空気なんて読まなくていいと思います。
空気を読んでいたらあのまま何も抵抗できなかったかもしれませんが、空気を読まなかったからこそ、いじめを撃退できたのかなと今では思います。
当時はそんなことは何も考えずにやっていましたが、暴力を使わないすごく平和的な正攻法でいじめを撃退していたんだなと思うと、あれは成功体験だったと思います。
ま、そんな感じで長くなりましたが、「オリンピックが盛り上がっている時に批判して水を差すな」みたいな「空気」が日本にできつつあるとしても、意見を表明する時に「空気」なんて読まなくていいと思います。(うまくまとめたつもり!)
少し前まで、たかがTwitterで政治や社会問題などに対して意見をつぶやいたところで何の意味があるんだ…という気持ちがどこかにあったのですが、その番組を見て、たとえツイートでもリアルタイムでつぶやいた言葉が歴史の記録になるんだなと思いました。
それで、やっぱりその時にしかつぶやけない言葉ってあると思うので、最近は意識して世の中に対して思った気持ちを積極的につぶやくようにしています。
特に、新型コロナウイルス禍に突入した去年からは、その時代の自分を記録するという意味で、Twitterやブログを今まで以上に積極的に使うようになりました。
そして今は、様々な問題や賛否両論を抱えたまま始まった東京オリンピックに対して、思うことを意識的につぶやくようにしています。
というわけで、あまり政治のことは書かないブログですが、せっかくなので忘れないうちにここ最近の気持ちをまとめておこうと思います。
ちなみに、僕が政治のことを考えるようになった経緯や、東京オリンピックに対する気持ちは、こちらの記事にまとめてあるので、もしよかったら見てみてください。
「政治について考えることと、自分自身と向き合うこと。」
軽く説明すると、僕は東京オリンピックが決定した直後から、「復興五輪」と言いながら、当時の安倍首相の「アンダーコントロール」という虚偽スピーチのように、被災地の復興よりも東京オリンピックを優先させるような政府の方針には疑問しかありませんでした。
しかし、2016年のリオオリンピックの閉会式で安倍首相がマリオの格好をして登場するセレモニー(僕の好きな椎名林檎さんやMIKIKOさんや中田ヤスタカさんも関わっていた)も素直に喜べない複雑な気持ちがあり、しかし日本のメディアもTwitterも結局盛り上がってしまったことに対する疑問もありました。
また、アスリートファーストと言いながらも、猛暑の開催時期や、トライアスロン会場の東京湾の水質汚染など、とてもアスリートを大事にしているとは思えないやり方にも疑問がありました。
それ以外にも、五輪を強行しようとする日本の方針にはずっと疑問があった中、コロナ禍が始まり、感染拡大を防ぐために中止するべきだという気持ちになりました(こういう人は多いのかなと思います)。
そんな感じで、東京五輪は招致の段階から現在にまで問題がありすぎだと思いますが、ただ考えてみればアスリートの人達も、別に東京五輪だからというより2020年に(結果的に2021年だったけど)オリンピックがあるなら開催地がどこだろうが出たかっただろうし、たまたま今回出たのがこんなオリンピックで気の毒だなという気持ちがあるので、アスリートの人達を責めたくはありません。
また、純粋にスポーツを応援している人達だって今回の東京五輪に反対したり疑問を持ってる人達は多いだろうし、僕は東京五輪には反対ではあるけれど、それはさておきスポーツファンの人達は本当につらいだろうし、気の毒だと思っています。
そんな中、東京五輪が始まるまでの一週間ほどで、開会式・閉会式の人事を巡る辞任・解任が相次ぐという出来事が起こりました。
せっかくなので、開会式までの、7/20(火)~23(金)の4日間に新潟日報の一面に載っていたオリンピック関連の記事を、一通り紹介しておきます。




7/15(水)、開会式、閉会式に関わる新たなアーティスト達が報じられましたが、その中の一人、コーネリアスの小山田圭吾さんが、20年ほど前にロッキンオンジャパン、クイックジャパンでのインタビューの中で、いじめ自慢ともとれる発言をしていたことがSNSを中心に指摘され、批判が集まり炎上するという出来事がありました。
小山田圭吾さんのこの記事は、知っている人達の中では有名で過去にも問題視されていたということですが、東京五輪によって今まで以上に注目を集めたことで初めて知った人達からも批判された、ということのようです。
(実際僕も、小山田圭吾さんに関しては、小沢健二さんとやっていたフリッパーズ・ギターの「恋とマシンガン」を知っている程度の人間で、このインタビューもこの機会に初めて知りました。)
(とは言え、昨年読んだ「ポスト・サブカル焼け跡派」という日本の音楽を中心としたサブカルチャーを評論している本の中で、フリッパーズ・ギターの小沢健二と小山田圭吾の違い、みたいな文章を読んでいたので、なんとなく腑に落ちる部分もありました。いい本なのでおすすめです!)
これに対して、過去に障害者をいじめ、それをインタビューで自慢していた人間がオリンピックやパラリンピックに関わることを批判する人、そういう少し調べれば分かるようなスキャンダルのある人間を安易に起用するオリンピック委員会を批判する人、そういう記事を掲載した雑誌の方にこそ責任があると批判する人、1990年代当時の人権意識の低さや悪趣味サブカルブームがあった時代背景を考慮して批判するべきだという人、ファンであるからこそショックを受ける人、もともと東京五輪に反対だった気持ちをさらに強める人、炎上が小山田圭吾さんへの過剰なバッシングなのではないかと指摘する人、昔のスキャンダルを今更蒸し返すことに疑問を持つ人…等々、様々な意見が飛び交う、まさに炎上となってしまいました。
こういう色々な意見を見ながら、僕自身はどういう風にこの問題を受け止めるべきか…と考えたのですが、小山田圭吾さんがオリンピックに関わることの是非や、オリンピックのあるべき姿、また当時の記事の検証などは僕なんかよりも適任の専門家の方々がいると思ったので、僕はそういう方向ではなく、これを機に今回の一件だけに限らず、「いじめ」という普遍的な問題について、あらためて自分の頭で考えるきっかけにしたいと思いました。
さて、あの雑誌の内容を信用するならば(と言っても、僕自身は全文読んだわけではなく、ネットニュースに書かれていた部分しか読んでいないのですが)、あそこで語られているのは紛れもなく「いじめ」「いじめ自慢」であり、それはどちらも決して許されない最低の行為であること、それは大前提としてはっきり書いておきます。
時代的な背景もあったとは言え、いじめはいじめであり、誰かを傷つけた過去はどれだけ謝罪、反省したところでなかったことには一生できない重い問題だとも思います。
実際この問題が炎上した翌日にはコーネリアスから公式に謝罪文が出されました。
それに対しては、時間が経ったとはいえ、たとえ形式的にだとしても謝罪文が出されたことは意味があることなのではないか(というか、海外のニュースにまで取り上げられてしまうほど大きな問題になった以上はああするしかないのではないか)、という気持ちと、それでもやっぱり、いじめ被害者の方に謝罪ができていない以上は何も解決していないのではないか、という気持ちが両方ありました。
内容が内容だけに、そしてそれがオリンピックという大きな場で明るみになってしまった以上、批判があって当然だとは誰もが思ったとは思いますが、さすがにここまで袋叩きにしたらそれもかえって小山田圭吾さんに対する新たないじめなのではないかという意見や、キャンセルカルチャーという言葉もネット上では散見されました。
その一方で、いじめとはそのくらい重い問題なのだから決して許されない、という意見も数多く見られました。
僕の気持ちとしては、僕自身いじめられた過去があり、10年、20年も前の出来事なのに思い出して腹が立つこともあるので、そのくらい根深い問題だということは理解できるし、それで小山田圭吾さんを批判している人達の気持ちは理解できました。
しかし、だからと言って、小山田圭吾さんの過去を過剰に蒸し返して批判し続けることには、それはそれで抵抗がありました。
どういうことかというと、確かに僕はいじめれていた人間ですが、同時に無自覚に誰かを傷付けていたことも確実にあるわけで、果たして自分は小山田圭吾さんを批判できるような人間なのだろうか…という気持ちがかなり強くあったのです。
まあ、小山田圭吾さんが語ったいじめくらいひどい行為をしたことはさすがにありませんが、それでも自分の中にも確実に存在する加害性に向き合う行為は、いじめられたトラウマ以上に、僕の中では恐怖を感じるものでした。
完全に清廉潔白な聖人なんていないわけで、おそらく誰もが誰かを傷付けた過去があり、では、そういう過去の過ちと人間はどう向き合えばいいのか、いつまで向き合い続ければいいのか、そう考えると簡単に答えの出ない問題だと思ってしまいました。
僕が過去に傷付けてしまった人は今でも僕のことを恨んでいるのかもしれない、そうなった以上、僕はいつまでこの問題を考え続ければいいのか、どれだけ反省、謝罪し続ければいいのか。
もしかしたらどんなに謝っても向こうは決して自分を許さないかもしれない、それでも自分は自分の人生を精一杯これからも生きていくしかない、その一方で自分が誰かを助けたり感謝されたりすることもあるという、人間は簡単に善悪では分けられない、複雑な存在なんだな、ということです。
誰かをいじめていた過去を忘れて、いじめられていた側がいつまでも恨んでいることも知らずに、幸せな人生を送っている人達なんて大勢いるわけで、でもその人達にだって幸せになる権利はあるはずだし、その幸せは誰にも奪えないという、いじめ問題は長い目で考えると本当に何が正解なのか分からなくなってしまう、本当に複雑な問題だと思ったのです。
そう考えると、いじめ問題は誰だって被害者にも加害者にもなりうる、誰もが当事者である本当に大きな問題だと思うし、もしかしたら人類が生きている以上、永遠に解決しない難しい問題かもしれません。
そしてこの問題は、オリンピックが始まろうが終わろうが、成功しようが失敗しようが、小山田圭吾さんが今後どうなろうが、ずっと続いていく問題なので、せめてこの機会にいじめ問題について真剣に考えてくれる人が一人でも増えてくれればいい、そのことでいじめに苦しむ人が一人でも多く減ればいい、と思いました。
でも、インターネットの炎上騒ぎって結局流行みたいなところがあるから、一時的に小山田圭吾さん一人だけを蒸し返しても何も変わらないのではないか、炎上して時間が経ったらみんな忘れてしまうというお馴染みのパターンになってしまうのではないか、小山田圭吾さんを批判していた人達の中で今後もいじめ問題を考え続けてくれる人が何人いるだろうか、などと考えてしまいました。
なので、せめて自分は、これ以上人を傷付けてしまわないように気を付けよう、やってしまったら謝ろう、発言には気を付けよう、今は笑えると思っていることも将来価値観が更新されれば問題になることもあるから気を付けよう、という方向で考えることにして、小山田圭吾さん一人を過剰に批判するのはやめました。
今はオリンピックのことがあるから騒がれているいじめ問題ですが、オリンピックが終わったあともずっと続いていく大きな問題だと思うので、僕はオリンピックよりもそっちを考えたいなと思ったからです。
そして個人的に僕は今回のオリンピック開催には反対ではありつつもオリンピック自体には大して興味がないし、小山田圭吾さんに対してもあまり興味がないのです(だって他人だし)。
ちなみに、僕はいつもわりとこういうスタンスで、少し前にナインティ・ナインの岡村隆史さん風俗嬢に関する女性蔑視的な発言で炎上した時も、無自覚な女性差別がなくなればいいなとは思いましたが、岡村隆史さんには別に怒らなかったし、彼が反省したかどうかとかは大して興味もありませんでした(だって他人だし)。
誰かが問題を起こして炎上した時は、その人を批判するよりも、自分自身の身に置き換えて、反省したり気を付けよう、という方向で考えるという、要するに「人の振り見て我が振り直せ」のスタンスです、僕は。
小山田圭吾さんが辞任した直後に、今度は小林賢太郎さんが解任になった時も、同じようなことを思いました。
一応書いておくと、小林賢太郎さんの場合は、本当にまだ無名の若手芸人だった時代の問題発言であること、それをとあるメディアがこのタイミングで掘り返して炎上させたこと、それを陰謀論者っぽい人が防衛副大臣に伝え、服防衛大臣が組織委員会の中で話し合うより前にユダヤ人の団体にリークし、いきなり解任になってしまったこと、等々、色々な問題がありすぎるので、小山田圭吾さんの時の問題とは違うとは思いつつも、それでもまあ、そっちの方は僕なんかよりも適任な方が検証してくれると思うので、僕はあくまで自分の意見を書いていきます。
個人的に、今回問題になった、小林賢太郎さんがラーメンズ時代にやったコントに登場した「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」は知りませんでしたが、個人的にNHKの「爆笑オンエアバトル」が好きでラーメンズも見ていた人間なので、例えば当時やっていた他のコントに出てきた「ホモ」や「不法滞在っぽい外国人」を使ったネタも、今の倫理観ではアウトだよなと思ったりしました。
今では普通に「あり得ない」と思うことも10年前は自分も特に疑問も持たずにネタにしていたこともあるし、小山田圭吾さんが批判された時はその背景にあった90年代の悪趣味サブカルブームが話題となりましたが、どの時代にもこういう無自覚な差別的な表現はあるし、時代の変化とともに間違いに気付き、価値観が更新されることを受け入れていきたいと思いました。
また、小林賢太郎さんが解任された時のコメントにあった、「思うように人を笑わせられなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた」という一文が、演劇をやっていた時代の自分に身に覚えがありすぎて、他人事とは思えなかったんですよね。
演劇以外でも、僕が10年前にやっていたニコニコ生放送の中でも、ただ目立ちたいがために何も考えずに差別的な発言を安易にしていた時期もありますし、もし当時の記録を残している人がいたとしたら、そして僕が何かの間違いでオリンピック関係者になったとしたら、まず間違いなく炎上するでしょうね。
個人的に、小林賢太郎さんは、日本のお笑い芸人が陥りがちなパワハラ的なネタには決して進まず(というか、途中で考えをあらためたのかなと)、笑いと舞台表現の新たな可能性を切り開いた人格者だと思っています。
そんな人でも(当時はまだ若かったとはいえ)間違うことはあるということ、それが時代の変化とともに問題視されることもあるということ、そういう方向でこの問題を重く受け止めることにしました。
まあ、これ以外にも女性蔑視発言が問題になって東京組織委員会を辞任した森喜朗さんを名誉最高顧問にという案が浮上した問題とか、オリンピックの開会式で過去に差別発言が問題視されたすぎやまこういちさん(個人的に、少なくとも小林賢太郎さんなんかよりずっと差別意識の強い方だと思ってる)の作曲したゲーム音楽を使うことは問題ではないのかとか、そもそもおそらく物凄く不本意な形で東京五輪のセレモニーから外されたMIKIKOさんや椎名林檎さんはどうなのかとか(個人的に気の毒な気持ちと、こんな五輪に関わってほしくなかったという気持ちが両方あり、自分の中では複雑です)、色々言いたいことはありますが、ここまででだいぶ長々と書いてしまったので、そろそろまとめに入りたいと思います。
東京五輪、開催前には様々な問題が浮上し批判も多くあったにもかかわらず、いざ開会式が開催され競技が始まったら、それまであった批判意見よりも盛り上げようというモードになってしまうメディアや、それに流されてしまう人達への疑問はあるものの(個人的にゲームの音楽が使われれば盛り上がってしまう人達はチョロすぎると思ってる)、僕としては「始まったからには楽しもう」という気持ちにはなれません。
寧ろ、本来中止にするべきだった(と、少なくとも僕は思っている)東京五輪が開催されてしまった以上、この機会に日本の政治や社会全体の、パワハラや人権意識の低さやアスリートやアーティストへの不配慮やメディアのジャーナリズム軽視やコロナ対策の不十分さなどの問題点が、世界が日本に注目されているこの機会にどんどん海外のメディアに取り上げられ、日本が本来受けるべき批判を受け、それで日本がいい方向に変わっていくきっかけになればいいなと思います。
それにしても、コロナ禍でオリンピックに限らず色んなものの今まで隠されていた問題点が露見したと思っていますが、逆にコロナ禍がなかったら実際はここまで問題だらけでしかないオリンピックにみんな騙されて盛り上がっていたのかと思うとそれはそれで恐ろしいと思うので、そういう日本社会というか国民性?の危険な部分にも、もうちょっと一人一人が目を向けるきっかけにもなればいいかな、なんてことも思いました。
ところで先程、オリンピックが始まったらみんないじめ問題なんて忘れてしまうのではないか…なんて書きましたが、そうではない人達がいました!
それは、プロインタビュアーの吉田豪さんと、ニュースサイトTabloの編集長の久田将義さんが、「噂のワイドショー」というネット配信番組で、オリンピックの小山田圭吾さんの問題を扱っていたのですが、なんと、その配信をオリンピックの開会式の真裏でやっていたのです!
こちらの動画です。
この中で、開始37分くらいで登場する、吉田豪さんの「いじめの問題でややこしいのは、いじめられた側はプライドがあるからいじめられたって認めたくないし言いたくない、いじめた側はいじめた過去を忘れる。だからいじめのデータを集めるのは難しい」という言葉が的確だと思いました。
そんな吉田豪さんの話を聞いて思い出した、自分がいじめられた時の体験があったので、最後にそれを書いて終わろうと思います。
僕は中学1年生の時にいじめられていたのですが、ある日、僕がキレて教務室(新潟方言)に乗り込んで担任に直訴していじめの実態を訴え、担任に学級会を開いてもらい、クラス全員の前で自分がいじめられていた事実を一人でひたすら話したら、いじめられなくなった、という体験がありました。
これ、吉田豪さんが言うところの「いじめられていた人間はその事実を認めたがらない」の真逆の行為だったと思うのですが、こうやっていじめの実態を「公然の事実」にしてしまったことって、今思うとすごく効果があったと思うんですよ。
いじめって狭くて閉鎖的な人間関係の中だから成立するところがあって、いじめを公然の事実にしてしまうと、それまでいじめていた奴らに対して批判的な目が集まり、彼らがカッコ悪いみたいな「空気」が周りにできてしまい、いじめが成立しなくなるんですよね。
いじめって、「こいつはいじめていい」みたいな「空気」で成立するところがあり、いじめっ子って「空気」を異様に気にするから、逆に空気を変えて、空気を味方に付けてしまうと、いじめがなくなることもあるんだなという。
それに、これは自分が「空気が読めない」人間だったからこそできたことなのかな、なんてことも思ったりしました。
というのも、「担任を味方につける」「学級会でクラス全員の前で話す」っていうのは、「いい子ちゃん」みたいで逆にカッコ悪いみたいな「空気」があったんですよ。
でも、いじめから逃げる時に空気なんて読まなくていいと思います。
空気を読んでいたらあのまま何も抵抗できなかったかもしれませんが、空気を読まなかったからこそ、いじめを撃退できたのかなと今では思います。
当時はそんなことは何も考えずにやっていましたが、暴力を使わないすごく平和的な正攻法でいじめを撃退していたんだなと思うと、あれは成功体験だったと思います。
ま、そんな感じで長くなりましたが、「オリンピックが盛り上がっている時に批判して水を差すな」みたいな「空気」が日本にできつつあるとしても、意見を表明する時に「空気」なんて読まなくていいと思います。(うまくまとめたつもり!)