取付け段階です。

間違いなくここが一番重要です!
先輩から教えてもらいましたが、「隙間から水が染み出るようではダメ」とのこと。

指で思いっきり圧着して・・・・

塩ビテープで圧着しながら、ひとつひとつ丁寧に巻いていきます。
これを150個分、とても手の掛かる作業ですが、やらないと成功も失敗も見えません。
繰り返しになりますが最も大切なのは、上下のコア同士の密着です。

一個のコアを密着をさせたら、次は直列方向の密着。
今回の本来の目的はここにありますので、直列方向の密着をないがしろにすることはできません。
つづく。















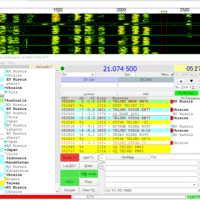




早速ですが、JRCさんの真似をしてクランプコアを屋外の同軸に装着しようと思っていますが、保護テープをどうするか迷っています。ビニテだと剥がれてきてしまう気がしますが、その後いかがですか?耐候性も考えると自己融着テープかなとも思っているのですが・・・お金が・・・
こんにちは。いつもありがとうございます。クランプコアは本当に重宝します。個人的には保護テープは必要ないと思っています。もう二年ほど屋外にそのままの状態でおいてあるコアもありますが、殆ど問題ない状態です。記事の写真のテープは保護用ではなく、TDK製のコアをケースから外して(つまり半円コアをふたつ取り出して、それをテープでぴったりくっつけている様子なんです) ただしこのやり方は、テープが緩んできますので全くおすすめできません。それよりもオリジナルのケースに入ったままの状態で、インシュロックで思いっきり締め付けることを強くお勧めします。パッチンと挟んだだけでも勿論効果を発揮するのですが、いかに隙間を無くすかがポイントのようです。高周波分野の私の恩師からは「コアの間に思いっきり水を流して(つまりホースのように)、コアの外側に水がにじむようではダメ!」と教わりました。確かにそのままパッチンとした状態と、締め付けた場合では阻止量が増えます。1個や2個ならともかく数十個や私のところのように200個という数量の場合にはトータルで効いて来ます。余談になりますがコアはTDK製品がやはり良いと思います。廻し者ではないのですが、SEIWAかTDKかなと思います。TDKのコアの場合ですと、秋葉原の晴恒というところが私の知る限り最安です。またいつでも御連絡下さい。
参考になりました。SEIKOも安いですね。
ついでにもう一つ教えてください。
コモンモード電流は同軸のどの位置で測定されていますか?私は大進のRF電流計を使っていますが、同じ同軸上でも場所を少し変えただけで電流値が大きく変わります。CMFの直後は小さいのですが、CMFから離れるに従って大きくなり、皆さんの値がどの位置で測定されたのか教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、少し場所を変えただけで値が大きく変化しますね。私の場合は、全てリグの出口の直近で測定しています。(記事の内容もそれに基づいています)これは単純に測定しやすいというのがその理由です。周波数や周囲との相関関係によって、同軸上のRF電流計を動かしながら測定してくると、何度も腹の部分や底の部分が出てくると思います。これに加えて、例えば給電点近くに10個ほど入れれば、先ほどまで電流の腹だったところが逆に底になったり・・・・こんなことを繰り返しているうちに、私の場合は全部覆っちゃおう!ということになりました。
私だけ測定方法に誤りがあるのかずっと心配でした。
大変参考になりました。ありがとうございました。FB DX!
全区間をまんべんなく測定して、カット&トライというのでしょうか、特に電流値の大きい場所にコアを連装して、更にそれ以外の場所を測定していくというやり方が良いかと思います。正の1/4波長にあたる部分や、短縮率を含めた1/4波長の部分などがどのような値を示すのかなども測定されて装着されるのが良いかも知れません。