
名前はよっく知っていたけど、実は初訪問の建仁寺。→サイト
本坊、高台寺や龍安寺とよく似ている。(写真だけ見てると区別がつきづらい

特別公開の塔頭を訪れながら、通常でも公開されている方丈の方も拝観した。
帰った直後に観たせいかもしれないけど、
たぶん、この前の大河ドラマ「江」の第4回でロケに使われていたかも。
雰囲気は鎌倉の建長寺に似ているようにも感じる。

↑法堂。天井画の双龍図が見応えあり。
方丈は中は拝見できるけど、屋根の葺き替え工事中。


小書院と庭、大書院といい雰囲気。
ここでも風神雷神図を見かけた。(←正月あけに光琳のを東博でみたので)
俵屋宗達のはココが所蔵だったのネ。
復元品の展示だったけど、ん~光ってる。
(以前、東博「対決!」でホンモノを観たけど、もっと暗かったような。。。こちら
お目当ての茶室「東陽坊」も拝見。


露地もいい感じ。茶事ともなれば枝折戸がつけられるのかなぁ。

蹲踞の前の大きな石(柱の礎石の再利用?)は“待ち石”かなぁ。(←この表現は正しくないと思うけど )
)


吸い込まれそうな躙口。茶席は二畳台目の下座床。
長次郎茶碗に「東陽坊」という銘の黒楽があるけど、意味は考えたことがなかった。
(ちなみに、茶釜もあるそうです)
茶道大辞典に解説と間取り図あり。
真如堂にあった塔頭の名前だったのねぇ。
その塔頭・東陽坊に住んでいた長盛サンが北野大茶湯のときにつくったものと伝えられ、
北野の高林寺にあったのを移転を重ねて、明治時代に建仁寺へ移築されたとか。
さらに、大正になって現在の位置に落ち着いたとのこと。
北野かぁ。。。
実はこの前日、北野天満宮もちょこっと行った。


点と点が線につながったみたいでウレシイ。
で、黒楽の「東陽坊」は長盛サンが所持していたからで、利休さんの門人だったらしい。
辻与次郎作の「東陽坊釜」は利休さんから長盛サンに贈られた茶釜だそうで。
ほー。そういうことだったのかぁ。
黒楽「東陽坊」は個人蔵だし、たぶんまだ見たことないと思う。
でもさー、如庵もそうだけど、茶室を移築しちゃうって、スゴイなぁ。
お城とか寺院の建物も昔から移築した話って、よく聞くけど、そんな特別なことではないのかなぁ。

水屋側もいい感じ。
そういえば、ここでは月釜が催されている。毎月5日だっけ。詳細はこちら。
真如堂の月釜(第2日曜)をセットで紹介されているのは、長盛サンつながりだったのかぁ。
建仁寺の月釜は行ったことないけど、真如堂の方はある。
今は電話で事前に予約みたい、だね。
それから建仁寺といえば、毎年4月20日の四頭茶会が有名だなぁ。
行ったことないけど。

にほんブログ村
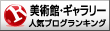 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
応援ヨロシク 致しマス
致しマス
本坊、高台寺や龍安寺とよく似ている。(写真だけ見てると区別がつきづらい


特別公開の塔頭を訪れながら、通常でも公開されている方丈の方も拝観した。
帰った直後に観たせいかもしれないけど、
たぶん、この前の大河ドラマ「江」の第4回でロケに使われていたかも。
雰囲気は鎌倉の建長寺に似ているようにも感じる。

↑法堂。天井画の双龍図が見応えあり。
方丈は中は拝見できるけど、屋根の葺き替え工事中。


小書院と庭、大書院といい雰囲気。
ここでも風神雷神図を見かけた。(←正月あけに光琳のを東博でみたので)
俵屋宗達のはココが所蔵だったのネ。
復元品の展示だったけど、ん~光ってる。
(以前、東博「対決!」でホンモノを観たけど、もっと暗かったような。。。こちら
お目当ての茶室「東陽坊」も拝見。


露地もいい感じ。茶事ともなれば枝折戸がつけられるのかなぁ。

蹲踞の前の大きな石(柱の礎石の再利用?)は“待ち石”かなぁ。(←この表現は正しくないと思うけど
 )
)

吸い込まれそうな躙口。茶席は二畳台目の下座床。
長次郎茶碗に「東陽坊」という銘の黒楽があるけど、意味は考えたことがなかった。
(ちなみに、茶釜もあるそうです)
茶道大辞典に解説と間取り図あり。
真如堂にあった塔頭の名前だったのねぇ。
その塔頭・東陽坊に住んでいた長盛サンが北野大茶湯のときにつくったものと伝えられ、
北野の高林寺にあったのを移転を重ねて、明治時代に建仁寺へ移築されたとか。
さらに、大正になって現在の位置に落ち着いたとのこと。
北野かぁ。。。
実はこの前日、北野天満宮もちょこっと行った。


点と点が線につながったみたいでウレシイ。
で、黒楽の「東陽坊」は長盛サンが所持していたからで、利休さんの門人だったらしい。
辻与次郎作の「東陽坊釜」は利休さんから長盛サンに贈られた茶釜だそうで。
ほー。そういうことだったのかぁ。
黒楽「東陽坊」は個人蔵だし、たぶんまだ見たことないと思う。
でもさー、如庵もそうだけど、茶室を移築しちゃうって、スゴイなぁ。
お城とか寺院の建物も昔から移築した話って、よく聞くけど、そんな特別なことではないのかなぁ。

水屋側もいい感じ。
そういえば、ここでは月釜が催されている。毎月5日だっけ。詳細はこちら。
真如堂の月釜(第2日曜)をセットで紹介されているのは、長盛サンつながりだったのかぁ。
建仁寺の月釜は行ったことないけど、真如堂の方はある。
今は電話で事前に予約みたい、だね。
それから建仁寺といえば、毎年4月20日の四頭茶会が有名だなぁ。
行ったことないけど。
にほんブログ村
応援ヨロシク
 致しマス
致しマス






























その家は、当然、世に知られた家で、年に1回、茶会が開催されまが、楽さんが半東をされます。
いつも、展観で出してくれないかな~と思ってはいますが、なかなか出さないでしょうね。
鳥取にあるのですかぁ。
あの境港のお茶会のおうちですね。
手元の資料にも「東陽坊」の写真すらなくて、でも名前だけは聞いたことがあるので、不思議だなぁと思っていたのですが、
謎が解けました。
時流庵さん
まだ露地の勉強まで進んでなくて。
(blog書くのにいっぱいっぱいで)
茶事の折り、席入りで「前のヒトが蹲踞を使っている時は、あの大きな石でなんとなく待機しなさい」と教わったので、つい「待ち石」を勝手に呼んでますぅ。