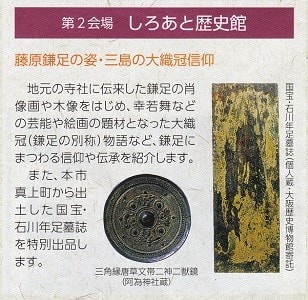
今城塚古代歴史館としろあと歴史館で共同開催している、「藤原鎌足と阿武山古墳」展。今回は、そのしろあと歴史館の方の展示を見てきましたので、私なりに理解した事をアップ致します。
コチラの展示は、古文献や絵図、木像などが展示の中心で、土から出た発掘品が中心の今城塚とは雰囲気が異なりますね。展示は4つのテーマに分けられており、個人的には、主に茨木市に鎮座する鎌足ゆかりの古社、古寺や遺跡、それらにまつわるエピソードや伝来品に関心が行きました。
1、藤原鎌足の生涯
こちらのコーナーでは、鎌足の生涯を、中世から大正時代までの様々な時代に出版された資料の記述をつないで振り返るという企画。資料は、日本書紀の江戸時代の版本、大和や西国の名所図会、大織冠公伝、多武峰縁起、そして尋常小学校の歴史教科書などです。
その中で面白かったのが、やはり乙巳の変の、例の入鹿を襲うシーンが、江戸時代の名所図会や、同じく江戸時代の百科事典である永代節用無尽蔵、そして尋常小学校の教科書などに、わざわざイラストで掲載されてた事。このシーンの伝搬力、ビジュアルにイメージしたくなるインパクトの大きさが感じ取れます。現代日本人のDNAになってしまった、と言えるくらいでは。
2、描かれた藤原鎌足
鎌足を描いた絵図、掛け軸を集めた展示はなかなか壮観でした。自身が祭神である談山神社蔵が多いのは納得ですが、我らが摂津三島、茨木市のお寺、地福寺や大念寺でも多武峰曼荼羅図が伝来しており、展示されていました。この曼荼羅とは、鎌足を中心に、右手前に長男の定慧(じょうえ)、左手前に藤原不比等を描いた、おそらく一番よく見かける絵で、多数のバージョンが有るのです。
一部写真展示だったものが、11月2日か3日(うろ覚えです)以降には現物展示されるとの事。ご興味ある方は、そのタイミングで見に行かれたら良いと思います。
3、大織冠物語
藤原鎌足には死の間際に、最高位の冠位である大織冠が授けられましたが、結局鎌足がその唯一の人になったので、大織冠が彼の代名詞となっています。それで、室町時代から江戸時代前期に流行した芸能幸若舞に、なんと鎌足自身が主人公となる「大織冠」の名の演目が存在し人気があったそうです。その主なシーンを表現した絵本や、さらに美しい屏風まで存在し、展示されていました。
ストーリーは、しろあと歴史館の展示や、企画展図録に紹介されていますので、そちらを見ていただくとして、物語はあくまでフィクションで史実とは関係しませんが、そういう物語の主人公ということは、まさに庶民のヒーロー。江戸時代にあっても、そのくらい大きい存在だったという事でしょう。
江戸時代の中期以降は、幸若舞は歌舞伎や人形浄瑠璃に取って代わられますが、これら新たな芸能にも大織冠の話は取り込まれていったようです。
4、三島の大織冠信仰
元々、藤原鎌足と摂津三島のつながりを伝える故事は2つ。祭祀を担う神衹伯への就任を固辞し「三島別業」に隠遁したこと、そして、死去した後の亡骸がまず阿威山(今の茨木市安威地域)に埋葬されたが、長男の定慧が掘り起こして多武峰に改葬したこと、です。これにちなんだ、安威地域の古地図や、ゆかりの古社、古寺に伝来する品々が展示されているコーナーです。
・阿為神社
中臣氏一族、中臣藍連の居住地だった場所に立つ、延喜式神名帳にも記載されている神社。鎌足の亡骸を多武峰に改葬した後、その代わりとして、この阿為神社の社宝となった三角縁唐草文帯ニ神二獣鏡が展示されていました。
・大織冠神社
ここが鎌足の古廟とされた将軍山一号墳で、中に鎌足を祀った社が鎮座しています。今は阿為神社が管理しているそうです。
・大念寺
病に伏せていた鎌足が夢の中でお告げを得て、師事していた僧の慧隠を開祖として建立された善法院が元。16世紀末に浄土宗の大念寺として再興したとのこと。18世紀に寺の第十世、練誉(れんよ)が古くからの伝承をまとめた「摂州島下郡阿威山大織冠堂縁起並序」が展示されていましたが、そこには、鎌足の長男とされている定慧が実は孝徳天皇の子だと書かれています。そして、その高貴さ故、開祖の座を定慧に譲ったのだと云います。定慧の血筋については、東出雲伝承でも同じ事が言われています。つまり、孝徳帝が軽皇子の頃から仕えていた鎌足は、既に皇子を身ごもった妃候補を自身の妃として与えられたという事です。鎌足は感激して有難がったと、「飛鳥文化と宗教争乱」に書かれています。
・地福寺
寺伝では、慧隠を開祖として鎌足によって創建されたとしています。多武峰曼荼羅図が2点と、それを立体化した木像が伝来しており、展示されていました。
現在の地は安威川ダム建設で移転した所ですが、鎌足がここで過ごしていた当時、東の阿武山の山頂にある光明石が輝くのを見て、蘇我氏を討つ事を決断した事を伝える、「桑原山地福寺縁起」も展示されています。
大織冠信仰は、談山神社や多武峰周辺の集落、奈良市の興福寺等の大和国が中心なのですが、その他の地域では、藤原氏の一族やそのゆかりの寺社の例はありますが、茨木市の安威地域は地域全体に信仰が伝わる稀有な例である、と企画展図録で学芸員の千田康治氏がまとめられていました。
なお、タイトル図の右に記載有るのは、奈良時代に活躍した石川年足の事績を記した墓誌です。摂津国真上村で江戸時代に発見されたもので国宝。。。詳しくは現地でご覧ください。
歴史上の有名人の一人、藤原鎌足との深いゆかりが、茨木市を中心にしたこの摂津三島にあることが改めて認識できて、とても良かったと思っています。



























