
―表象の森― 空豆の巻
安東次男の「風狂始末-芭蕉連句評釈」による芭蕉の歌仙めぐりも、この「空豆の巻」をもって掉尾となる。「冬の日」所収の「狂句こがらしの巻」にはじまったのは昨年の1月20日、これまで9つの歌仙、316句を連ねてきたことになる。
「猿蓑」編集を果たした芭蕉は、元禄4年9月膳所の無名庵を出て東下の途につき、10月末には江戸着、細道の旅立から2年7ヶ月ぶりの江戸であった。翌年5月には再興成った芭蕉庵に入っている。同8月に許六入門、9月には膳所から酒堂が下ってきて食客となっている。
6年3月、幼い頃から並々ならぬ愛情をかけてきた猶子桃印-姉の子-が33歳という若さで病没、芭蕉の落胆はよほどのことであったか、7月盆過ぎから約1ヶ月いっさいの客を謝し閉居している。
以後、能役者の宝生暢栄-俳号沾圃-、野坡ら越後屋手代衆、深川茶人衆の杉風一派、彼ら三者三様新風を模索させるべく芭蕉が動き出したのは、同年秋冬の交りからで、翌7年5月にはまたしても西へ上る旅へと。その旅の途上、10月12日大坂で歿した。
歌仙「空豆の巻」を所収する「炭俵」は野坡が主撰者となり、同じ越後屋手代の孤屋と利牛が扶助。元禄6年冬にはじまり、7年6月奥付板。芭蕉指導の歌仙は、夷講・梅が香・空豆の各巻、三歌仙を収める。
・連衆略伝
孤屋-小泉氏、江戸の人、生没年不詳。野坡-寛文2、1662生、当時33歳-より年長か。野坡・孤屋両人共、其角の手ほどきを受けて、貞享3.4年頃ひとまず直門に入ったらしい。彼らが足繁く深川へ通うようになったのは元禄6年の秋以降だが、孤屋・利牛が芭蕉と一座した興行は夷講・空豆の二つしか遺っていない。
岱水-初号苔翠、江戸深川住とのみで生没・経歴詳らかにしない。芭蕉との興行は貞享5年の帰庵以降で、「更級紀行」をほぼその初稿と思われる形で収めて「木曽の谷」-宝永元(1704)年-を編んだ。当歌仙では執筆役か。
利牛-池田氏、江戸の人、生没年不詳。「蕉門諸生全伝」-文政年間-に三井家支配人と記すから、既にこの時期3人の内では上位-番頭-だったのかもしれぬ。「炭俵」以前では其角編「萩の露」-元禄6年刊-に入集1句が知られるのみで、以後元禄末年頃まで句が見られる。
<連句の世界-安東次男「風狂始末-芭蕉連句評釈」より>
「空豆の巻」-01
空豆の花さきにけり麦の縁 孤屋
前書に「ふか川にまかりて」と
次男曰く、空豆の花は仲春から晩春にかけて咲く。葉腋に短い総状花を出し、翼弁に黒い斑紋を一つずつ持った白紫色の蝶形花である。豆類の花で春に咲くのはソラマメとエンドウだけで、ほかは夏咲く。そのせいか「豆の花」-春-という特別の季語がある。尤も、これは何でも観賞にしたがる今の歳時記の話で、江戸時代には「毛吹草」-正保2、1645刊-から「栞草」-嘉永4、1851刊-に至るまで、空豆引く-仲夏-、豆引-晩秋-など生活の季題はあるが、豆の花・空豆の花のようなことばはどの季寄せも採っていない。
句の季は、「麦の縁-へり-」と作っているから「麦」が主であり、初夏の候と知られるが、「空豆の花さきにけり」が気になる。「けり」遣いが、今まで気付かなかった事実に気付かせられた感動をあらわす詠嘆の助動詞だ、とは先にも述べたとおりだが-灰汁桶の雫やみけりきりぎりす-、空豆の初咲ならぬ名残を捉えてわざわざ「花さきにけり」と云っている。
発句は当座に叶った客挨拶という約束に照らして、「ふか川にまかりて」とは芭蕉庵庭先の嘱目だと思うが、空豆の花は葉の青々とした時期には目につきにくく、下葉から黄ばみかける晩春・初夏の候になって、むしろ目にとまるものだ。それにしても、ソラマメの茎丈は50㎝くらい、畝の間では青麦の伸びに隠れて、花も見えにくかったろう。
「空豆の花さきにけり麦の縁-へり-」は、一読、目付平凡、季語の扱いも紛らわしく不束に見えるが、句材の珍しさも与って-ソラマメは桃山・江戸初ごろに中国または南方から渡来した-、けっこう興のある挨拶のようだ。
この空豆がいつから芭蕉庵に植えられていたかわからぬが、嘗て孤屋が初めて深川-旧芭蕉庵-を訪れた時には既にあったのではないか。以来7.8年ぶりに、再興成った芭蕉庵に野坡らとともに指南を請うて通うようになった。往時のあの日あの時のまま青麦と空豆の花が眼前にある、と読めばこの挨拶、格別の興が添うてくる。たぶんそう解してよい、と。















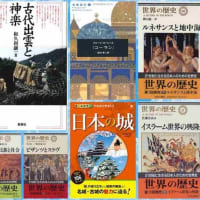




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます