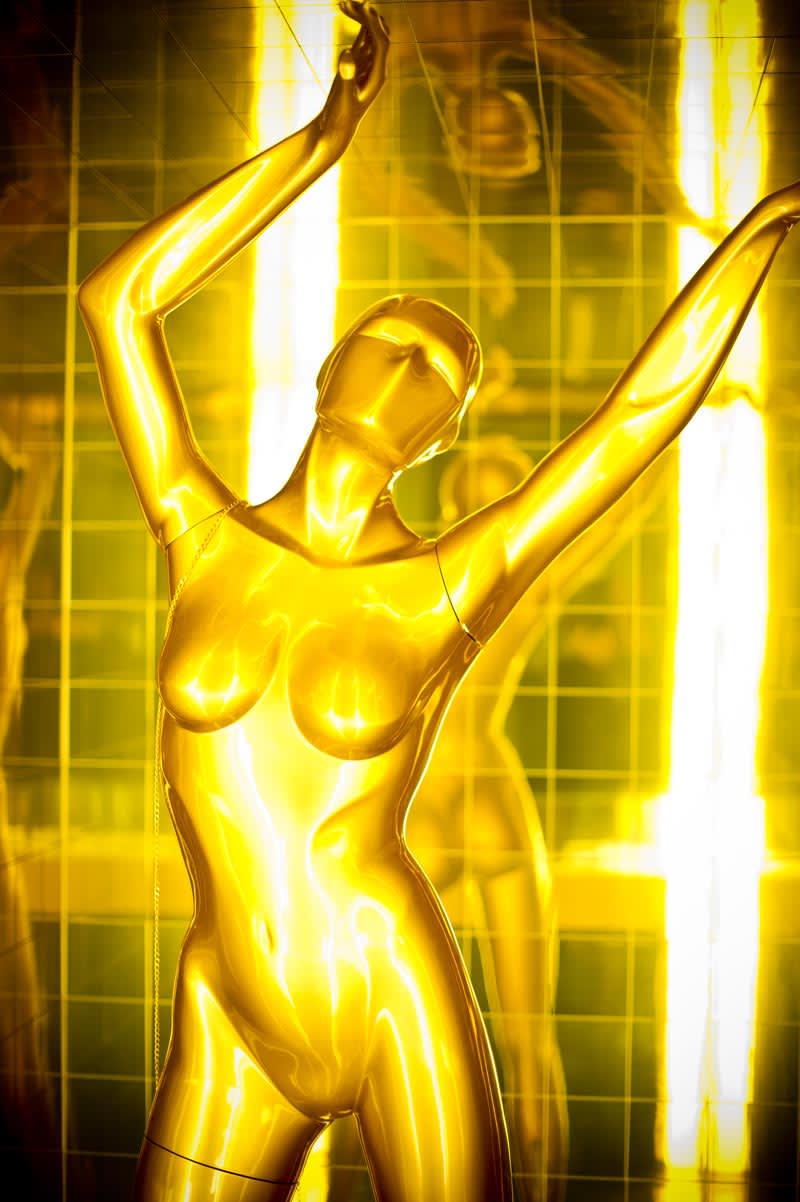あと数時間後に、日本の原子力発電所54基すべてが停止する。
あれだけの人災(もはや取り返しのつかない)を起こしてしまったのだから、当然である。
…それなのに、いまだ日本政府は「脱原発」を将来の指針として明言していない。
さらに電力各社は、夏の電力供給が追いつかないことばかり声高にするだけだ。
なぜ、ニッポンはここまでコトの重大さを棚上げしているのだろう。
内田樹の「他者と死者」を熟読する。
フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスを
同じく哲学者のジャック・ラカンの文献から繙いたものである。
レヴィナスによる人生の請け負い方…といったら良いだろうか。
ユダヤ人であったレヴィナスは、ナチスによるホロコーストを目の辺りにする。
しかし彼は軍事通訳として従軍、フランス軍兵士として捕虜となったために
強制収容所行きをまぬかれ、「ホロコーストの生き残り」として戦後を迎えてしまう。
比較的過ごしやすい収容所生活を送っていたその同じ時期に、
沢山の同胞たちが無惨な死を強いられた…という事実。
「生き残ってしまった…なぜに?」という自問を繰り返すレヴィナス。
その問いかけの徹底が、ドイツの潔さにつながっている…と言い切っても良いと思う。
(「潔さ」とは、ナチスの過ちについての引き受け方としても、原発への指針としても)
デカルトの「コギト(我思う故に我在り)」的存在論を通り越した「存在するとは別の仕方で」という命題。
国家社会主義者たちによって虐殺された六百万人の「死者」への責任を己に問い糾すことで、
自身がいまこの世に存在することの意味を確認する。究極のカタチで。
「無意味に死んだ」同胞たちの死に責務を負い、彼らの分の未来に向けて「最善」を尽くす。
…それはつまり、死者の存在が,自身の存在を相補完していると考える。
無意味に死んだ六百万人の魂は「死者」としてレヴィナスの存在を支えている。
死者が生きたであろう未来に向けて「最善」を尽くす…とは、
今生きている「隣人(他者)」の未来に向けて「最善」を尽くすということである。
ではなにをもって「最善」だと言えるのか?
…そこでレヴィナスは未来から過去への時間軸でもって、その答えを見出す。
「隣人(他者)」に向けて「最善」とはどういうことか?
「死者」の未来に向けて「最善」とはどのように推し量ることなのか?
「死者」がその「最善」の是非によって、自身を罰するのか?
「他者」がその「最善」によって、自身を恨むのか?
しかし、その「最善」を実行しないうちには、その選択が「最善」であったかどうかは伺い知れない。
それでも「最善」を尽くすことが可能なのか?
こうなるともはや「神の御名において」最善を尽くす…としか言えなくなるのではないか…。
結局のところ「死者」や「他者」は「神」と同義なのだけれど、
「神の御名において」最善を…となると、己自身がどう裁かれるか…という
ある種、「神はみている」的戒律への盲従に帰する。
それでは、「死者」や「他者」の未来への責任というのは、懲罰への恐れから来ることになり、
己自身も「死者」に収斂され、その未来への責任を全うすることができない。
だから「存在とは別の仕方で」コトに当たらなければならないのだ。
非常にややこしい話だけれど、存在する存在しないの文脈で
未来への責務を負ってはならない…というのがレヴィナスの人生の請け負い方なのだ。
驚くべきことだが、レヴィナスにおいて、倫理を最終的に基礎づけるのは、
私に命令を下す神ではなく、神の命令を「外傷的(トラウマ)な仕方」で聴き取ってしまった私自身なのである。
(内田樹「死者と他者」)
これだけの内容を1時間やそこらで噛み砕こうとするのが間違いだけれど、
「ホロコースト」も「東日本大震災」も無意味な死を迎えてしまった「死者」に対して
「生き残った」私たちは、その未来を引き受けて「最善」を尽くさなければならないわけで、
思うに、私たちが「生き残った(存在している)」状態とは
常に「死者」の存在が相補的な振る舞いでもって支えていることを肝に銘じなければならない。
それはつまり「他者」たち…浮浪者・政治家・猟奇殺人者をも含めた…とも相補的な関係である…ということ。
この世に存在するとは…アインシュタインの相対性理論と同様、相対的なものなのだ。
この「相対的」という感覚が掴めただけでも、ボクは進歩だと思った。
ボクの存在は「死者」や「他者」と「相対的」である。
「相対的」な視点で物事を眺めてみると、「最善」の理屈も…見えてくるから、不思議だ。
とにかく、これから先の未来は、四次元的思考で捉える。
それが「存在するとは別の仕方」なのだと思う。
あれだけの人災(もはや取り返しのつかない)を起こしてしまったのだから、当然である。
…それなのに、いまだ日本政府は「脱原発」を将来の指針として明言していない。
さらに電力各社は、夏の電力供給が追いつかないことばかり声高にするだけだ。
なぜ、ニッポンはここまでコトの重大さを棚上げしているのだろう。
内田樹の「他者と死者」を熟読する。
フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスを
同じく哲学者のジャック・ラカンの文献から繙いたものである。
レヴィナスによる人生の請け負い方…といったら良いだろうか。
ユダヤ人であったレヴィナスは、ナチスによるホロコーストを目の辺りにする。
しかし彼は軍事通訳として従軍、フランス軍兵士として捕虜となったために
強制収容所行きをまぬかれ、「ホロコーストの生き残り」として戦後を迎えてしまう。
比較的過ごしやすい収容所生活を送っていたその同じ時期に、
沢山の同胞たちが無惨な死を強いられた…という事実。
「生き残ってしまった…なぜに?」という自問を繰り返すレヴィナス。
その問いかけの徹底が、ドイツの潔さにつながっている…と言い切っても良いと思う。
(「潔さ」とは、ナチスの過ちについての引き受け方としても、原発への指針としても)
デカルトの「コギト(我思う故に我在り)」的存在論を通り越した「存在するとは別の仕方で」という命題。
国家社会主義者たちによって虐殺された六百万人の「死者」への責任を己に問い糾すことで、
自身がいまこの世に存在することの意味を確認する。究極のカタチで。
「無意味に死んだ」同胞たちの死に責務を負い、彼らの分の未来に向けて「最善」を尽くす。
…それはつまり、死者の存在が,自身の存在を相補完していると考える。
無意味に死んだ六百万人の魂は「死者」としてレヴィナスの存在を支えている。
死者が生きたであろう未来に向けて「最善」を尽くす…とは、
今生きている「隣人(他者)」の未来に向けて「最善」を尽くすということである。
ではなにをもって「最善」だと言えるのか?
…そこでレヴィナスは未来から過去への時間軸でもって、その答えを見出す。
「隣人(他者)」に向けて「最善」とはどういうことか?
「死者」の未来に向けて「最善」とはどのように推し量ることなのか?
「死者」がその「最善」の是非によって、自身を罰するのか?
「他者」がその「最善」によって、自身を恨むのか?
しかし、その「最善」を実行しないうちには、その選択が「最善」であったかどうかは伺い知れない。
それでも「最善」を尽くすことが可能なのか?
こうなるともはや「神の御名において」最善を尽くす…としか言えなくなるのではないか…。
結局のところ「死者」や「他者」は「神」と同義なのだけれど、
「神の御名において」最善を…となると、己自身がどう裁かれるか…という
ある種、「神はみている」的戒律への盲従に帰する。
それでは、「死者」や「他者」の未来への責任というのは、懲罰への恐れから来ることになり、
己自身も「死者」に収斂され、その未来への責任を全うすることができない。
だから「存在とは別の仕方で」コトに当たらなければならないのだ。
非常にややこしい話だけれど、存在する存在しないの文脈で
未来への責務を負ってはならない…というのがレヴィナスの人生の請け負い方なのだ。
驚くべきことだが、レヴィナスにおいて、倫理を最終的に基礎づけるのは、
私に命令を下す神ではなく、神の命令を「外傷的(トラウマ)な仕方」で聴き取ってしまった私自身なのである。
(内田樹「死者と他者」)
これだけの内容を1時間やそこらで噛み砕こうとするのが間違いだけれど、
「ホロコースト」も「東日本大震災」も無意味な死を迎えてしまった「死者」に対して
「生き残った」私たちは、その未来を引き受けて「最善」を尽くさなければならないわけで、
思うに、私たちが「生き残った(存在している)」状態とは
常に「死者」の存在が相補的な振る舞いでもって支えていることを肝に銘じなければならない。
それはつまり「他者」たち…浮浪者・政治家・猟奇殺人者をも含めた…とも相補的な関係である…ということ。
この世に存在するとは…アインシュタインの相対性理論と同様、相対的なものなのだ。
この「相対的」という感覚が掴めただけでも、ボクは進歩だと思った。
ボクの存在は「死者」や「他者」と「相対的」である。
「相対的」な視点で物事を眺めてみると、「最善」の理屈も…見えてくるから、不思議だ。
とにかく、これから先の未来は、四次元的思考で捉える。
それが「存在するとは別の仕方」なのだと思う。