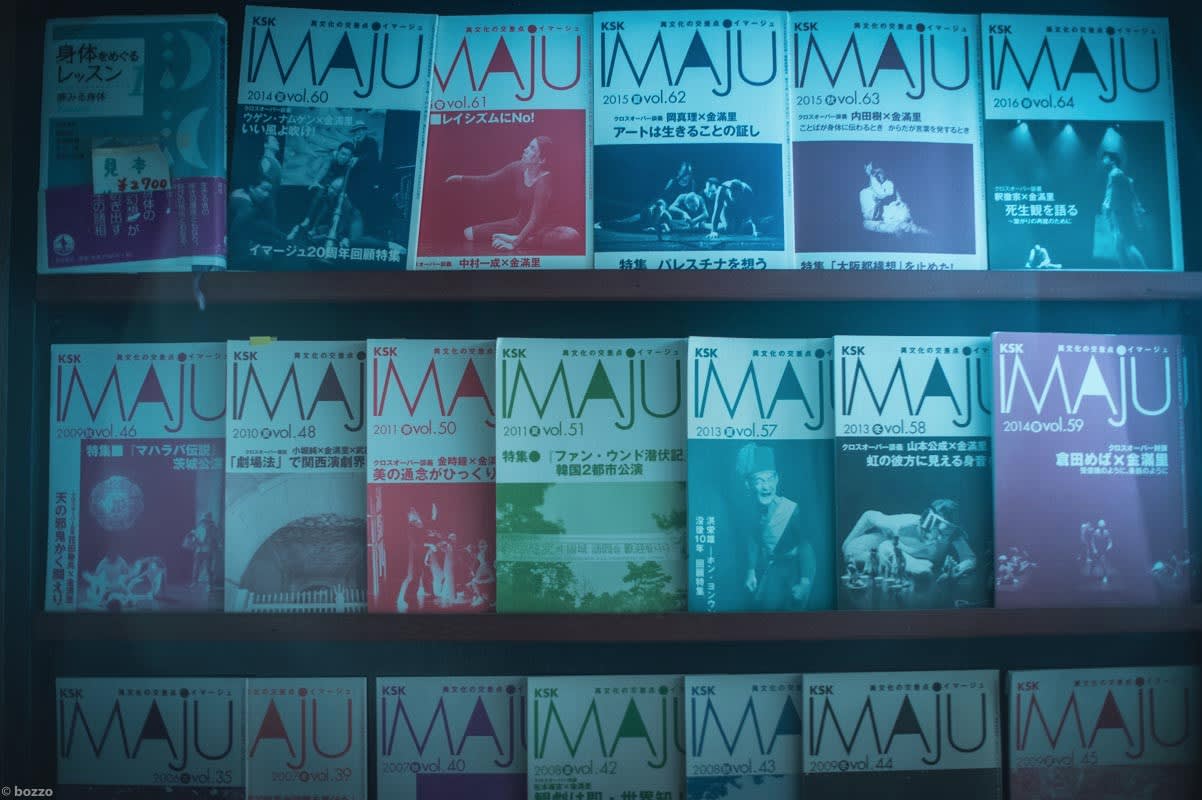牯嶺街少年殺人事件@新宿武蔵野館
4時間ものの映画。
1961年の混沌と不安が渦巻く時代の台湾を舞台に、
少年たちが徒党を組み争い、殺人を犯すまでの実話を基にした物語。
まずもって情景が美しい。
日本統治時代の日本家屋と裸電球、
開けっ放しの窓をすり抜ける風、
舗装されていない土道に側溝、
鉄製ブレーキの自転車…。
しかし展開する物語は穏やかではない。
国民党独裁に伴う本省人と外省人の争いやら、
本国共産党への軍事圧力で台湾自体のアメリカ支配も強まり、
ドルが大量流入するなど、政治が不安定であると、
思想統制や監視、吹聴、密告などなど、生活レベルでの些末な争いも絶え間なく。
当然コドモ社会においても親世代同様、
党派が乱れ、鉄砲や日本刀(統治下の名残)など
物騒なものが手に届く範囲にあり、
その結末に殺人事件が起きる。
それらの出来事をヤン監督は、ある種
不親切な手法で紡いでいく。
ナレーションは入らず、フレーミングも照明も客観的で説明不足。
できるだけ感情移入をさせまいと一歩引いて並列に落とし込んでいくから、
登場人物の背景も探り探りだし、あまりに暗くて
何が起こっているのか分からないシーンまである。
それは
「一つの映画は世界そのものである」とするヤン監督の思想…の顕れであり、
世界は
その細部に宿ることへの証左なのかもしれない。
とにかく言えることは、
私たちが日々経験する出来事はすべて、
私たち自身が選んだ結果であり、
その起因は私たち自身にある…ということ。
1961年の混沌とした台湾の政治情勢によって、
ひとりの中学生が女学生を刺し殺すのであり、
思想統制によって家族の気持ちがバラバラに崩れ落ちるのだ。
私たちが今生きる現代社会においても、
日々必然として事件が起こり、事故が起きる。
それをあちら側とこちら側で分断し、
関係ないを決め込んでみても、
その因子は自分たちの中に抱えているのだ…ということ。
オウム事件しかり。安倍政権しかり。
「社会は思想が物化した成果物」と云ったのはハンナアレントだけど、
人々の思想そのものが言語化され言葉で発せられる前から、
人々は空気で選択し、無意識がカタチとなって顕れる…、それが社会だと。
その恐怖を体感した4時間だった。
エドワードヤン監督の映像言語の強靱さには、驚かされた。