2020年 4月28日(九州医療センター病室にて)
「歴史を紀行する」司馬遼太郎:著
●各章構成(12都市をめぐる歴史紀行文)
・高 知 竜馬と酒と黒潮と
・会 津 会津人の維新の傷跡
・滋 賀 近江商人を創った血の秘密
・佐 賀 体制の中の反骨精神
・金 沢 加賀百万石の深い眠り
・京 都 好いても惚れぬ権力の貸座敷
・鹿児島 独立王国薩摩の外交感覚
・岡 山 桃太郎の末裔たちの国
・盛 岡 郷土閥を作らぬ南部気質
・三 河 忘れられた徳川家のふるさと
・山口萩 維新の起爆力・長州の遺恨
・大 阪 政権を亡ぼす宿命の都

地域に根付く習慣や思考性、自然環境や歴史風土に洗われた人々、歴史上の人物を通じての「人間止観」「歴史観」「地理風土観」が見てとれ、結構面白かったなぁ~。
歴史の大いなる変遷の時期における人物像や地域風土に裏打ちされ謂わば風習や指向性や人々の発想とかが、独特の司馬史観で炙り出されていく。
振り返ってみれば、糸島半島の小さなエリア内に置いてさえ、志摩、二丈、前原街道のそれぞれの地域で、風土や生活習慣の違いを感じる。
更に言えば、桜井(農業基盤)と野北(漁業基盤)の集落毎にその生活リズムや思考性に違いがある事さえ、なぁ~んとなく実感できる。
年間の四季を通じ、数家族(寄合毎)が協力しての水路管理や農作業を伴い、中長期的思考と内部指向が強く働く田園地域。
自然環境(風雨や潮の流れ)に命と日々掛ける生活リズム、更に外(外洋)に向け開かれた指向性を持っと思われる漁村地域。
それぞれの特質が、自然に形成されていくのであろうか?
それらに加え、戦国乱世~近代迄の権力集団や集落間の争い等も通じ形作られた風土というものがある様にさえ思える。
紀行文『街道をゆく』を、続けて読むキッカケにもなった本である。
盛岡以外の地域は、仕事や観光で訪れたことがあるが、再び訪問したくなった。記憶が曖昧にて再度の読み返しとなったが・・・結構、面白くベッドで読み耽った一時となる。
時代・社会の危機の時にこそ、人間の特質が明瞭に現れる。・・・とか?
いざという時、愈々是からという時に避けていく人あり。
最後まで決着をつけるべく進みゆく人あり。
傍観者的に廻りの様子見の人あり。
正しく人夫々であり、いつの時代も同じやなぁ~と思える。
翻って己が生き様は、如何?!
決して傍観者的生き方でなく、可能な限り生涯真っ向勝負でチャレンジしゆく人生でありたいものである。
読後に改めて己に言い聞かせる如く、思いしこと也。










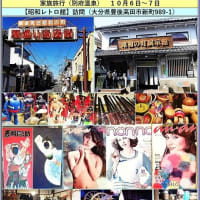
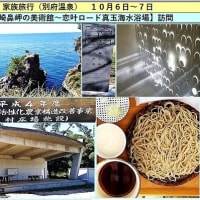

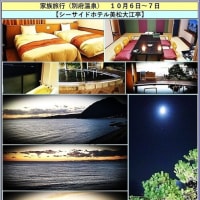

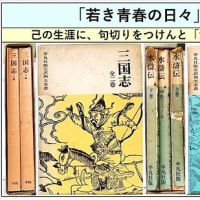
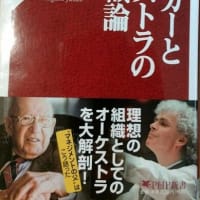
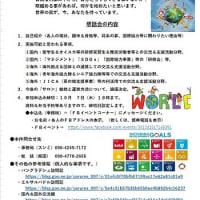

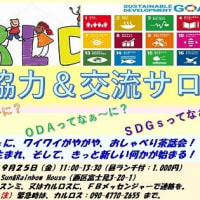
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます