3月10日(土)に、文京アカデミーで「本駒込」について話をすることになり、新たに本を読んだり、出掛けたりしている。3日前には真砂町にある「文京ふるさと歴史博物館」を訪ね、「神明町貝塚」について調べ写真撮影をして来た。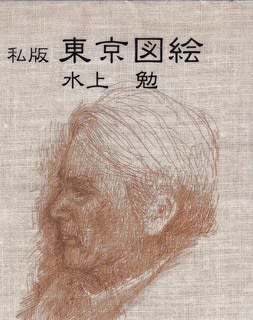 目赤不動についてはネットで検索すると、何故か、水上勉著『私版 東京図絵』がフィットした。早速、区立図書館にオンライン予約し、借りて読んだ。その「動坂目赤不動」の稿の最初の一行に目が釘付けになった。
目赤不動についてはネットで検索すると、何故か、水上勉著『私版 東京図絵』がフィットした。早速、区立図書館にオンライン予約し、借りて読んだ。その「動坂目赤不動」の稿の最初の一行に目が釘付けになった。
“父が建てた目赤不動は、動坂の途中にあった”
目赤不動を水上さんのお父さんが建てたという記述に驚くと同時に、目赤不動は江戸寛永年間に南谷寺へ”引越”したはずだなのに、1930年代頃にいまだ動坂に目赤不動があったとの記述が不思議で解せなかった。
『東京図絵』は、1994年6月から翌年の9月まで朝日新聞の東京版に連載され、単行本が出版された後、1998年に朝日文庫のシリーズに収められた。水上さんは1940(昭和15)年、21歳の時に初めて上京し、駒込蓬莱町の勝林寺を染井に移築する仕事をしていた父を訪ねていた。お父さんは腕のいい大工だったのだ。
水上さんはその後、幾度となく東京を訪ねた。文学の師・宇野浩二氏との交流、幸田文さんの思い出、女性遍歴などが綴られている。文京区に限っても、旧名の駒込蓬莱町・神明町・初音町・冨坂二丁目・本郷森川町などが登場してくる。かつて読んだ『雁の寺』や『飢餓海峡』などの名作の著作に関わる話にも及び、懐かしくも楽しく読んだが、今回は「目赤不動」に限って綴っておきたい。
ここから綴りは、“不思議で解せなかった”点を私なりに推定したものである。
「動坂目赤不動」の稿では、戦後早々森川町に住んでいた宇野浩二氏の口述筆記のときの記憶が書かれている。「・・・観潮楼跡などが焼け残り、旧屋敷町はおおかた健在だった記憶があるのに、動坂の目赤不動だけは屋根も壊れ、祠堂は跡形もなく石段だけがあるだけだった。」「そこの狭い台地の畑の中に、コロボックルの自然石の石碑が立っていたのをおぼえている」とある。
私の赤目不動についての理解は概略次の様なものだった。
「元和年間に万行和尚は、現在では動坂と呼ばれているこの地に庵を結び、不動明王像を安置し、赤目不動と呼ばれるようになった。その後、鷹狩に来た家光により、現在の本駒込1丁目へ移転させられ、目赤不動と改称され、「南谷寺」の寺号を与えられた。旧地は赤目堂跡と称されていたが、1793(寛政5)年に日限(ひきり)地蔵堂が建てられた」
ここからは私の推測だが、日限地蔵堂が建てられた時点で、赤目不動は無くなっていはいなかった。日限地蔵の傍らに、赤目不動とそれを祀る祠堂は細ぼそと残された。人々の間では”目赤不動”と膾炙されたかも知れない。水上さんのお父上さんはそこにあった、その祠堂を作り替えたと理解するのが正しいのではないだろうか。
 初めて上京してから54年後の1994年に水上さんが目赤不動を訪ねると、戦後早々に訪ねた時にはあった祠堂上の台地はビルになってしまっていた。落胆しつつも、その後水上さんは徳源院と南谷寺を訪ね、徳源院ではコロボックルの碑に再会し、南谷寺では不動明王を垣間見ている。それは現在私達が見る風景と同じである。(写真:徳源院のコロボックルの碑を訪ねる水上さん)
初めて上京してから54年後の1994年に水上さんが目赤不動を訪ねると、戦後早々に訪ねた時にはあった祠堂上の台地はビルになってしまっていた。落胆しつつも、その後水上さんは徳源院と南谷寺を訪ね、徳源院ではコロボックルの碑に再会し、南谷寺では不動明王を垣間見ている。それは現在私達が見る風景と同じである。(写真:徳源院のコロボックルの碑を訪ねる水上さん)









